さかしまのジゼル <第19回>
第3部 V オペラ座の新女王
かげはら史帆
コツ、コツ、コツ。
馬の蹄がステップを踏む、軽やかな音──。
かつてマリー・タリオーニの象徴として畏れられていた足音。
その音でオペラ座を制する者は、いまやカルロッタ・グリジに代わろうとしていた。
9年前、新作バレエ『ラ・シルフィード』が、タリオーニを一介の女性ダンサーからオペラ座の女王に変えたように。
いまフォワイエ・ド・ラ・ダンスで創られている新作が、グリジの頭上に新女王の冠を築きつつあることを、ジュールはまざまざと感じていた。詰め物で膨らんだ固い爪先と、それを支えるほっそりとした足首。天使の光輪さながらの円を形づくる真白な二の腕と、薔薇の蔦のようにしなだれる華奢な手首。光に当たれば青々と澄みわたり、うつむけば神秘的な紫を帯びる一対の瞳。小兎のようにエネルギッシュな跳躍と、なめらかに床を滑る精確で繊細な足さばき。
彼女の魅力のすべてが、「ジゼル」という作品に統べられていく。
第1幕、恋する村娘。第2幕、死せる精霊ウィリ。──同じ魂を持つふたつの役柄へ。
ただ、グリジに向けられる女性ダンサーたちのまなざしは、タリオーニに対するそれとは違うように見えた。
「かわいそう」
振り写しの初日、ジゼルの狂乱のシーンを見て泣いていた彼女たちは、それ以来、同情の念をにじませて彼女に接しているようだった。リハーサルの合間に髪のほつれを直してあげたり、床に小さなじょうろで滑り止めの水を撒いてあげたり、ナプキンにくるんだ手製のお菓子を分けてあげたり。それは、ジゼルの村の女友達が病弱な彼女をいたわるさまにも似ていた。
ジュールは、どこか不可解な想いに囚われながらその様子を眺めていた。
テオフィル・ゴーティエの台本を最初に読んだときには、ジゼルというヒロインは、まるで現実感のない男の妄想だとしか思えなかった。村のどの女の子よりも可愛くて、浮世離れした、弱々しい娘。男が女を買う生き物であることも、女もまた自分を買わせるために男を騙す生き物であることも、毎夜の経験からとうに知っている群舞の女性たちが、ジゼルのようなキャラクターに共感を覚えるのだろうか。しかもジゼルは、自分を騙して死に追いやった男をかばいつづけ、最後には赦してしまうのだ。
森に迷い込んだ男たちを次々と殺してしまうウィリの女王──ミルタのような女のほうが、よほど同性から支持を集めそうな気がした。かつて男に裏切られ、死して精霊になってもなおその恨みを抱きつづけ、魔法の杖のようにローズマリーの枝を操り、若い男たちを踊り狂わせて死に追いやっていく。憎しみを振りかざして男に罰を与える女であるミルタと、情けでもって男の罪を赦してしまうジゼル。自分自身が女性ダンサーだったとしたら、ミルタとジゼル、どちらの役を踊りたいと思うだろう。
────自分自身だったら?
膝の上で拍を刻んでいた指が、いつの間にかぎこちなく宙に浮いたままになっていた。
ジュールの異変に気づいたのか、アドルフ・アダンがオーケストラ・ピットに向けて合図を送った。ソロのヴィオラがまず止まり、弦楽器が止まり、楚々としたアダージョが劇場の暗がりに溶けて消えていく。客席に飛び降りたアダンが、平土間席の最前列に座っていたジュールのところへ駆け寄ってきた。試奏者たちの小さな咳払いと、楽譜をめくる音のさざなみが、上階の無人の桟敷席にまでこだまする。オーケストラ団員だけを集めた音楽リハーサルは、佳境を迎えていた。
「小節数の指定を間違えたかな。それなら書き直すが……」
「いえ」雑念を追い払いながら、ジュールは立ち上がった。「短時間で書き上げたとはとても思えない。第1幕もよいですが、第2幕はまた格別で……。あなたは素晴らしい作曲家だ」
「よかった。あなたこそ素晴らしい振付師だ」アダンは感極まったようにジュールの手を握った。「ジゼルとアルブレヒトの哀しい情愛を、マイムに頼らずに、ダンスでもって細やかに表現する……こんなバレエは他にはなかった。私もできる限りの力で応えました」
「そうおっしゃっていただき光栄です」
「願わくば、アルブレヒト役があなただったらもっとよかったのに」
耳にすべりこんだ声を躱して、ジュールはアダンの手を握り返した。
「リュシアンの目覚ましい成長を見れば、きっとご意見も変わりますよ」
グリジのデビュー公演の『ラ・ファボリータ』のときには、彼女の隣にいるのが自分であればという欲望に苦しめられたのに、いまのジュールは、アルブレヒト役に対する執着を完全に失っていた。むしろ、リュシアンが日々、悪戦苦闘しながらアルブレヒト役を我が物にしていくさまを快く思うようにさえなっていた。
変わったのはグリジも同じだった。フォワイエや楽屋でジュールにべたべたと接するのをやめて、ひとりで空いたレッスン室に籠もり、夜遅くまで練習していることが増えた。彼女なりの役作りなのだろうか。
その反動なのか、家に帰れば交際して間もない恋人のようにジュールに甘えてきた。辻馬車から飛び降りて玄関の扉を開けるなり、マリーに夕食のじゃがいもスープを食べさせていたジュールの背中に飛びついて、頬を寄せながらささやくのだった。
「早く結婚したいな。ねえ、式はいつ挙げるの?」
「『ジゼル』の初演が成功したら、でどうかな」
皿の底にスプーンを沈めながらそう答えると、化粧を落として子どものように赤らんだ頬をふくらませた。
「成功しなかったら、結婚は先延ばしってこと?」
「そういうわけじゃないけど……」
ジゼル役から解放された深夜の彼女は、むしろ天真爛漫なジゼルに似ていた。ジゼルもまた、アルブレヒトにこんな風に結婚をねだったのだろうか。結婚への憧れが人一倍強かったことは確かだろう。だからこそ、クールランド大公の娘バチルドから、自分には婚約者がいると打ち明けられると、その幸福な愛の成就を我が事のように喜び、ひどくうっとりとした顔で天を仰ぐのだ。彼女の婚約者が、自分の恋人であると知らないままに。
「それなら、初演が終わったら絶対ね。ママもいとこたちも来てくれないと思うけど、私たちとマリーが幸せならいいんだもの」
こんなに嬉しいことを言ってくれるのに、かすかに腹立たしさを覚えるのはどうしてだろう。彼女の肩をつかまえて、皮肉を言ってやりたくなる衝動に駆られた。早く結婚したい、だって? 俺が5年間ずっと我慢してきた言葉を、随分やすやすと口にするんだな。
夢を無邪気に口にできるのは、相手から拒絶されないという確信を持っている側だけだ。もしかしたら、恋人の耳に結婚の夢をささやいたのは、ジゼルではなくアルブレヒトの方だったかもしれない。そんな想像がジュールの頭をもたげた。結婚しよう。葡萄の収穫祭が終わったら。クリスマスを過ぎたら。春が巡ってきたら。葡萄が花をつける頃になったら。未来へと延ばされる甘い約束。花びらをむしりながらその成就を待ちつづける娘。
「……信じても、いいのか?」
知らず知らずのうちに、ジュールの口からそんな言葉が漏れていた。背中に当たっていた温かな呼吸が、ふっと止まる。
「……信じられない?」
言葉は途中でかすれて、潰れた卵のように床に落ちた。背中からジュールの顔を覗きこんだグリジの瞳は、哀しみをたたえて瞬いていた。ジュールがあいまいに首を振りながらそっと視線を逸らすと、グリジのほっそりした両腕がジュールの肩に絡みついた。

『ジゼル』の初演が終わったら。
グリジと結婚式を挙げて、晴れて正式に夫婦になる。
そして『ジゼル』成功の功績を称えて、主演のグリジは大幅に昇給し、影の振付師であるジュールも、あらためてオペラ座入団のオファーを受ける。
敵方の予想外の陰謀のおかげで1年遅れにはなったが、当初思い描いていた計略はすべて実行されることになる──。
「そういえばあんた、俺のファンでもある、と言っていたな」
ジュールがそう問うと、ゴーティエの唇から、忍び笑いの形を描いた紫煙がこぼれ出た。
「ええ、それが何か」
「『ジゼル』の台本を書いて、オペラ座に売り込んで、俺に作品の振付をさせるように計らったのは、ひょっとして俺のためなんじゃないか? あんたは、最初から、俺のキャリアを助けるために動いてくれたんじゃないか……?」
ふむむ、と謎めいた鼻息が漏れた。
「あなたには友愛の情を抱いていますし、グリジ嬢は僕のミューズだ。それ以上は、ご想像にお任せしますよ」
「ミューズ、ねえ」
「しかし恩を着せるつもりはございません。あなたがたのおかげで、僕は、芸術家としての最高の栄誉を手に入れるのですから」台本作家は、楽屋で仮縫いの衣装を合わせている男性ダンサーたちを指さした。「ほら、ご覧なさい。僕が紙の上に書きつけた言葉が、まもなくオペラ座の舞台に乗る。太陽王ルイ14世の威光に照らされて、僕と僕の詩が、偉大な芸術史の一部になるんですよ」
「それが、あんたにとってのオペラ座の価値か……」
腰の革ベルトに大きな狩猟ナイフと角笛をぶらさげるのに苦心しているヒラリオンの衣装係。平民を装う貴族という役どころをどう表現するか、ズボン用の絹布をリュシアンの脚にあてがいながら話し込んでいるのは、アルブレヒトの衣装係だろうか。群舞の衣装係は、村人用の灰色がかった地味な胴着と、貴族用の肘がふくらんだ鮮やかな緑の胴着を抱えて、楽屋と衣装室を往復している。みなが忙しく立ち回っているが、それでも女子楽屋の天地がひっくり返るような大騒ぎと比べたらずっと穏やかだった。『ジゼル』に出演する男性ダンサーの数は、それだけ少ない。なにしろ第2幕の群舞は全員女性で、男性はアルブレヒトを含む2、3名しか舞台に上がらないのだ。
その人もまばらな男子楽屋に、グリジの衣装係をつとめる女性が飛び込んできた。ジュールの目の前に、待ち針がついたままの白いエプロンをかざす。
「衣装係長のムッシュー・ポルミエからの質問です。ジゼルのエプロンは、もっと短いほうがいいでしょうか。中世の農民服をモデルにすると、長さはこの程度が妥当ということですが」
振付を任されているからといって、衣装に口を出す権限はない。メートル・ド・バレエに聞いてくれ、とジュールが返そうとした矢先、横からゴーティエが割り込んできた。
「ああ、もっと小さく、エプロンなんて飾り程度で充分だよ。なんたってジゼルは、家業そっちのけで踊りたがる娘なんだからね。ほかの村娘とはそこが違うんだ」
エプロンを抱いて駆けていく衣装係の背中を見送りながら、ジュールは肩をすくめた。
「なるほどねえ。さすがジゼルの生みの親だ」
「死因の件であなたから手厳しい指摘を受けましたからね。サン=ジョルジュ侯爵と一緒に、必死で設定を練り直しましたよ」
「家業に興味のない娘か。なんだか、ジゼルは俺の子ども時代みたいだな」
ジュールの言葉に、ゴーティエが小さく目を光らせた。「ほう」
「親父は家具職人で、劇場の道具係に転職した。おふくろはリヨン名産の織物を作っていた。俺は親の背中を見ようともせずに、毎日踊ることだけを考えていた。それが昂じて、ついには地元を飛び出してパリに行ったんだ」
「なるほど。バレエとの駆け落ちをなさったわけですな」
「作家はうまいことを言い過ぎる」
「それが仕事ですからね」
「美しい女に入れあげるのも仕事、というわけか」
ゴーティエはしげしげとジュールの横顔を見つめ返して、肩をすくめた。
先ほどの衣装係が、今度はグリジの腕を引っ張ってやってきた。ふたまわり小さくなったエプロンを腰にあてがう。
「これくらいでどうでしょう?」
「いいね。でも、かなり雰囲気が変わるな……」
ステップを踏むたびに、膝のあたりでエプロンが品良く翻る。そんな想像をして振付をした。だが、腰飾りに毛が生えた程度のサイズだと、飛んでも跳ねても揺れないし、指でつまんで遊ばせることもできない。そうなると、踊りを少し変えたほうがいいだろう。
できればグリジを連れ出して振りを作り直したかったが、第2幕の衣装合わせが控えていて、しばらくは楽屋を離れられないという。村娘の衣装をまとったグリジにすっかりのぼせているゴーティエを置いて、ジュールはひとり廊下に出た。上着やら羽つき帽子やらが飛び交う人波をかきわけ、空き部屋を探していると、フォワイエ・ド・ラ・ダンスが無人なのに気がついた。道具係が制作をしている途中なのか、第2幕の墓石のセットだけが、下手側にひっそりと置かれていた。まだ色を塗っていない薄べったい十字架型の板地に、「ジゼル」という文字が浅く彫られている。
靴とジャケットを脱いで、部屋の中央に立つ。衣装合わせの喧騒ははるか彼方に遠ざかり、深夜の森さながらの張り詰めた沈黙が快い緊張を誘った。薄い絹靴下を履いただけの足に、ひんやりとした床の感触が広がる。
伴奏者がいないので、頭のなかで拍を取るしかなかった。第1幕の序盤、恋人に裏切られる夢を見て不安になったジゼルが、マーガレットの花で占いをする場面を思い浮かべる。花びらをむしって、好き、嫌い、好き、嫌い──結果は吉。すっかり安心したジゼルは、片手で恋人の腕を取り、もう片方の手でエプロンをつまんでワルツを踊り始める──そうだ、ここの振りを変えたい。でも、アルブレヒトと腕を組んでいて、どこまで身体の動きが自由になるだろう。だめだ。やっぱり、パートナー役がいないと考えにくいか……
真横から目の前に突き出された二の腕に、ジュールははたと動きを止めた。
腕を伝うように視線を上げると、そこにいるのはジョゼフ・マジリエだった。いつの間にフォワイエに入ってきたのだろう。男の足音は気づきにくい。舞台で戦うための強靭な爪先をもたない性別のダンサーは、その柔和な瞳にどこかもの思わしげな色を浮かべて、ジュールに向けて肘を差し出していた。
戸惑っていると、ジョゼフは半ば強引にジュールの腕に自分の腕を巻きつけ、ステップを踏み始めた。ジゼルとアルブレヒトのデュエットだ。無理やり引っ張られたジュールは、その勢いでよろめいた。
「何をやってるんだ」
間の抜けた声が出る。男ふたり、恋人同士のダンスを踊るなんて。何の冗談かと笑って振りほどこうとしたが、ジョゼフの顔はふざけるでもなく、アルブレヒト役にふさわしい優雅な微笑みを浮かべている。ジュールが肩をつかんで押しとどめようとしても、彼は一向に踊るのをやめない。
「足を踏んじまうぞ」
「きみも一緒に踊れば、踏まずに済むよ」その美貌にふさわしい涼しげな声が返ってきた。「新作の準備は順調みたいだね」
少しも動じる様子がなくたおやかにジャンプするので、ジュールもつられて跳び上がる。ジョゼフがダンサーとして一線を退いてからはもう数年が経っているはずだったが、『ラ・シルフィード』のジェームズ役を踊ったときの身のこなしはまだ衰えていないようだった。
ジョゼフは、今回の『ジゼル』の作品制作には、振付師としても教師としても参加していない。ただ、どういうわけか振り写しやリハーサルの現場には必ずやってきて、壁際に椅子をぴったりと寄せて座り、しじゅう興味深そうに稽古の様子を眺めているのだった。どうりで振付を隅々まで記憶しているわけだが、それにしたって様子がおかしい。いぶかしげな表情を隠さないジュールに気づいたのか、ジョゼフはようやく腕をほどいてジュールから離れた。それから、ゆっくりと口を開いた。
「僕は、きみがこういうバレエを作るとは思っていなかったよ」
ジュールは足を止めた。言葉の意味を判じかねていると、ふいにジョゼフは、第1幕の音楽の一節を軽く口ずさんだ。ジゼルが恋人の裏切りを知ってショックを受ける場面だ。フル・オーケストラの雷が、激しい光を放ちながら脳天に落ちる。
「男が主役になれるバレエを作るために、きみはオペラ座に乗り込んできたと……。そう信じていた」
ジゼルの絶望と狂気を予兆する調べが、ジュールの思考を奪っていく。思わず、こめかみに手のひらを押し当てる。
「ウィーンできみが作った『ニンフと蝶々』や『コボルト』の評判は耳にしていた。どちらも、男性の主役のほうが女性よりもずっと目立つバレエだと知って、きみが新天地でやりたいことをやれているんだと嬉しかった。パリに戻ってきたときはひそかに期待もした。きみが、このフランスで、男性ダンサーの威光を取り戻す革命を起こしてくれるんじゃないかと思って……」
「無理だよ」さえぎった声は、水気を含んで震えていた。情けない声音が自分の耳に届いて、羞恥心が背中から這い上がる。ふたたびジョゼフが、狂乱の場のメロディを口ずさみ始めた。なんなんだ、こいつは。こみあげる怒りにまかせて言葉をぶつける。「きみのほうがずっと早くから、わかっていたじゃないか。オペラ座の客は女の子しか観に来ないって、かつて俺に諭したのはきみじゃないか。グリジの評が少ないことへの不満を言った俺を見て、大人になったな、と笑ってくれたじゃないか」
エプロンのことなぞ、もうどこかに吹っ飛んでしまった。フォワイエから立ち去ろうとしたが、どういうわけか出口が見つからない。誰かが自分を取り囲んでいる。村人たちだ。髪を振り乱して恋人の不実を訴えるジゼルを、心配そうに見つめる人、人、人。いないはずの群舞たちの輪。そのなかのひとりが、動きを封じるように肩をどんと突く。よろめいたジュールは、その場に仰向けに倒れ伏した。天井に顔を向けながら荒い息をついていると、それを上から覗き込むジョゼフの顔があった。若い頃から、喜びも哀れみも控えめにしか見せない、四方八方どこから見ても崩れのないその端麗な面差し。
「澄ました面をして、きみも本当はオペラ座に不満を持っていた、ということか……給料も、地位も、演目も……」
「ジュール」
「いつも俺を気の毒そうに見つめるだけだったくせに。俺が諦めたら、今度は批評家気取りで、まだ足りない、もっと戦えと言うのか?」乾いた笑いが喉をひくつかせる。「……ああ、そういうことか。俺が我を捨てて従順になったら、次期メートル・ド・バレエの地位が俺に盗られるかもしれないもんな。俺には永遠に馬鹿な反逆児でいてもらわないと困るんだろう」
「違う、違うんだ。きみを責めているわけでも、陥れようとしているわけでもない。信じてくれ」汗でぼやけた視界の向こうで、彼の唇が上下に動いている。「僕はずっと考えていたんだよ。朝から晩までずっと『ジゼル』の稽古を観ながら。そうしたら、あるとき気がついてしまったんだ。踊りがこの世の何よりも大好きなのは、愛するパートナーに裏切られて気が狂って死んでしまいそうなのは、グリジ嬢のほうじゃなくて……」
床を両足で蹴り飛ばして、ジュールは身を起こした。頭がひどく痛む。頭蓋を両側から潰されているようだ。かつて風刺彫刻家に仕立て上げられた、あの胸像のように。もうとっくにひしゃげているのに、もうとっくにみにくいのに、これ以上俺の顔をぐちゃぐちゃにしないでくれよ。そう叫んだ言葉もまた、ゆがみきった唇に吸い込まれて消えていく。
両手で額を抑えながらフォワイエから出ていこうとしたが、それを制するようにジョゼフが立ちふさがった。ジュールの鼻先に、冷然と指を突きつける。ローズマリーの枝が空気をこすってざわめく音が脳裏に響いた。ミルタだ。ジョゼフがミルタの役を演じている。世の異性という異性すべてを憎む怨念の女。新参者のウィリであるジゼルに、自分を裏切った恋人を殺すように教唆する女。
「よく似合うよ。……きみは、女のように美しい顔とずっと褒められていたな」
そう皮肉を言うと、相手からも、同じトーンの言葉が返ってきた。
「きみのほうこそ、男版シルフィードと褒められてきたじゃないか」
ジュールの胸に、狼狽とも怒りともつかない感情が粟立った。だからなんだ、と言いかけて、そのまま唇が凍りつく。男らしからぬ男という天分を神から与えられたことで、辛うじてバレエの舞台の上に居場所を見つけてきた自分とは、自分たちとは、いったい何なのか。答えがすぐ目前にまで迫っているのはもうわかっていた。いまここで、彼が振りかざすあのローズマリーの枝に従えば、一歩踏み出して踊りだせば、そこに正解がある。
背後で、小さく息を呑む音が聞こえた。
振り返らずとも、フォワイエの壁に掛かった大きな鏡にその主は映っていた。第2幕のジゼルの衣装の仮縫いを付けた彼女は、身じろぎひとつせずに、ジュールとジョゼフが交わす、揉み合いともマイムの応酬ともつかぬ奇怪な場面を見つめていた。死装束のような白銀のチュールだけが、彼女の心の動揺を表すように微かに揺れている。
だが、彼女は背中に手を回して、仮縫いのチュチュを脱ぎ捨てた。
薄手の稽古着ひとつになった彼女が、裸足のままで踊りだしたのは、アルブレヒトのソロだった。
恋人を死に追いやってしまった男を、カルロッタ・グリジが演じ、踊っている。己の罪に心を窶し、償うすべも思いつけぬまま、墓の前でうなだれている男を。その悲嘆を、その絶望を、詫びて楽になりたいという浅ましい願いを、すべて体現するように。
ジョゼフの指が、ジュールの目の前で再び動きだした。
あの裏切り者のアルブレヒトを始末せよ。ミルタがジゼルにそんな命を放つ。おまえが命を落としたときのように、あの男も踊り狂わせて、殺してしまえばいい。彼の──彼女の指がそう言っている。
ジゼルはミルタの強力な魔力に逆らえない。背中の小さな羽根を不安げにはためかせ、取り憑かれたように宙を旋回しはじめる。そのジゼルのあとを追うように、アルブレヒトもまた踊りはじめる。一心不乱に跳び、回り、疲れて倒れ込みそうになったところでまた、激しい跳躍を強いられる。自分の意志をすっかり失った人形のように。
踊らせるのをやめてほしい。どうか命だけは助けてほしい。そう叫びながらも、アルブレヒトはだんだんと己の天命を悟り、安堵の境地に足を踏み入れる。もう、いい。自分の命でもって彼女を殺した罪を償えるのならば、これでいい。生きて帰り、大公の娘バチルドと結婚させられ、王侯貴族どもが支配するあのきらびやかで虚しい世界で半ば死んだような人生を送るくらいなら、かの人の死因をなぞるように自分も踊り狂い、彼女の聖なる爪先に跪いて絶命したほうがずっといい。どうか、罰を負わせてくれ。それが自分にとっての償いであり、唯一の愛の証明なのだから…………。
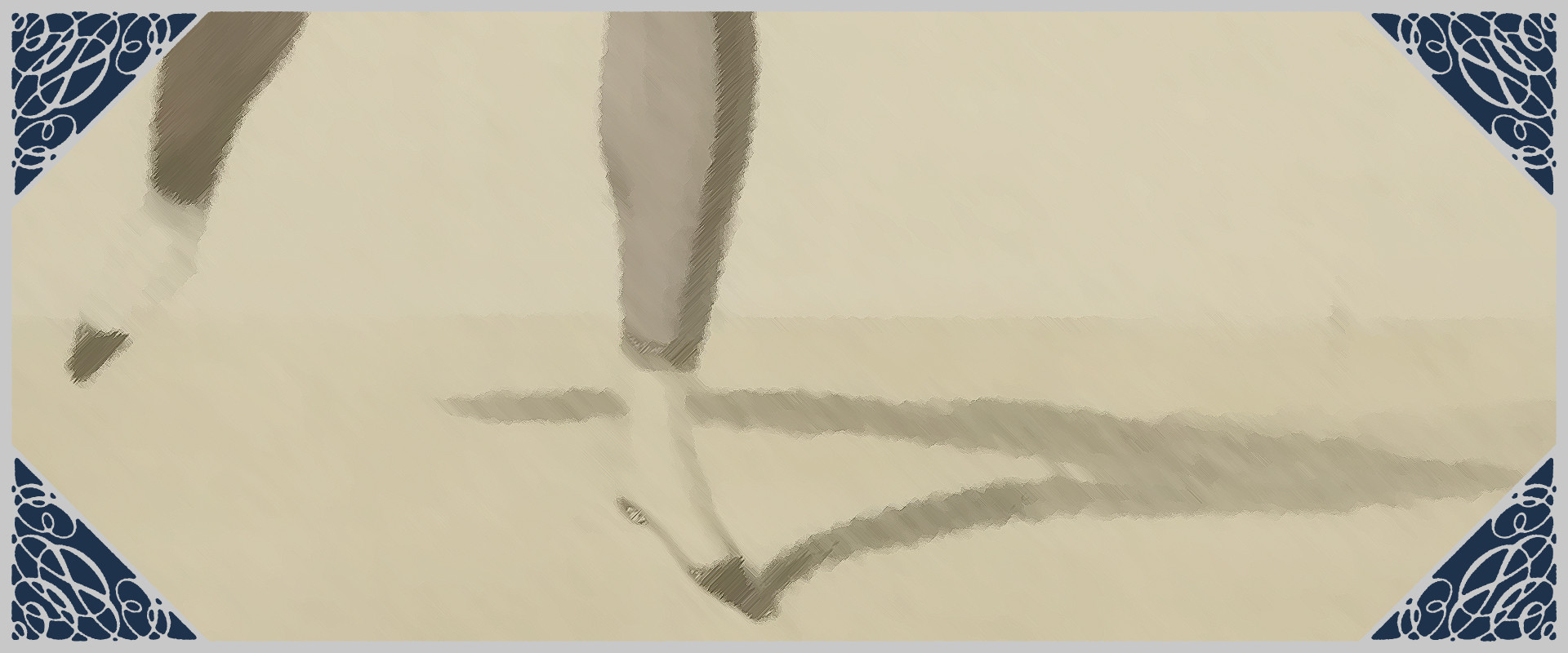
声と足と、どちらが先に動いたのかわからなかった。
気づいたときには、ジゼルの墓石を腕でなぎ倒していた。十字架が横倒しになり、木の板が床の上ではじけるような音を立て、大きな亀裂が走った。驚いて目を見開いたジョゼフを強く押しのけて、倒れ込んだグリジのもとに駆け寄る。
「だめだ、だめなんだ、これでいいわけがないんだ」
知らず知らずのうちに、言葉が口から飛び出していた。うつ伏せになって荒い息をつく彼女に覆いかぶさって、その華奢な肩を抱き寄せながら、ジュールはつぶやいていた。
「これじゃ、だめなんだ……」
Back Number
<第1回> イントロダクション──1873年
<第2回> 第1部 I みにくいバレエダンサー──1833年
<第3回> 第1部 II 遠き日の武勇伝
<第4回> 第1部 III リヨンの家出少年
<第5回> 第1部 IV オペラ座の女王
<第6回> 第1部 V 俺はライバルになれない
<第7回> 第2部 I 転落と流浪──1835年
<第8回> 第2部 II 救いのミューズ
<第9回> 第2部 III 新しい契約
<第10回> 第2部 IV “踊るグリジ”
<第11回> 第2部 V 男のシルフィード
<第12回> 第2部 VI 交渉決裂
<第13回> 第2部 VII さかしまのラ・シルフィード
<第14回> 第2部 VIII 最高のプレゼント
<第15回> 第3部 I 仕組まれた契約──1840年
<第16回> 第3部 II 夢見る詩人
<第17回> 第3部 III 狂乱の振り写し
<第18回> 第3部 IV ジゼル、または群舞たち







