さかしまのジゼル <第14回>
第2部 VIII 最高のプレゼント
かげはら史帆
「もし、あのまま悲劇で終わっていたら──」
芸術監督とメートル・ド・バレエの感嘆の声が、ジュールの耳を快く打った。
「ここまでのヒットはなかったでしょうな」
「まさか、たった3ヶ月で20回以上も再演することになるとは。われわれの想像以上の成功ですよ」
まばゆく輝く照明に目を細める観客たちの前に、花嫁姿のイオラがしずしずと歩み出る。彼女が振り返り、優しく腕を伸べたその向こうから姿を現したのは──なんと、花婿姿のコボルトだった。彼は永遠の命を捨てた代わりに、イオラへの愛の力によって人間として生まれ変わったのだ。ふたりの結婚式は、ぶどうの収穫を祝する村の祭とともに繰り広げられ、笑顔で舞う新郎新婦と村人たちのダンスがフィナーレを飾った。
批評家たちは、この作品の賛否を熱く論じた。『ラ・シルフィード』の悲劇のほうがより詩的で格調高い、という声が上がる。いや、『コボルト』のハッピーエンドのほうが寛容の精神にあふれていて好ましい、という声も上がる。そうした議論に触れた客が、興味を抱いて、また劇場に押し寄せてくる。
主役ふたりの力量も話題を呼んだ。コボルトという前例のない役を踊りきったジュールが賞賛を浴びる一方、彼への想いに揺れ惑うグリジの演技や踊りも注目された。これほどに美しい娘が、これほどみにくい精霊を愛するなんてありえない。そう思いつつも、コボルトを見つめる彼女の切なげなまなざしや、恋のよろこびをまとって燃え上がるデュエットを見ていると、たしかにこの愛は本物であると納得させられてしまうのだった。
『コボルト』の評判は、ウィーンの市壁の外にも広がった。ヨーロッパじゅうの劇場が、『コボルト』の再演の相談や、ペロー&グリジへの出演オファーを送ってくるようになった。その誘いを受けて、ふたりはミュンヘン、ミラノ、ナポリ、ロンドンを周遊する巡業に出て、どの場所でも拍手喝采を浴びた。そんな多忙な旅回りの生活を送っているさなか、思いがけない吉報が舞い込んだ。パリの人気の劇場のひとつであるルネサンス座が声をかけてきたのだ。
「……となると、『コボルト』の再演を?」
期待を込めて、ジュールはそう問うた。しかし芸術監督は頭を振った。
「いや、フランスではバレエの上演はオペラ座に限るという法律がありますから、『コボルト』全幕の上演は難しいでしょう。しかし、歌やセリフの要素を入れることで法の抜け穴をかいくぐることは可能です。舞台に上げられる新作を考えましょう。われわれは、ぜひあなたがたに踊ってほしいのです」
これが成功すれば、オペラ座が手に入るのは時間の問題だ。
ジュールはそう確信した。オペラ座関係者とて、最近のふたりの評判を聞いていないわけがない。オペラ座から目と鼻の先にあるルネサンス座で踊るとなれば、必ず青田買いに来るだろう。でも、もし声をかけられたとしてもすぐには応じない。自分はさておき、若いグリジはまだ買い叩かれる危険性がある。ここは大いに出し渋りしたい。焦らして焦らして、しびれを切らした向こうが、言い値の待遇でいいと折れたところで、はじめてオファーを受ける。
もしも、契約がぶじ成立したら──。ジュールの胸は大きく脈打った。グリジに、いまいちど結婚を申し込もう。団のなかできちんとした地位を得られれば、うぶな娘のふりをしてフォワイエ・ド・ラ・ダンスでパトロン候補の紳士に媚びを売る必要もない。彼女ももうすぐ20歳になるのだから、夫婦として堂々と表舞台に出たっていいはずだ。
この計画は、あくまで極秘で進めよう。ジュールはそう心に決めていた。グリジ本人にも、何も言わない。もう自分の将来に王手がかかったと気を緩めてもらっては困るし、プロポーズはとびきり驚かせたい。
「もうすぐ、パパとママの結婚式をやるんだ。でも、ママには内緒だよ」
そっと、マリーの小さな耳にだけはささやき入れた。2歳になったマリーは、もうすっかり赤ちゃんを卒業して、部屋の端から端まで踊るように走ったり、衣装の切れっ端や靴のリボンを振り回したりと、毎日はじけるように遊んでいた。けれどいまは、父親のことばにきょとんと小首をかしげている。結婚式はもうやったじゃない、とでも言いたげな顔つきだ。たしかにこの子は、劇場の客席で乳母の膝に抱かれながら、もう何度となく『コボルト』のラストシーンを観ているのだった。村人たちに祝福されながら踊る、花婿のパパと花嫁のママの姿を。
「なるほど。ストーリー上にオペラの要素を取り入れたバレエ、というわけですか」
ルネサンス座から提示された痛快なアイデアに、ジュールは手を打った。振付は劇場専属の振付師が担当したが、ジュール自身もアドバイザーとして制作に関わることになった。ジュールの役は、子どもの頃に受けたトラウマで声を失った若いジプシーのジンガロ。グリジの役は、ジンガロに命を助けられ、最後には彼をトラウマから解放させる少女ジャニーナだった。
「声を失った」設定のジンガロは、舞台上で歌わない。けれど、ジャニーナは歌う。ロンドン・デビュー以来封印していたカルロッタ・グリジの歌が、やむを得ない事情によってふたたび解禁される。その噂が、パリの観客たちの関心を駆り立てて、初日の劇場は満員になった。口が利けないぶん手足をより大きく広げて空を舞う青年ジンガロ。可憐な声で歌い、繊細かつ軽やかな足さばきでステップを踏む少女ジャニーナ。
1場を終えるごとに、観客たちは面白いほどに湧いた。しかし、ジュールの心は冷静なままだった。
喝采をもらえるだけでは、この舞台は成功じゃない。──
大雨のように舞台に降り注いでくる拍手に頬や腕を濡らしながら、ジュールは客席の一角にじっと目を凝らしていた。手を口元に当てて、せわしなくささやきあっているオペラ座の幹部たちの姿をジュールは見逃さなかった。数年ぶりに見るジョゼフ・マジリエの顔もある。彼は関係者の密談には加わっていなかった。ただ、ジュールの姿をまぶしげに仰ぎ、感極まったように拍手を送っていた。見つめ返すと、目が合った。穏やかな微笑をたたえた懐かしい唇が、はっきりとこう動いた。
「おめでとう」
舞台袖に駆け戻るやいなや、ジュールは倒れ込んで仰向けになった。まだ続いている拍手と、ダンサーや歌手たちのせわしない足音が、床を伝って地鳴りのように身体に響いている。
これで、望んでいたものが手に入る。
あとは焦らしに入るだけだ。彼らが陥落するのは、予想よりずっと早いかもしれない……。
万感の想いに打たれて目を閉じていると、人の気配を感じた。片目をあけると、グリジが両膝をついて、真上からジュールの顔をのぞきこんでいた。どうしたの? とその唇が動くより前に身を起こし、白い房飾りの付いた腕を引き寄せて思い切り抱きしめた。
「愛している、カルロッタ」
耳元で、小さく息を呑む音が聞こえる。真紅の帽の下で汗に濡れている彼女のおくれ毛に、そっとキスを寄せた。
「もうすぐ、最高のプレゼントをきみに贈れるはずだ」
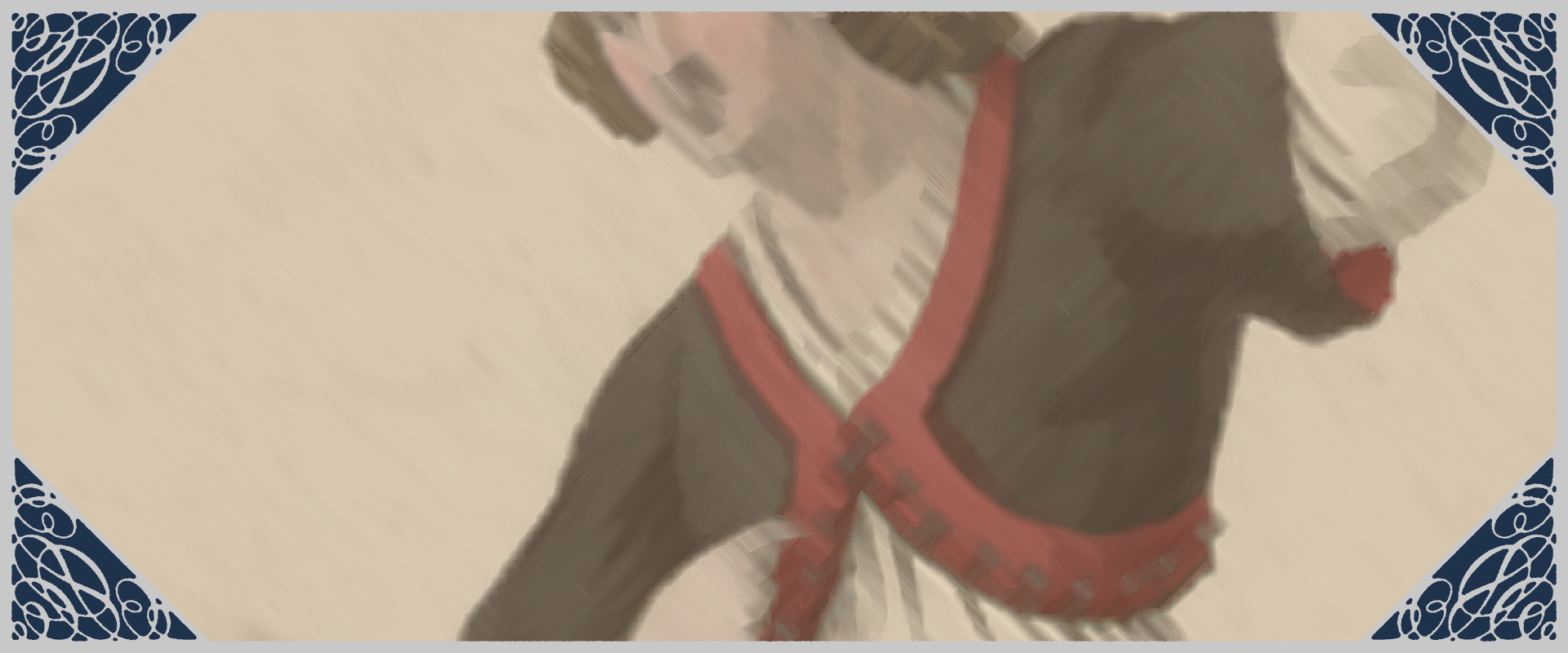
再演を何度も重ねて、ようやく訪れた『ジンガロ』の休演日。
ジョゼフ・マジリエを誘って、ジュールはイタリアン大通りのオペラ・コミック座の建物内にあるカフェに向かった。付近の高級店と比べれば格落ちだが、オペラ座関係者はまず訪れないので、密談をするにはうってつけの場所だ。
久々に再会したふたりの会話ははずんだ。あと数年で40歳になるというジョゼフは、ダンサーとしてはほぼ現役を退いており、振付と教師の仕事に専念しているという。彼に計画を妨害される可能性はなかろうと考えて、ジュールは声をひそめると、自分とグリジの今後の意向を切り出した。ジョゼフはあくまでも生真面目に、相槌を打ちながら話を聞いてくれた。
「あいにく僕はまだ人事権を持っていないけど、お偉いさんたちがきみたちの獲得のために算盤をはじきだしているのは知っているよ」
「オファーがあるとすれば、もうすぐかな」
「間違いない。ちょうど契約更新のシーズンだからね。大いに交渉して、いい条件を狙うといい。──不安材料がひとつだけあるとすれば、リュシアンだな」
リュシアン・プティパ。マルセイユ生まれの新進気鋭の男性ダンサーだ。歳はジュールより5歳下で、つい先日、破格の待遇でオペラ座に入団したという。
若くしてバレエの世界に入ったジュールにとって、歳下の同性ダンサーというライバルの存在は新鮮だった。むしろ、話を聞いているうちに闘志が湧いてきた。自分だってまだ、歳下に地位を譲るような年齢ではない。
「グリジ嬢の立場は昔より優位になっているが、きみはほんの少し厳しくなっている。とはいえ、契約の大きな障壁にはならないはずだ」ジョゼフはそう太鼓判を押してくれた。「何しろ街じゅうのバレエファンが『ジンガロ』ブームに湧いているからな。このベタ褒めの舞台評を読んだかい? この評者、男性ダンサーがめっぽう嫌いって有名なのにさ」
『ラ・プレス』紙の切り抜きを渡される。署名には、テオフィル・ゴーティエという名があった。近頃、よく耳にする作家の名前だ。数年前に、青年聖職者と女吸血鬼のラブ・ロマンス小説がヒットして話題をさらったことはジュールも記憶していた。たしか、男装した女騎士を主人公にした小説もあったような気がする……。
カップの底に泥のように溜まったコーヒーの残りを飲み干してから、記事を読みはじめた。たしかに、公演を褒めてくれている。だが、読んでいるうちに眉間に皺が寄った。
「ペローは風であり、シルフィードであり、男版のタリオーニだ」
「ペローの足首から先と膝の関節は、とてもほっそりしていて、女性的なまろやかな脚を女性的すぎないように見せているのだ」
「男性ダンサーは不自然でグロテスクな生き物である──これまでのオペラ座の男性ダンサーたちを見ても、バレエ団の団員には女性のみがなるべきだと強く思う。しかしペローは、このような偏見を見事に打ち破ったのだ」
──ジュールは顔を上げて、その記事をジョゼフに突き返した。
「気に入らないね」
「どうして」
「なんだか気味が悪い。それに、カルロッタについてほとんど書いてない」
ジョゼフは笑った。「ずいぶん大人になったな、ジュール。あれだけ自分のことだけで必死な若造だったのに」
あくまで茶化すような、嫌味のない笑いだった。だが、コーヒーの苦味が、舌の上でほんの少し強まった気がした。

そのとき、ジュールはまだ知らなかった。
自分がカフェに出かけていくのを見届けるべく、集合住宅の共用廊下の一角でじっと息をひそめている中年女がいたことを。
何が起きたのか、本当のところは分かりようがない。ただ、あとから聞いたグリジの証言を信じるならば、それは彼女にとっても不意打ちだったらしい。呼び鈴の音を聞いて、彼女は、てっきりジュールが忘れ物をして戻ってきたものと思い込んで、何の気なしに錠を開けた。そして呆然と立ちすくんだ。
「ママ……」
数年ぶりの再会だった。彼女は我を忘れて、少女のように母親の胸に飛びついて大はしゃぎした。「どうしたの? ママ、ママったら。いつミラノから来たの?」
だが、母親はそんな娘の腕をゆっくりと振りほどいて、意味深長な微笑みを浮かべた。
「マリーは乳母に預けて、出かける支度をなさい。約束の時間があるのよ」
建物の裏手にはすでに馬車が控えていた。馬の蹄はイタリアン大通りへと向かい、見慣れたカフェやレストランの並びを優雅に通り過ぎていく。行き先も教えてもらえず、戸惑いながら窓の外を見つめていたグリジは、馬車が北に折れて細長いル・ペルティエ通りに入っていくのに気がついて声をあげた。
「オペラ座に行くの?」
「そうよ。あら、ペローさんから何も聞いていないの?」
聞いてない、と言いかけた彼女の脳裏に、ふと、『ジンガロ』初演の晩の記憶がよみがえった。
「ひょっとして、“最高のプレゼント”のこと……?」
一瞬、空気が固まる。いぶかしんだ矢先、彼女の身体は、母親のでっぷりとした腕のなかに包まれていた。
ジュールがカフェを出た頃には、イタリアン大通りにはすでに夜の帳がおりはじめていた。
ジョゼフと別れると、彼はひとり、通りを西に向かって歩きだした。途中で幾度も、今日のオペラ座の観客とおぼしき人びとや馬車とすれ違う。舞台に夢を見て、あるいは舞台に立つダンサーや歌手に夢を見て、パリ市内の屋敷から、ホテルから、あるいはヨーロッパじゅうから、世界最高峰の芸術の殿堂に吸い寄せられていく大きな群れ。
自分はずっと、この場所を欲し続けてきた。あらためてそう確信する。ほかの都市でもほかの劇場でも、踊れる場はいくらでもあるのに、どうして自分はオペラ座でなければだめなのか。結局はこの世界を牛耳る権力や名誉に焦がれているだけなのか。これまで幾度となく自問自答してきた。でも、手に入りさえすれば、もうそんな葛藤もいらない。
もうすぐだ。
間もなく、すべてが我がものになる。
通りのかなたに燃え落ちていく夕陽に目を細めたジュールの心は、これまでの人生のどの瞬間よりも幸福に満たされていた。
(『さかしまのジゼル』第2部 終)
※主要参考文献は<第1回>のページ下部に記載
Back Number
<第1回> イントロダクション──1873年
<第2回> 第1部 I みにくいバレエダンサー──1833年
<第3回> 第1部 II 遠き日の武勇伝
<第4回> 第1部 III リヨンの家出少年
<第5回> 第1部 IV オペラ座の女王
<第6回> 第1部 V 俺はライバルになれない
<第7回> 第2部 I 転落と流浪──1835年
<第8回> 第2部 II 救いのミューズ
<第9回> 第2部 III 新しい契約
<第10回> 第2部 IV “踊るグリジ”
<第11回> 第2部 V 男のシルフィード
<第12回> 第2部 VI 交渉決裂
<第13回> 第2部 VII さかしまのラ・シルフィード








