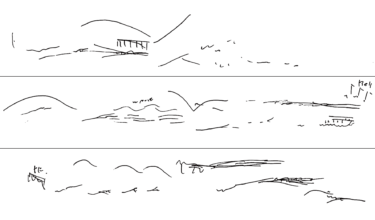さかしまのジゼル <第5回>
第1部 IV オペラ座の女王
かげはら史帆
あのひとの足音だけは、すぐにわかる。
コツ、コツ、コツ。馬の蹄がステップを踏む、軽やかな音だ。
女性ダンサーたちは、みんな彼女のスキルを盗もうと必死だ。彼女がくず入れに捨てていったシューズをこっそり拾い上げ、宝玉の鑑定士のように、顔がくっつくほどサテンの縫い目を眺め回したり、足の裏側に張られた革を指で叩いたり、爪先の詰め物をつまみあげて分解したり。レッスンとなれば、桟敷席の場所取りさながら、彼女の隣のバーを奪いあって、その足さばきや首のかしげ方を舐めるように観察する。
それでも、謎は解けない。どうしてあれほど強く、甲が弓なりにしなるほどの爪先立ちができるのか? どうしてあれほど愛らしく、風にそよぐ薔薇の花びらのようにくるくる回れるのか? どうしてあれほど儚く、肩甲骨から羽根が生えているかのようにふんわり宙を舞えるのか? ワイヤーで背中を吊り上げて体重を支えることもなしに。
業を煮やしたあるダンサーが、喧嘩腰にこう言い放った。
「マリー。あんたかあんたのパパは、きっと悪魔に魂を売ったんでしょうね?」
彼女は笑った。「ええ、それは確かだけど」それから、風の精の白銀のチュチュに似つかわしくない、おそろしく低い声でこう返した。「でも、買ってもらったのは、魂じゃなくて私の努力」
誰もが認めるパリ・オペラ座の女王──マリー・タリオーニ。
でも、彼女の足音が、どうしてこちらに近づいてくるのだろう。まだ人の気配がない、男子ダンサー用の小さな楽屋をめがけて。朝方の夢から醒めきれぬまま、劇場によろよろと出てきて、半ば眠りながらストレッチをしていた自分のところに。
「御機嫌よう、ジュール」
「タリオーニさん……」
「おめでとう」
「意地悪はやめてください」彼女のまなざしが、ネッカチーフでぐるぐる巻きにしたダンタンの首に注がれていることに気がつく。慌てて、座る位置を変えて隠した。
「昨夜、“社長”から聞きましたよ。新作の男性の主役はまたジョゼフなんでしょう」
「そうなんだけど、第1幕に見せ場のパ・ド・ドゥがあるんですって。で、その役をつとめるのはあなた」華奢な手首を折って自分の胸元に当てながら、女王は不敵な笑みを放った。
「つまり、私と踊るの」

「いいね、いいね、ジュール。とてもいい」
ヴァイオリンの伴奏が止んだ瞬間、ヴェストリス先生が手を叩いた。
“社長”のヴェロンと振付師のタリオーニ・パパが同席している手前、大げさに褒めてくれているのだろう。そう思ったが、このふたりも顔を見合わせて満足げにうなずいている。干されたシーツのようにバーに両腕をもたせかけて、汗をぼたぼた落としている間にも、3人はこぞってジュールを讃えた。
「うむ、当たり役だな」
「これはジョゼフを完全に食うだろう」
「きみはこの奴隷のパ・ド・ドゥのほうが向いていると思ったから、主役から外したんだ」
喜んでいいのかわからない。そうやってジョゼフに奪われた役が、これまでいくつあっただろう。
去年の『ラ・シルフィード』初演のときもそうだった。
作品の見どころはシルフィード役の女性ダンサーたちのソロや群舞で、主演級の男性ダンサーは青年ジェームズ役だけ。そんな噂を耳にしたときから、ジュールはその役は自分がもらうと意欲に燃えていた。しかし配役発表の日、緊張で張り詰めたフォワイエ・ド・ラ・ダンスに響き渡ったのは自分の名前ではなかった。タリオーニの横に連れて行かれ、甘いマスクに照れた笑顔を浮かべてお辞儀をするジョゼフ・マジリエの姿を、ジュールは呆然と見つめていた。自分で自分を笑い飛ばすしかなかった。シルフィードに一目惚れされて、森の奥深くに誘われる美青年の役なんか、おまえに似合うわけがないだろう?
しかもジョゼフは、いい役に抜擢されても驕ったところを一切見せなかった。待遇への不満も口にしない。それが劇場から重宝される一因なのかもしれないが、その従順さのおかげで、ジュールの半分ほどのギャラしかもらっていなかった。ちゃんと交渉したほうがいい、と焚き付けたこともあったが、ジョゼフは「充分だよ。暮らしには困らないし」とおっとりと返してくるのだった。
「それにさ、ほとんどのお客さんは、バレエといえば女の子たちを観に来るんだよ」
「客を集めた男のスターだってたくさんいるじゃないか。ヴェストリス先生も、ルイ・デュポールも、シャルル・マズリエも……」
「みんな現役から引退してるか、故人だ」ジョゼフの声は心持ち小さくなった。「ジュール、きみだってわかっているだろう? 時代が変わってしまったんだ」
「でも、ラ・シルフィードのきみのジェームズ役は素晴らしかったよ」
「あれは女の子を輝かせるための役だよ。僕の、僕らのための役じゃない。無難に踊れて、衣装が似合っていて、女の子の踊りをサポートできればそれでいいんだ」
「そんな」
「だって、きみはフォワイエ・ド・ラ・ダンスで声をかけられたことはある?」
思いがけない問いに、ジュールはしばし言葉を失った。
ヴェロン社長が、舞台のすぐ裏にあるフォワイエを開演前や終演後に開放するようになったのは、オペラ座が民営化された2年前からだ。観客と出演者が自由におしゃべりして、バレエにより親しみを持ってもらうため──というのが表向きの理由だった。
しかし実態は違った。フォワイエに入ってくるのは金貸しや商人の成金紳士ばかりだし、彼らに手招きされておしゃべりに興じているのは女性ダンサーだけだった。なかには、客からお小遣いや宝石をこっそり受け取ったり、愛人になったり、積極的に身体を売っている娘もいると噂されていた。社長は、そうした舞台裏の風紀の乱れを黙認していた。それどころか、羽振りが良さそうな客の耳元に、「──いいと思いません? あの娘」と吹き込むことさえもあった。客に贔屓の娘を作らせ、高額の年間予約席を買わせる。それがフォワイエ開放の真の目的だからだ。
「諸君、もはや王侯貴族はいない」
社長が団員たちを前にして垂れるお気に入りの訓示が胸をよぎる。「革命がバレエの歴史を変えた。いまやオペラ座は私企業になり、バレエやオペラは王室の手を離れた。われわれはできる限り自力で経済活動を営み、芸術を金に換えねばならぬのだ」──
ジョゼフはさらにこう畳み掛けた。
「ないだろう。僕だってない。つまり、僕らは売れないんだ。舞台の演目には必要だけど、売上には貢献できない」
「しょうがないじゃないか。男なんだから」
自分の言葉に、はっと口をつぐむ。ジョゼフもまた、その美しい瞳を伏せてこう言った。
「そう、しょうがないんだ。──男だから」
ジュールは、ジョゼフの言葉の全てに納得したわけではなかった。
時代が変わった。それはたしかにそうだ。ジュールがオペラ座にデビューした1830年、王政に抵抗する市民革命がパリで起きた。フランスの王政は、ルイ16世と王妃マリー・アントワネットの処刑によって18世紀末にいったん消滅したが、1815年のナポレオン・ボナパルトの失脚によって復活し、それが長らく市民の不満の種になっていた。1830年の革命は王政そのものを廃するには至らなかったが、新しく王座についたルイ・フィリップは市民に改革を約束し、その一環としてオペラ座を手放すことを決定した。晴れて民営化された劇場の新総裁となったヴェロンは、貴族に代わる新しい客としてブルジョワ市民をターゲットに据えた。彼らを呼び寄せるべく編み出したのが、女性ダンサーを男性客と接触させ、席を買わせる商法だった。
──でも、男性ダンサーだって、芸で魅せて、それで客を呼び寄せることができるのに。
ジュールはそう思っていた。問題は、劇場の上層部が、女性を目立たせるために男性の役を削ったり、女性が主体の作品を作りすぎていることにある。昔のように、男性にスポットライトを当てた作品をもっと制作してくれればいいのに。
──それに、そんな“接触商法”だけが劇場の収益を上げる道じゃないはずだ。
だって、人気ナンバーワンのタリオーニだって、終演後のフォワイエ・ド・ラ・ダンスにはあまり姿を現さない。太客が手を揉みしだいてやって来ても、美しいお辞儀をひとつ披露するだけで、立ち止まってのおしゃべりも、媚を売るようなボディタッチもしない。それでいて、たくさんのファンを獲得して、席をしっかり売っているのだから……。
「マリー。休んだら、もう一度やってみようか」
ヴェストリス先生が声をかける。一発で合格をもらったジュールとは対照的に、タリオーニは苦戦していた。重心を下に置いたエキゾチックなダンスは、長い脚がかえって邪魔になるし、スリムな胴体と骨ばった腕は、ハーレムの女奴隷の肉感的な魅力とはほど遠い。
柳の枝のようにしなやかで、触れたら消えてしまいそうな妖精の役を十八番とするタリオーニは、人間の役を踊るのが大の苦手だった。本人にもその自覚はあるようで、オペラ『悪魔のロベール』の尼僧院長役を、自分のイメージに合わないと言って降りてしまったこともあった。
ところがどういうわけか、今回は、その苦手な役にあえて挑戦する気になったらしい。新作『後宮の反乱、または女性の反乱』──タリオーニが踊るのは、アルハンブラ宮殿のハーレムを舞台に、剣をたずさえて権力と闘う、勇敢な女奴隷ズルマ。彼女自身が望まなければ、父親のフィリポがわざわざこんな作品を振付することはなかっただろう。
「休みなんていりません!」タリオーニはつっけんどんに答えると、矢継ぎ早に指示を飛ばしだした。「先生、このステップのどこが問題か教えて!」「ジュール、もういちどピルエットの支えをやって!」「パパ、ストレッチを手伝って!」
あの子は実家が太いから。
そう言って揶揄されることもある彼女が、どれほどに練習の鬼であるか。「努力を売った」と堂々と言い放つ彼女は、その言葉にたがわず、正真正銘の努力家なのだった。
タリオーニの稽古は強烈だった。脚を開き、うつ伏せで寝て、その骨盤の上に父親がどっかりと腰を下ろして体重をかける。ドゥミ・ポワントで百秒ものあいだ立ち続ける。気絶するまでジャンプを繰り返す。はじめてタリオーニと一緒に組んだとき、ジュールはその壮絶な特訓を目の当たりにして、思わず手で顔を覆った。父親がこれほど付きっきりで練習に付き合ってくれるのは、確かにうらやましい。でも、こんな拷問に耐えられるのは彼女くらいのものだろう。
「じゃ、もういちど最初からふたりで合わせよう」
ヴェストリス先生が手を叩く。ふたたびヴァイオリンがパ・ド・ドゥの旋律を奏ではじめた。女性にしては長身のタリオーニと、男性にしては小柄なジュールとは、ほとんど背丈が変わらない。タリオーニが爪先で立てば、身長はもっと高くなる。踊り慣れた相手とはいえ、互いに手を取り損ねて、ひやりとする場面がちらほらある。「ごめん、俺……」思わずジュールが口走ると、たちまち睨みつけるような強いまなざしに射すくめられる。言い訳したら殺すよ。視線がそう訴えている。
その気丈さに励まされるように、ジュールはタリオーニの高い腰を支えて天高くリフトさせた。

「ね、お腹すいたでしょう? 寄っていかない?」
タリオーニの細長い人さし指の先を追って、ジュールは凍りついた。このイタリアン大通りの北側の並びでいちばん高級な老舗レストランだ。つや光りする鉄製の扉の前で、タイをきっちり締めた黒服のウェイターがいかめしく立っている。
一瞬のうちに、無数の思惑が頭をかけめぐる。誘ったからには、お金を出してくれるのだろうか。向こうが年上だし、噂が確かならギャラだって倍近く多いはず。でも、もし自分が出さなきゃいけないとしたら。そんな持ち合わせはない。それ以前に、こんな高級な店で女性をエスコートできない。
眼を白黒させるジュールの顔をのぞきこんで、タリオーニは口をとがらせた。
「あ、お腹すいてないの? それなら、あっちでいい」
示されたのは、通りを挟んですぐ隣にある、アイスクリームで有名なカフェだった。
結局、奢ってもらったザクロのシャーベットの皿を手に、ジュールはしばらくぼんやりとタリオーニの横顔を見つめていた。この店も、パリっ子なら知らない者はいないくらい有名だ。ただ、高貴な身分の人や有名人であれば、奥の貴賓席に通してもらうか、アイスを氷漬けにして自宅まで運ばせるだろう。それなのに、このオペラ座の大スターは、店の前の素っ気ない籐椅子に座り、長すぎる脚を惜しげもなく高々と組んで、スプーンを口に運んでいる。案外、誰にも気づかれないのは、堂々としているからか。それとも、両耳を覆うように巻き付けた “シルフィード・スタイル”のシニヨンを解き、妖精の涙のような真珠の首飾りを外して、青みがかった白粉や薔薇色の頬紅をすっかり落としているからだろうか……。
「あ、いま、私のこと、ブスだなと思って見てたでしょ」
「え!?」
うっかり、スプーンを取り落としそうになる。からかわれていると気づいたのは、彼女がそんなジュールの様子を見るなり、お腹を抱えて笑いはじめてからだった。こういうおふざけは苦手だ。相手が女性であろうと、男性であろうと。取り繕うとする笑顔が引きつる。
「タリオーニさんはお綺麗です。踊っていると妖精そのもので……」
「あなたは真面目だね」タリオーニはふっと目を細めた。「ありがとう。踊ってるジュールもとってもイケメンだよ」
喉が蛙のようにぐぐ、と音を立てる。これを否定したら、話が堂々巡りだ。舌に転がしたザクロの種がひどく酸っぱい。
晩秋のわりに暖かい夜だった。人混みの絶えない街に、ゆっくりと帳が降りていく。ふと大通りの左方に目を遣れば、晴雨計と大時計を吊るした2つのパサージュが金色の光の点々をまとって輝きはじめていた。宝石店や帽子屋が軒を連ねるあのガラス張りのアーケードの先に、パリ・オペラ座がある。1821年落成。フランスの──いや、ヨーロッパのバレエダンサーなら誰もが憧れる芸術の聖地。
生粋のパリっ子という団員は決して多くない。タリオーニも生まれはストックホルムで、イタリアとスウェーデンの血を引いている。幼少期はパリのバレエ学校に通ったが芽が出ず、父のいるウィーンに行って地道に稽古に励み、成人してからパリに戻って、23歳ではじめてオペラ座の舞台を踏んだ。いまでこそ女王と呼ぶにふさわしい名声を得ているが、決して早熟型のダンサーではない。
「私、子どもの頃から背が高くて、痩せっぽちで、男の子みたいとか色気がないとか、さんざん言われてきた。でもね、それなら、いっそ人間の女じゃない役にならなれるかもと思ったの。『ラ・シルフィード』の主役を踊って、私、やっと自分に出会えた気がした。自分じゃないけど、それは自分なの。わかる?」
コートの下からのぞく爪先が、軽く地面を蹴った。
「ただ、妖精とか幽霊とか、そういう得意な役だけ踊っているわけにはいかないじゃない。ヴェロン社長にもちくちく言われているの。いつも森が舞台ってわけにはいかないよ、って」
「それで今回の作品を?」
「ええ。今度は人間の役にして、しかもとびきり強そうな女の役がほしい、ってパパに頼みこんだの。奴隷のパ・ド・ドゥの相手役にあなたをお願いしたのも、実は私。あなたが主役になりたがっていたのは知っていたけど、パ・ド・ドゥが舞台のいちばんの見せ場だし、一緒に踊りを作ってくれる相手がほしかったから」
シャーベットが溶けるのも忘れて、ジュールはタリオーニの横顔をふたたび見つめていた。もう20代も終わりに近づきつつあるパリ・オペラ座の女王は、いま、新たな挑戦に瞳を燃やしていた。
「だから、お願い。私の力になってちょうだい」
そう言い切れるしたたかさこそが、女王の証だ。彼女の気迫に呑まれるように、ジュールはザクロの種を噛みしめながら強くうなずいていた。
※主要参考文献は<第1回>のページ下部に記載
Back Number
<第1回> イントロダクション──1873年
<第2回> 第1部 I みにくいバレエダンサー──1833年
<第3回> 第1部 II 遠き日の武勇伝
<第4回> 第1部 III リヨンの家出少年