さかしまのジゼル <第21回>
エピローグ──桟敷席にて、1873年10月29日
かげはら史帆
緞帳のように重たいまぶたをようやくこじあけたときには、すでにブランケットが背中から剥ぎ取られていた。寝返りを打って抵抗すると、枕まで奪われて、私の頭はあえなくシーツの上に落下した。まだ鶏も鳴きだして間もない時刻に宅に押し入り、こんな無礼を働く者はメアリー・カサットただひとりだが、あいにく起き抜けは日中よりも視力が効かない。分厚いカーテンの端からこぼれる白光を受けて朧に浮かび上がる、ひっつめ髪の女のシルエットは、舞台袖で本番を待つ踊り子のように見えた。
「何なんだ……」
部屋の端から端をせわしなく往復する足音を聞きながら、目頭を手の甲でおさえていると、ようやく視界が鮮明になってきた。ベッドの足元に、まっぷたつに折れた白のパステルと、空っぽになったローヌ産のワイン瓶が転がっているのが目に入る。昨夜の醜態の記憶と、胃の底に溜まったアルコールの臭いが喉から口元にまでせりあがった。カサットはもう、私の身に起きた悲劇を完全に悟っているに違いない。バレエ・レッスンの画を描きはじめた初夏の頃から比べても、私の目の調子は格段に悪化している。
悪態をつこうとした矢先、目の前に黒い塊が降ってきた。半開きの唇に布の感触がへばりつく。払いのけてみると、それは私が昨夜、晩酌をしながら脱ぎ捨てたジャケットだった。
「早く着替えてください。コートはどこへやったんです?」
「そんなに慌てて、どうしたっていうんだ」
「臭いでわかりません?」
ああ、そんなに私は酒臭いかね。放った皮肉は、頬をなぶる冷気に巻かれて消えた。いつの間にか、彼女が窓を開け放っていたらしい。部屋に滞留していた埃と空気が押し流されて、鼻孔に暗灰色の燻るような臭気が侵入してくる。煙草や暖炉のそれではない。
「オペラ座だ……」
「え?」
「オペラ座では、昔から舞台照明に大量のガス灯を使っているんだ。その臭いがする」ジャケットにくっついたパステルの粉をはたき落とす。「ガス灯はいい。『ジゼル』のウィリたちがまとうチュチュを、この上なく幻想的に照らす。太陽の光よりもずっとエレガントで、蝋燭の火よりもずっと青白い。その神秘的な色合いで、死の世界を作り上げるんだ……」
ジャケットを羽織って、ベッドの端で丸まっていたズボンを引き寄せる。靴と靴下を探そうとベッドからすべりおりたところで、こちらを見つめるカサットの哀しげな瞳に気がついた。
「ご名答ですよ」
私たちが馬車から飛び降りたときには、ル・ペルティエ通りもパサージュ・ド・ロペラも、餌にむらがる山羊のごとく人びとがごったがえしていた。噂を聞きつけてカルチェ・ラタンからはるばる歩いてきたとおぼしき無精髭の貧乏学生。泥のついた芋を麻袋からのぞかせた市場帰りの女使用人。真白な絹ハンカチを口元にあてがって「私の年間予約席はどうなる」とつぶやく紳士。有象無象の野次馬が、イタリアン大通りにはみ出るくらいにひしめいている。カサットはひるむ様子もなく、私のフロックコートの左袖の端っこをつかんで、パサージュの細い通路に押し入っていった。「出直そう」と叫びかけたが、彼女のいかり肩は人びとを強気で押しのけていく。
黒山は生き物のように蠢き、荒波のように寄せては返す。あおりを受けて引き離されそうになった矢先、カサットが袖から指を離し、私の手を強く握りしめた。小ぶりでほっそりしているが、温かくも冷たくもない──自分の手の向こうに、もうひとつの自分の手が現れたような快さ。
「行きますよ」
投げかけられたその声に応えるように、人波をかきわけて進んだ。
オペラ座の開場時刻とて、パサージュがこれほどまでに混み合うことはない。この場所に野次馬が殺到した出来事として、ただひとつ記憶にあるのが、15年前に劇場前で起きたナポレオン三世と皇后の暗殺未遂事件だ。夫妻は奇跡的に無傷だったものの、爆発によって市民12人が死亡し、150人以上が怪我を負う大惨事になった。この事件をナポレオン三世は忌み、別の場所に新しいオペラ座劇場を建てると宣言した。つまり、このル・ペルティエ通りのオペラ座劇場は、すでに取り壊しが決まっている建物ではある。
そう、もう決まっている。
だから、近いうちに失われることはすでに誰もが知っていた。
──だが。
開場の頃には茜色の夕陽の残滓を、終演後は黄金の月明かりを浴びてそびえる芸術の神殿。いつもここに来るたび、美術アカデミーにも通じる威圧感に身がすくんだ。舞台裏にもぐりこんで踊り子たちをスケッチしていると、権力の闇を暴くジャーナリストやスパイになったかのような暗い喜びを覚えることさえあった。
──だが。
鼻を衝いたのは、ガスではなく、真冬の焚火の臭いを何倍にもしたような強烈な煙臭だった。
野次馬どもの頭を押しのけた先に広がるのは、見慣れた劇場の外壁ではなく、どこまでも澄み渡る秋の朝の青空。
呑気に浮かぶ小さな雲の下に、黒焦げた柱が枯れ木のように傾いている。
「なくなった……」
間抜けな声が自分の口から漏れる。
「本当に、なくなったのか……」
カサットの手から、気を失うように力が抜けた。
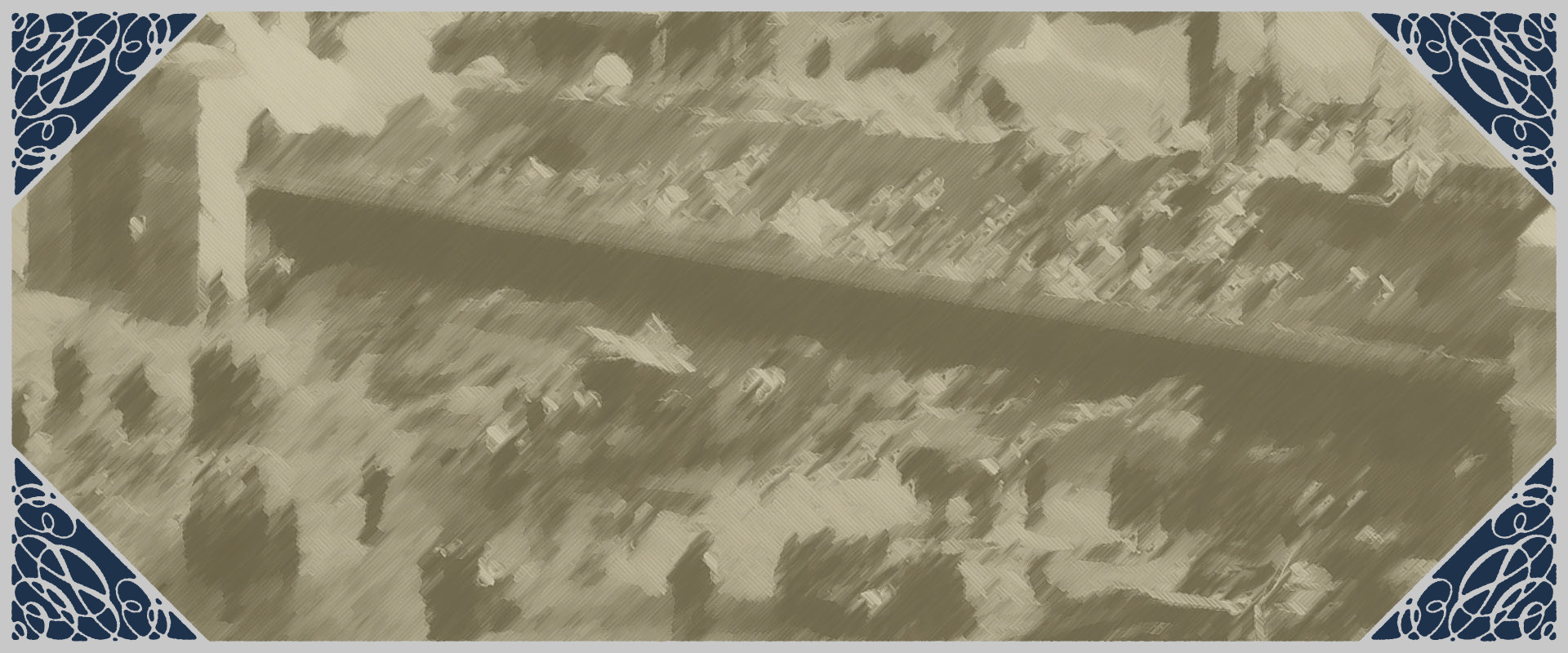
「原因は? ガス灯か? それとも放火か」
「いまはなんとも……」
「死傷者は」
「いまはなんとも……消防士がひとり、消火中にバルコニーから転落したそうですが……」
情報が錯綜しているのか、警察官や顔なじみのオペラ座幹部をつかまえて問い詰めてもまるで埒が明かない。劇場は、楽屋部分の建物を除けば、ほぼ全焼といってよい状況だった。かろうじて形が残っているのは、石造りの基礎の一部とファサードの一階部分だけだ。大きな炎は消し止められていたが、細い煙はまだ敷地内の数箇所から上がっていて、崩れかけたバルコニーやル・ペルティエ通りを挟んだ隣の建物から水をかける消火作業が続いていた。アーチを描いて瓦礫の山の上に落ちる水しぶきが、野次馬たちの灰色の顔を映している。
劇場とは、空洞の建物なのだ。そんなことにあらためて気付かされる。堅牢な壁の内にあるのは、馬蹄の形をしたがらんどうの空間にすぎない。その虚無の世界を極彩色の輝きで満たすのが、音楽であり、物語であり、舞台美術であり、ダンサーたちの舞だ。
しかし、その壁は毀れた。
毎夜、星の爆発のごとくに熱気と光を放ってきたあの奇跡の空間はもう存在しない。炎に侵されて、塵のように宙に散ってしまった。
「衣装も大道具も丸焼けか。大損害だな」
「とはいえ、新劇場の建造が始まっていたのは幸いだ」
「解体の手間が省けた、と喜んでいる関係者もいるんじゃないか?」
黒く濁った水たまりを避けながら、ひそひそ話に興じている若い新聞記者どもにはわかるまい。世界最高の芸術の殿堂として君臨してきたこの劇場が、半世紀の間にいかなる業を背負ってきたか。どれほど多くの有名無名の踊り子たちが、鍛えられた爪先で床を削り、袖幕でこっそりと涙をぬぐい、ガス灯の青白い光に横顔を染め、両腕を客席に向けて広げ、降り注ぐ喝采をかき抱いてきたか。マリー・タリオーニが、ファニー・エルスラーが、カルロッタ・グリジが、
そして、ジュール・ペローが……。
平土間の椅子の残骸とおぼしきビロードの塊を足先でつついていた私は、不穏な想像に胸を衝かれてふと顔を上げた。早足で正面玄関側に回ると、疲れ切った顔でパイプをふかしているおまわりに気づかれぬよう、こっそりとファサードを通り抜けて火事現場の敷地内に入っていった。先とはうってかわって、私に手を引っ張られる格好になったカサットが、なにやら叫びかけている。
「危ないですよ。まだ煙が出てるってのに」
耳に入らないふりをして、ローマの遺跡さながらの青天井の下を進む。このル・ペルティエ通りのオペラ座の造りは、たとえ盲目になっても迷わず歩けるくらいにわかっている。正面玄関から入って、客用廊下をまっすぐに進んで、バックステージに通じるドアを開けて、舞台袖を通り抜けて、細い渡り廊下を抜けて──その先に現れるのは。
フォワイエ・ド・ラ・ダンスだ。
舞台側の壁の一面は、すっかり焼け落ちている。
だが、ほかの三面は、壁こそ真っ黒に煤けているものの、窓や柱の大きな破損はなかった。消火の放流を浴びたバーから大きな水滴が滴り落ち、床に沼のような水たまりを作っている。
その部屋の中央に、佇んでいるひとりの男がいる。
ひしゃげた頭蓋。肉の削げた頬。ぎょろりとした瞳。かつて彫刻家ジャン=ピエール・ダンタンが技術の限りを尽くしてみにくく造形したその人が。指導用のステッキを垂直に床におろし、背筋を伸ばして立っている。若い踊り子たちを導く老教師として。
──あなたは、帰ってきた。
いらぬ感傷が胸にこみあげる。ジュール・ペロー。彼は長年の活動拠点だったロシアを去り、妻子を連れてフランスに帰ってきた。カサットがかき集めた古新聞から得た情報によれば、それは1861年の出来事だった。理由はわからない。彼が戻ってきた頃のオペラ座は、以前にも増して惨憺たる状況だった。女性ダンサーの肉体美がもてはやされる一方、男性ダンサーはこぞって──容姿の美醜にかかわらず総じて「みにくい」と見なされ、本格的に舞台から排除されるようになっていた。かつて『ジゼル』の台本作家、テオフィル・ゴーティエが男性ダンサーは見るに耐えないと喝破したとき、それはまだ過激派の一意見にすぎなかった。しかし20年の歳月を経て、それは市井の観客の共通認識に成り果てていた。あれほどに幻想的なウィリの群れを、あれほど可憐でいじらしいジゼルを観たあとに、いったい誰が、筋張ってごつごつとした、現実の汗の臭いを帯びた男の肉体なぞを好んで観たがるだろう?
なんという皮肉だろうか。男性ダンサーとしての苦悩を抱えてきたジュール・ペローが創造した『ジゼル』が、男性ダンサーの排除をさらに加速させてしまったのだ。だがその荒廃した世界に彼はなぜか舞い戻り、いま、一教師として佇んでいる。加齢によってダンサーの頑健な肉体を失い、しかし加齢によって生来のみにくさをもまた失うことに成功した、ただの薄灰色の髪の老人となり、まばゆい白銀のチュチュをまとう踊り子たちに囲まれながら。
焼け野原の彼方から近づいてくるカサットと私の姿に気づいたのか、彼はゆっくりとこちらに首を傾けた。

「私がオペラ座に火を放った──とでもお疑いですかな?」
老人の口から放たれた言葉に、私とカサットは思わず顔を見合わせた。冗談にしても辛辣に過ぎる。だが、彼の顔色はごく平静だった。まるでこれからイタリアン大通りのカフェに朝食を食べに行くかのように、のんびりと客用廊下の跡地を歩いていたペローは、私たちのさぐるような目つきを見やって忍び笑いをもらした。
「お二方が青い顔でこちらへ向かってくるものですから、よもや逮捕されるかと思いましたよ」
「ゴーティエが存命であれば、そんなロマンティックな台本を書いたやもしれませんね。老アーティストが、かつて自身の活躍した劇場に火を放つ──」私も精一杯の冗談を返した。「しかし、私は作家ではなく、画家ですから」
実際、作家であれば、こうした顛末に乗じて果たしてどんな物語を紡ぐだろう。彼らはきっと、因果という名の尻尾をつかまえようと躍起になるはずだ。おそらくこう考えるだろう。結局のところジュール・ペローは、革命を起こすことができなかったのだ、と。最愛のカルロッタ・グリジを手放して、オペラ座から一度は離れたにもかかわらず、彼は結局のところ、世界のバレエ界を席巻するロマンティック・バレエの呪縛から逃れられなかったのだ。彼のその後の活躍ぶりは、はたから見れば華やかだったが、おそらく彼自身の理想とは遠く隔たっていた。イギリスを経て新天地ロシアに渡り、振付師として大成し、『ジゼル』を自らの手で再演したものの、若き日の『ニンフと蝶々』や『コボルト』のような作品を創ることは、男性ダンサーの地位が保証されているロシアにおいても許されなかった。彼は再び、バレエ界に対してひそかに怨念を抱くようになっていた。それゆえに彼は、復讐のために古巣のパリに戻り、毎日毎夜、ミルタのごとく、呪いのローズマリーの枝をふるいつづけた──。
若く魅惑的な女たちよ、──舞台の上で踊り狂って、パトロンの男どもの餌食となれ。
芸術の殿堂たるオペラ座よ、──女たちを美しく魅せるそのガス灯を暴発させて、炎で包んでしまえ、と。
ジュール・ペローの物語、悪夢の続編。馬鹿げた空想だ。だが、劇場を包む炎が消しとめられても、建物が消え去っても、そこに生きていた人間の業は残る。無念を抱えて散ったさかしまのウィリたちの逆襲は、誰がいつ、果たしてくれるのだろう。それは5年後か、10年後か、はたまた世紀が新しくなり、ここにいる誰もが死に絶えたあとのことだろうか。
コートのポケットに突っ込んだ手に、固いかけらが触れる感触があった。まさぐると、ちびた白いパステルが1本、手のひらに転がり出た。踊り子がまとうチュールの色。そして、老いたるペローの髪の色。小指に満たないほどのその小さなかけらを見つめていると、ペローの視線が同じところに注がれているのに気がついた。
彼は何も言わなかった。ただ、その目は私に何かを促しているように思えた。パステルを見つめ、もういちど彼の顔を見つめる。
──私が?
まばたきだけで問いかけると、彼はうっすら微笑んだ。相槌の代わりのように。
──でも、私は、物語のように画を描く主義ではありませんよ。
ペローは私の目の異常に気づいているのだろうか。それはわからない。彼に構図を見せたあのバレエ・レッスンの画は、油彩で描き進めていた。でも、いつかもっと視力が弱ったときには、繊細なコントロールを必要とする絵筆ではなく、目が効かなくても動きを制御しやすいパステルに頼らざるを得ない日が来るかもしれない。そのときが来てもなお、描き続けるべきなのだろうか。若いバレリーナたちのなめらかな腕の輪郭を。悪戯っぽくすくめた肩を。シューズの紐を結び直すためにかがめた背を。そして、彼女たちの陰でうごめく教師やパトロンたちを。
物体や人物それ自体に、意味はない。
駆ける馬も、踊る娘も、脱ぐ娘も、傾いたチェロケースも、ビジネスマンの紳士も、老教師も、みな同じだ。私が描きたいのは彼らの半生なぞではない。
それが私、エドガー・ドガの信念だ。
──だからこそ、許可してくださる。ということですか?
もういちど、心のなかで問いかける。彼に代わって返事をするかのように、手のなかのパステルが白銀色に輝いた。
私たちの無言の目配せを目撃していたのだろう。カサットが、割り込むようにペローと私との間に入って両手を広げた。
「あ、ずるい。殿方同士でそうやって、女の知らないところで密談するなんて。そういうの、嫌です」ほつれた髪を帽の下で躍らせて、私とペローの顔を交互に睨み返す。「私もアーティストですよ。芸術の相関図にちゃんと入れてください」
「おい、おい」私は彼女に叫びかけた。「私のネタを盗るなと言ったじゃないか」
「ええ、ご安心を。申し上げたでしょう。私は“男性を中心にした”画を描くつもりはございませんから」小さな白い歯を見せてにっと笑う。「アイデアが浮かんできました。私は、オペラ座の画は描きません。舞台の画も、描きません。踊り子の画も、描きません」
「それなら、いったい何を描くんだ……?」
火事現場に似合わぬほどに愉しそうな笑みを浮かべるカサットに、ペローは声を投げかけた。
「楽しみにしておりますよ」
「本当?」彼女は飛び上がって、ステッキの上に乗せた皺だらけのペローの手を握った。「それなら、どうか、画のインスピレーションを私にお授けください。お願いがあるんです」
カサットの耳打ちに、老ペローはわずかに顔色を変えた。
乳白色の月光ゆらめく真夜中の森とは似ても似つかない、どこまでも澄み渡る秋の紺碧の空の下。
私たちは、濡れそぼった瓦礫の山を蹴り、飛翔するジュール・ペローの姿を目撃した。
振付は、私の幼少期の記憶とはだいぶ変わっていた。ロシアで改訂されたという新しいバージョンだろうか。だが、それはまぎれもなく『ジゼル』第2幕のワンシーンであり、彼がジャケットに包んだその腕を胸の前に組み、ほんのわずか背を前傾にして睫毛を伏せているそのさまは、死してウィリと化し、ローズマリーの枝を振りかざすミルタの前に歩み出たジゼルそのものだった。
高くなりはじめた陽の輝きは、弱った目に痛みのように染みる。帽のひさしを眉まで引き下げて、目線を地面に落とすと、身じろぎもせずに立ちつくしているメアリー・カサットの靴のすりきれた踵が目に入った。顔をあげると、そこには、唇をきゅっと結んだ緊張感のある横顔と、一心不乱に燃える瞳があった。桟敷席の最前列で、オペラグラスを片手に、ダンサーの姿を凝視する客のように、彼女は老ジュール・ペローの舞を追っている。私は、その彼女の姿が新たな1枚の画を形作っていくさまを、もうひとりの観客として見つめていた。


「さかしまのジゼル」 終
Back Number
<第1回> イントロダクション──1873年
<第2回> 第1部 I みにくいバレエダンサー──1833年
<第3回> 第1部 II 遠き日の武勇伝
<第4回> 第1部 III リヨンの家出少年
<第5回> 第1部 IV オペラ座の女王
<第6回> 第1部 V 俺はライバルになれない
<第7回> 第2部 I 転落と流浪──1835年
<第8回> 第2部 II 救いのミューズ
<第9回> 第2部 III 新しい契約
<第10回> 第2部 IV “踊るグリジ”
<第11回> 第2部 V 男のシルフィード
<第12回> 第2部 VI 交渉決裂
<第13回> 第2部 VII さかしまのラ・シルフィード
<第14回> 第2部 VIII 最高のプレゼント
<第15回> 第3部 I 仕組まれた契約──1840年
<第16回> 第3部 II 夢見る詩人
<第17回> 第3部 III 狂乱の振り写し
<第18回> 第3部 IV ジゼル、または群舞たち
<第19回> 第3部 V オペラ座の新女王
<第20回> 第3部 VI さかしまの夜明け






