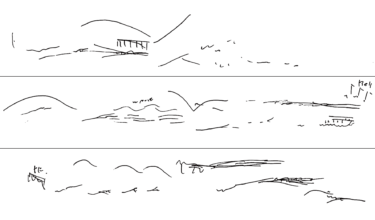Yaffle 『After the chaos』に寄せて
レイキャビク 霧のなかのノスタルジア
text & photo by 八木宏之
ここに記す文章は極めて私的なエッセイであり、一般に考えられる評論とは性格の異なるものだろう。私はYaffleのアルバム『After the chaos』について、音楽評論家としてではなく、作曲家のひとりの友人として、自らの想いや考えを書き残しておきたかったのだ。私が執筆した『After the chaos』のライナーノートもWebで公開されているので、そちらも併せてご一読いただきたい。このアルバムを聴く人が、私の文章を読んで、少しでもYaffleという作曲家の実像に近づくことができたら、それほど嬉しいことはない。
作曲家Yaffleの原点
「ドイツ・グラモフォンから作品集をリリースすることになった」とYaffle に聞かされたとき、私は自分のことのように嬉しかった。と同時に私たちの高校時代に想いを馳せていた。私とYaffleは小学校からの同級生だ。中学校までは共通の友人を介して少し遊んだことがある程度だったが、高校1年生のときに初めてクラスが一緒になった。私は吹奏楽部に入部してオーボエを吹くと心に決めていたのだが、いざ新入生歓迎イベントに行ってみると、ファゴットの恐ろしい先輩に「ファゴットを吹く同級生を連れて来なければ、オーボエを吹かせない」と言われてしまった。困った私は校内をうろうろしながらファゴットを吹きたそうな人を探した。そして中庭でYaffleの姿を見つけた。Yaffleがピアノを弾けること(すなわち楽譜が読めること)を思い出した私は、唐突に「ファゴットを吹いてみない?」と声をかけた。Yaffleはきっと断るだろうと思ったが、ファゴットがどんな楽器かも知らないのに、彼は二つ返事で承諾した。
クラスも部活も一緒になった私たちはすぐに親しくなった。当時からクラシック音楽の魅力を友人たちに広めたいと思っていた私は、Yaffleにも半ば無理矢理、オーケストラ作品のCDを聴かせた。もちろんそこにはドイツ・グラモフォンのCDも多く含まれていた。チャイコフスキーやマーラー、ドビュッシー、ストラヴィンスキーなど、自分がかっこいいと思った曲を片っ端からMDにまとめてYaffleに渡した。Yaffleを誘って、放課後に図書館の視聴覚コーナーでオーケストラのDVDを観たり、NHK交響楽団の定期公演へ行ったりもした。クラシック音楽のファンではなかったYaffleは、最初は困惑している様子だったが、次第に自分の感性にあう作曲家を見つけて、フォーレやラヴェル、エルガーやヴォーン・ウィリアムズなどの作品を進んで聴くようになっていった。
関連記事
Yaffleと考える クラシック現在進行形 Vol.1 Yaffleのクラシック原体験
そんなある日のこと、Yaffleから「オーケストラの曲を書いたから聴いてみて」と話しかけられた。そして購入したばかりの楽譜作成ソフト「Finale」に打ち込まれた、自身初のオーケストラ作品をイヤホンで聴かせてくれた。タイトルも付けられていない未完成の作品だったが、友人がゼロから作り上げたオーケストラ作品に言葉にならない感動を覚えた。あのとき抱いた作曲という行為に対する畏怖の念はいまでも忘れることができない。高校2年生になると、Yaffleは音楽大学の作曲科に進路を定め、国立音楽大学へと進学した。映画をこよなく愛するYaffleは、映画学校で学んで映画監督を目指すことも考えていたが、最終的には作曲家になる道を選んだ。国立音大卒業後のトラックメーカー、プロデューサーとしてのYaffleの国際的な活躍はここで述べるまでもないだろう。
元来レディオヘッドやシガー・ロス、オアシス、ゴールドプレイなど、洋楽の熱心なファンであったYaffleが、クラシック音楽ではなくポップスのフィールドでその才能を発揮していることは実に自然なことだ。また自身の映画への愛を、映画音楽の作曲家としてしっかりとかたちにしていることも、軸のブレないYaffleらしい仕事だと思う。しかし、ポップスや映画音楽で自分のやりたかったことを着実に実現していたYaffleが、クラシック音楽の象徴というべきドイツ・グラモフォンからのオファーを引き受けたことには、正直驚いた。まさかYaffleがドイツ・グラモフォンからアルバムをリリースするとは、全く予想していなかった。完成したジャケットに、Yaffleの後ろ姿とあの黄色いラベルが並んでいるのをこの目で見てからも、やはり夢のなかにいるような感じがする。ドイツ・グラモフォンのカラヤンやバーンスタイン、アバド、ブーレーズのCDを「騙されたと思って聴いてみてよ」と手渡した相手が、15年の時を経て、そのレーベルから自作を発表するのだ。その感慨は言葉では言い尽くせない。高校生の私にいま会いに行けるなら、人生は思っているより美しいものだと伝えたい。
白夜のレイキャビクへ
だからこそ、このアルバムが完成するまでのプロセスを、私は可能な限りYaffleの側で見届けたいと思った。Yaffleが日本での激務から距離を置いて、アイスランドのレイキャビクでアルバムの制作に取り組むと聞き、私もレイキャビク行きの航空券を予約した。Yaffleがレイキャビクへ飛んだ6月末、アイスランドは白夜の真っ只中にあった。大西洋の最果ての街には一日中暗闇が訪れることはなく、昼の空は灰色の厚い雲に覆われていて、陽の光を感じることはほとんどない。ぼんやりとした明るさが、時間の流れを歪なものにしている。Yaffleはあえて孤独に身を置きながら、自信の内面を見つめ、その先にある世界の混沌と分断に思いを巡らせた。自己を理解することを通して、より広い社会の姿を捉えようとする姿勢は、高校時代から変わらない。それは苦しい営みだ。見たくないこと、知りたくないこと、気づきたくないことから逃げずに自身と向き合うには、レイキャビクのような特殊な環境が必要だったのかもしれない。そうした過酷な仕事を経て生み出された『After the chaos』は、Yaffleの私小説的ノスタルジアと2020年代の世界の緊張が同居するアルバムとなった。
新型コロナウイルスとロシアによるウクライナ侵攻がもたらした混沌と分断が、このアルバムの創作の出発点になっていると、Yaffleはレイキャビクではっきりと語った。では『After the chaos』は、21世紀の悲劇をテーマにした標題音楽的アルバムなのだろうか?
《Brown rain》という作品にははっきりとした視覚的イメージがある。この作品はレイキャビクからヨークルスアゥルロゥンへと向かう道中に得たインスピレーションに基づいて作曲された。レイキャビクから車で15分も走れば、そこには北極圏の厳しい自然が広がっている。Yaffleはその風景を車窓からじっと静かに眺めていた。破壊された世界にかろうじて残された道に1台の車が走っている。そこに泥水のような雨が降っている。それがYaffleの心を捉えたイメージだった。《Brown rain》の反復するパッセージは雨だろうか。これはある種の標題音楽と言えるかもしれない。
しかし、この音楽はヨークルスアゥルロゥンへと発つ前から、すでにYaffleの頭のなかにあったものだ。ヨークルスアゥルロゥンへと出かける前日に、Yaffleが《Brown rain》の断片をピアノで弾いていたのを私は覚えている。遠ざかっては近づく座標の音楽は、ミニマル・ミュージックの巨人、フィリップ・グラスへのオマージュでもあり、作品は絶対音楽的な精神を含んでいる。アイスランドの霧や雨に触れたYaffleはそこに標題音楽的な層を重ね、音楽のテクスチャはより繊細で複雑なものとなっていった。
Yaffleの作曲の根底にあるのは、音楽はなにかを表現、描写していなくても価値があるという絶対音楽的な態度である。しかし、標題音楽がテーマとなる事象を音によって表現する過程で生じる「バグ」や「ギャップ」の面白さもYaffleは大切にしている。リヒャルト・シュトラウスが、オーケストラを用いていかに巧みに山を描いたとしても、それは音である以上、視覚情報としての山にはなり得ない。しかし、オーケストラで山を描こうとするからこそ必要となる新しい表現技法もある。そこに標題音楽の本質的な意義があるとYaffleは考えている。それをYaffleは「JPEGをWAVに変換する行為」と呼ぶ。決して変換することのできない両者を、それでも変換しようとするからこそ生じるカオスのなかに標題音楽の面白さがあるというのだ。最初から音響だけを追い求めていたら、カウベルやサンダーマシーンを使ってみようとは思わないかもしれない。だからこそ、ヒントを外の世界に求めつつ、技術的な臨界点を目指すことは重要であるとYaffleは指摘する。シュトラウスの《アルプス交響曲》が標題音楽であると同時に絶対音楽的な交響曲であるように、『After the chaos』に収められた10曲もまた、絶対音楽と標題音楽の二元論には当てはめられないものである。絶対音楽的な美意識のうえに標題音楽的な層を重ねていくのが、Yaffleの作曲スタイルなのだ。
日本とアイスランドのアーティストたちとのコラボレーション
創作のヒントを外に求めるYaffleの創作姿勢は、さまざまなアーティストとのコラボレーションにも表れている。Yaffleはこれまでも、世界各地のアーティストたちとコライトを重ねてきたが、『After the chaos』でも日本とアイスランドのアーティストたちをゲストに迎えて作品を作り上げていった。アイスランドに到着して最初に書かれた《Alone》は、レイキャビクを拠点に活躍するシンガーソングライター、CeaseToneとの共同作業の末に完成した。Greenhouse Studio(このスタジオはアイスランドの音楽シーンの中心的存在であるBedroom Communityの拠点として知られる)で目の当たりにしたふたりの創作プロセスは、まるで魔法を見ているかのようだった。Yaffleが提案する音楽的アイデアに対して、CeaseToneが即興的にテキストを書き、ひとつの歌が生み出されていく。初めて顔を合わせたふたりのアーティストが、互いに反応し合いながら、ひとつの世界を創造していく。Yaffleは全てを自らの手でコントロールしようとするのではなく、他者とのコラボレーションのなかで、作品が想定外の方向へと展開していくことを楽しんでいる。けれども、最終的に完成したものは、紛れもなくYaffleの音楽になっているのだ。

レイキャビクから東京に戻ると、Yaffleはアイスランドで書いた作品の仕上げとレコーディングに取り掛かった。東京でのレコーディングには、日本のクラシック音楽シーンの最前線で活躍する石上真由子(ヴァイオリン)、ビルマン聡平(ヴァイオリン)、安達真理(ヴィオラ)、富岡廉太郎(チェロ)、コハーン・イシュトヴァーン(クラリネット)、中川日出鷹(ファゴット)といった、Yaffleと同世代のアーティストたちが集った。Yaffleはスタジオで彼らと意見交換をしながら、ポップスのワークスとは異なるスタイルを模索していった。あらかじめ決められた編成のために音楽を書くこと。できる限りアコースティックな楽器の響きを活かすこと。ドイツ・グラモフォンからアルバムをリリースするからには、クラシック音楽の伝統的なアプローチへのリスペクトも示したいという思いがYaffleにはあった。

それがもっとも強く表れているのが《Mercy through the clouds》だ。ヴァイオリン・ソロのために書かれたこの作品は、石上の熱く濃密な音を引き立たせるシンプルでストレートな旋律が音楽の核となっている。《Mercy through the clouds》を聴いていると、作曲に取り組み始めたばかりの頃のYaffleの姿が頭に浮かんでくる。ところどころで聴こえてくるファゴットのモチーフが、Yaffleのノスタルジアを強く感じさせるのだ。しかし、それらがノイズによって汚されていき、輪郭が曖昧なものになっていくと、高校生のYaffleははるか彼方へと消え、15年の月日が経ったことを思い出す。美しいものをあえて汚すことによって、その美しさをより際立たせる手法は、Yaffleがポップスや映画音楽の仕事を通して体得したものである。《Mercy through the clouds》には、そうしたYaffleの作曲家としての15年の歩みが凝縮されている。

『After the chaos』は、数十年後に2020年代の音楽シーンを語るうえで欠かすことのできないアルバムとなるだろう。Yaffleの音楽を彩る白夜のような仄暗い明るさは、混沌と分断の時代に生きる私たちの心のなかを映し出しているかのようだ。しかし時代と結びついた作品の奥底に秘められているのは、作曲家の私的なポエジーであり、その音楽は時代を越える普遍性をも帯びている。アルバムを繰り返し聴きながら、アイスランドの霧のなかに隠された作曲家の姿を見つけてみて欲しい。