さかしまのジゼル <第20回>
第3部 VI さかしまの夜明け
かげはら史帆
おまえは、男だから──。
父親の声が、遠雷のように意識のかなたから響く。
威圧的なニュアンスはまったくなかった。むしろその声は、いまにも消え入りそうに弱々しく、どこか卑屈な色を帯びていた。
おまえは、男だから──。
男だから──だから?
だから、駄目だ。パリには行くな。父親が言いたかったのはただそれだけだろう。もしかしたら、彼は彼なりに、舞台にかかわる仕事をする者として、男性ダンサーという職業のままならぬ未来を予見していたのかもしれない。
しかし途切れたままのその言葉は、途切れたままの言霊となって、いつも背中にまとわりついた。知らず知らずのうちに、自分は、言葉の続きを頭のなかでいくつも作り出していた。
男だから、仕方ない。
男だから、そういうものだ。
男だから、許される。……
実際、憧れを胸に飛び込んだパリ・オペラ座はそんな呪いの空気に満ち満ちていた。舞台の上では女性ダンサーばかりが脚光を浴び、男性ダンサーは日陰に甘んじなければならなかったが、管理者としてその世界を支配するのは男性たちだった。ゆえに、男性ダンサーたちは耐えられた。たとえいまが不遇な状態であっても、そこから脱出するルートは残されているからだ。たとえば、事務方になって総裁室に出入りするとか。振付家になってメートル・ド・バレエを目指すとか。あるいは、コネクションを作ってメディアや政界でのセカンドキャリアを歩むとか。
あるいは若くて美しい女性ダンサーを我が物にして、彼女の才能をだしにして出世を目論むとか……。
──父さんの言うとおりだったよ。
ジュールは小さくささやいた。結局、自分は、そういう世界に絡め取られてしまった。待遇を公平にしてほしい。実力で配役を決めてほしい。容姿をからかわないでほしい。正当だと思っていたそれらの要求は、いつしか胸の内でこじれ、苦しんだ分だけ褒美を手に入れたいという欲望に変わっていた。
ここから逃れるすべなど、果たしてあるのだろうか。
枕に頭をうずめたまま、うっすらと目を開ける。まだ一条の光も射さぬ夜明け前の暗がりの果てに、ひとりの男の残像が浮かんだ。乳白色の靄がたちこめる深夜の森、かつての恋人の名前が彫られたその灰色の墓の前でむせび泣くのは……
アルブレヒトだ。
昨日のフォワイエ・ド・ラ・ダンスでのワンシーンがよみがえって、喉が詰まる。なぜ、グリジはアルブレヒトを踊りだしたのか。理由はわかっている。パートナーは映し鏡だ。バレエにおいても、人生においても。──カルロッタ。なぜ、俺を裏切った。俺を馬鹿にしていたんだろう。後ろ盾のない俺を。みにくい俺を。きみはいいよな。いつもきらめく光を浴びて。愛されて。綺麗で。俺なんかいなくたって、いつかは別の男がきみの美貌と才能を見出して、檜舞台に送り出しただろう。そう、俺なんていなくたっていいって。つまり、そう思っていたんだろう?
──自分は裏切るつもりなんてなかった、悪いのはママだって? アルブレヒトも、ジゼルの死を村人たちから責められたらそう言うだろうな。あの山の上にある淀みきった宮殿の世界が悪い、結婚相手を勝手に決める親が悪いって。ちゃんと後悔している、反省している? それなら、懺悔のために俺と結婚しろよ。そうしないと、俺も狂って倒れて死んじゃうぜ? 心臓病なんかなくたって、人間はショックで死ぬんだよ。なあ、愛する人を死なせたくないだろう? 墓の前で泣きたくないだろう? 後悔する一生を送りたくないだろう? だったら、俺の言うことを黙って聞けよ。
「はい……」
グリジの弱々しげな声が、記憶の底から引きずり出される。
メートル・ド・バレエからの手紙を見てしまった、半年前の、恐ろしく寒い冬の日の晩。本当は、口に出した瞬間から後悔していた。こんなプロポーズにするつもりではなかったのに。グリジが青ざめた小さな唇を動かして承諾の言葉を発した瞬間に、後悔は絶望へと変わった。これじゃ、だめなんだ。こんなの、愛の成就でもなんでもない。テーブル・ランプの下で震える一葉の手紙。この紙に書かれたオペラ座との契約はもう取り消せなくても、自分が放った言葉を撤回することはできたはずなのに。
あの日から、実際には何も変わっていなかった。何ひとつ変わらないまま、ここまで来てしまった。
──彼女は、今日、主役として舞台に立つ人なのに。

ふたたび目を醒ましたのは、ちょうど一番鶏が鳴き終えた頃だった。
いつの間に、彼女を抱き寄せていたのだろうか。右腕に、心地の良い重みがある。首を向けると、ウェーブした金褐色の髪と、なめらかな白い二の腕が、ほんのりと輝きを帯びているのが目に入った。小さな唇から規則的な呼吸が漏れている。まだ寝ていると思ったが、ジュールがその頭をそっと撫でると、長い睫毛がハープの弦のように揺れた。
「起きてたの……?」
くっつけるように額を寄せながら、そう聞いてくる。グリジの柔らかな身体を感じて、昨晩、眠る前の記憶がうっすらとジュールの脳裏によみがえった。
交わったのは、いったい何ヶ月ぶりだろう。
行為に及ぶ日はいつも必ず、ナポリでの最初の晩を思い出す──と言ったら、彼女は驚くだろうか。背中のボタンを外そうとするだけで泣いていた彼女を、子どもをあやすように抱きしめて、なんでもないように見せかけながら事に及んだ日の夜のことを。
あのときの彼女はまだ、17歳にもならない少女だった。
「裏切ったのは、きみじゃなくて俺なんだ」
言葉が喉を伝って朝の冷たい空気のなかに放たれたとき、やっと言えた、と思った。記憶がさらに逆流する。ナポリの海沿いのレストランでの禍々しい会食のことを。サン・カルロ劇場のレッスン室ではじめて出会ったときのことを。「まだ、子どもだ」顔を間近で見て最初に抱いた感情がそれであったことを。
それなのに……。
「俺は、自分のキャリアのためにきみの才能を利用しようとした。きみはまだあんなに幼かったのに」
小さな笑い声が、鼻息とともにジュールの頬をくすぐった。
「どうしたの? そんな昔のこと」
──昔のことだけど、それで終わらせちゃいけなかった。もっと早く、言わなきゃいけなかった。
──それに、昔のことだけじゃない。俺はいまもなお、きみを裏切りつづけているんだ。
寝室のカーテンが、朝陽を受けてゆっくりと明度を増していく。さかしまの夜明けだ。夜を支配していた強きウィリたちが、魔力を失って朝の陽光に溶けていく時間。死は生を迎え入れ、生は死を迎え入れる。すべてが反転して、元の世界に還っていく。オーケストラの最後の一音が鳴り、物語が終わるそのときはもう迫っていた。ふたたび幕が開いたとき、そこにはジゼルでも、アルブレヒトでも、ミルタでもない、役から解き放たれたそれぞれのダンサーが佇んでいて、万雷の喝采のなかで深々とお辞儀をするのだ。
「ジュール」
グリジの手が、いつの間にかジュールの頭や顔の端々を撫ぜていた。つぶれた頭蓋に、突き出た頬骨に、ぎょろりとした目の周りに、絶壁のような鼻のラインに、いまにも苦悶のうめき声が吐き出されそうな不格好な唇に。婚約者のほっそりとした指は、この世でいちばん美しいものを愛でるように優しかった。涙がこみあげそうだった。一番鶏が鳴く前に自分ひとりで固めた決意は、果たして正しいのだろうか。
わからない。これもまた人生の大きな過ちのはじまりにすぎないのだろうか。そんな暗い予感が胸にうずく。間違えすぎていて、もう何もわからない。わかるのは、自分がまだ彼女に「最高のプレゼント」を渡せていなくて、自分ができるのはそれだけだということだった。
泣いているの? とは、グリジは聞かなかった。ただ、朗らかな微笑みを浮かべながら、ジュールの鼻先に唇を寄せてこうささやいた。
「愛してる」

本番前の舞台は、いつも、ほんのりとガスの匂いが漂っている。
パリ・オペラ座自慢の最新式のガス灯を使うせいだ。蝋燭の光よりも青みがかっているので、第2幕の深夜の森の場面では劇的な効果を発揮するだろう。舞台係が、群舞の女性ダンサーの背中にワイヤーを取り付けて、強度を確かめていた。ウィリたちを宙に飛ばせるための演出だ。
床に倒して壊してしまったジゼルの墓は、すでに修繕されており、色を塗った完成品が舞台裏に置かれていた。道具係の親方に声をかけて詫びると、ついに犯人が名乗り出てくれたと豪快に笑われた。
「俺の親父も、リヨンで大道具の仕事をしていたんです」
「それじゃ、その親父さんに免じて見逃してあげましょう」
開場はこれからだが、すでに正面玄関に客がごったがえしているという報が入ってきた。主演が期待の新人カルロッタ・グリジであること以上に、振付にジュール・ペローがかかわっているという噂が、パリのバレエ愛好家たちの興味をかき立てたらしい。自分の名前は正式にはクレジットされていないはずなのに、どこからその話が漏れたのだろう。
「きみ、また何か動いてくれたんじゃないか?」
舞台の上からそう叫びかけると、平土間の最前列の中央に陣取った正装のゴーティエが、綺麗にカールした髭を揺らして笑った。
「何のことだか、わかりませんね。それより……」片手でちょいちょいと、ジュールを手招きする。ジュールが眉をひそめて舞台の縁まで寄ると、ゴーティエも立ち上がって、オーケストラ・ピットに落ちるのではないかというくらいに身を乗り出した。「僕は、新しい女神を見つけましたよ」
「何だって?」
「グリジ嬢のいとこのエルネスタですよ。イタリア座で歌っている」
「……本気なのか?」
「ご安心を。もう、グリジ嬢には懸想いたしません。『ジゼル』は僕の手を離れたし、あなたがたおふたりはご結婚する。心よりお幸せをお祈りしますよ」
ナポリの燦々とした太陽を浴びながら、大ぶりの牡蠣にむしゃぶりつくメゾ・ソプラノ歌手の姿が目に浮かぶ。あの一家は大変だぞ。そう言いかけた言葉を、辛うじて呑み込んだ。自分が口出しするような話ではない。
それよりも、憑き物が落ちたように晴れやかな笑みを浮かべている詩人の顔を見るにつけ、別の不安が胸にこみあげた。自分はこれから、彼と同じことをしようとしているに過ぎないのかもしれない。女に出会い、女に見惚れて、さんざん妄想をふくらませて、その妄想で振り回して、ひとつの作品に昇華させて、事が終わればしれっと他人の顔をするような……。
おまえは、男だから──。
父親の声がまた、意識をなぶっていく。まだ自分の心の内に居座りつづける言葉。グリジに決意を告げれば、消えてくれるのだろうか。それとも。
舞台裏に戻ると、第1幕の衣装を着込んだリュシアン・プティパがいた。軽く手足を動かしながら、振りを確認している。ジュールの姿がすぐ近くにあるのに気づくと、黒いビロードの帽子に片手をかけて会釈した。その指が心なしか震えているのは、ジュールに怯えているからではないだろう。彼の肩を軽く叩いて、ジュールは言った。
「パートナーの存在を意識して。そうすれば、おのずといい踊りができるから」
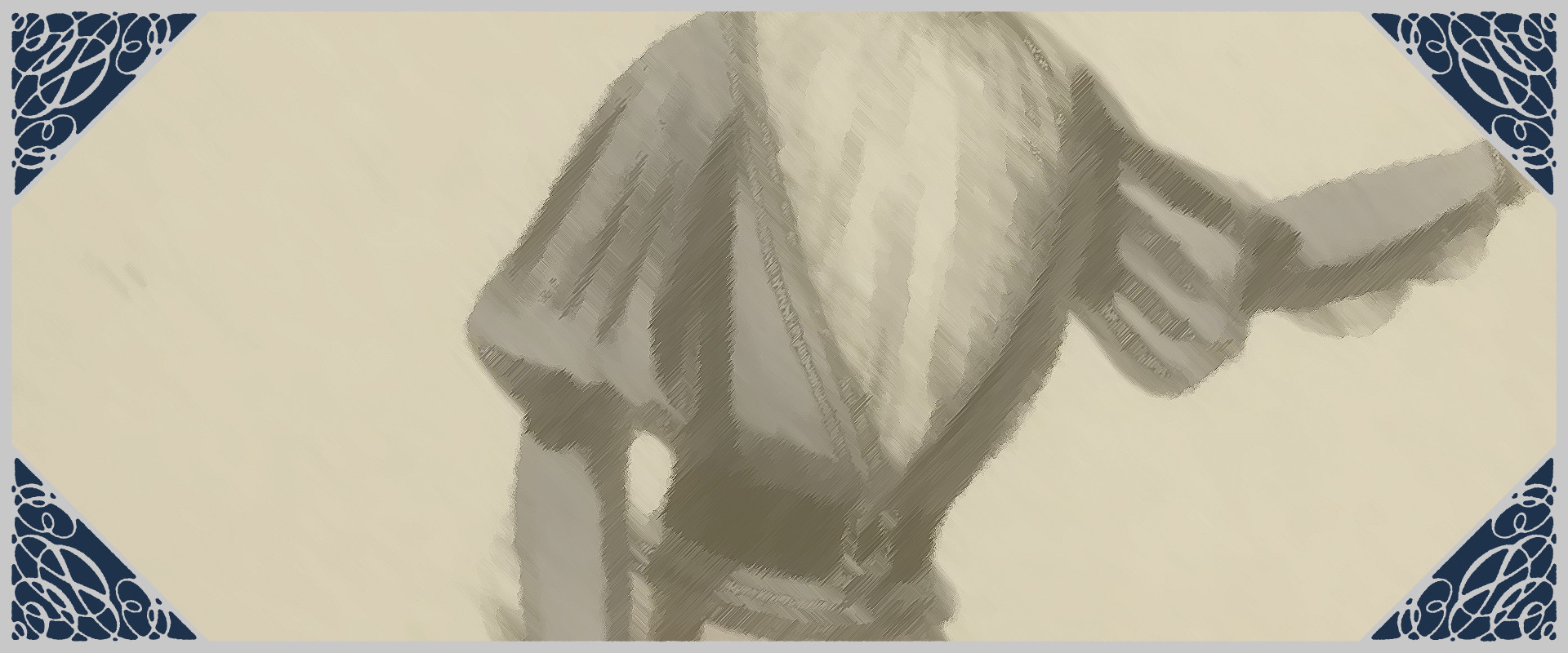
「奥様、呼んできましょうか? 楽屋にいると思いますけど」
フォワイエ・ド・ラ・ダンスの隅で、あまりに所在なげに立ちつくしているように見えたのだろう。通りがかりの舞台係が、気を遣って声をかけてきてくれた。辞退を示すために片手を上げて、まだ結婚していないよ、とジュールが言い添えると、彼は冗談を言われたかのように笑って去っていった。
本番前のスタッフや出演者に気を遣わせるわけにはいかない。バーにもたれ、腕を組んで目を閉じた。こうやって耳を澄ませていれば、彼女の足音はすぐにわかる。コツ、コツ、コツ。馬の蹄がステップを踏む、軽やかな音──。
まぶたを開くと、はたしてひとりの村娘がそこに立っていた。青みがかった素朴なヴェール。明るい茶色のビロードの胴着に、黄色のスカートと小さな白のエプロン。キンポウゲの髪飾りが、額のまわりを愛らしく飾っている。一週間かけて念入りに慣らされたサテンのシューズの先は、詰め物でふくらんでつやつや輝いていた。若い娘の熱い恋心を表すように濃い目にはたかれた紅のチークと、心のか弱さを表すように垂れた眉毛。けれど睫毛にふちどられた青紫の瞳は、本番前の心の高揚を映すように静かに燃えていた。
完璧だ、とジュールはつぶやいた。カルロッタ・グリジの全幕バレエ作品デビューの支度は整った。あと数時間後には、きっと、劇場の壁が揺れるほどの喝采が彼女を包んでいるだろう。
とはいえ、その歓喜の瞬間は無条件で待っていてくれるわけではない。一歩一歩、踏みしめるように近づいて、彼女の両手を取り、自分の手の温かさが伝わるようにゆっくりと握りしめる。
「カルロッタ。この初演の舞台が終わったら……」
瞳を見つめ返す勇気を出すまでには、しばらく時間がかかった。まだ、引き返せる。言わないこともできる。固めた決意をすべて引っくり返して、まったく反対の選択をすることも。絡みついてくる迷いを振りほどくために、ぎゅっと目を閉じた。
「別れよう」
目を開いたときには、もう彼女の顔は頭上のキンポウゲの花に覆われて見えなくなっていた。握った手が、にわかに焼けた石のように熱くなって、それからじわじわと冷えていく。ほんのわずかな後ずさりとともに、スカートのチュールが、葉のざわめきのような音を立てた。はるか遠く、舞台のオーケストラ・ピットから、第2幕の終曲を練習するヴァイオリンの旋律が聞こえる。
さかしまの夜明けだ。夜を支配していた強きウィリたちが、魔力を失って朝の陽光に溶けていく時間。死は生を迎え入れ、生は死を迎え入れる。すべてが反転して、元の世界に還っていく。オーケストラの最後の一音が鳴り、物語が終わるそのときはもう迫っている。
ウィリが首を傾げるときのようにゆっくりと、グリジは顔を上げた。どんな表情もしていなかった。混乱のあまり感情を失っているのか、意外と冷静なのかはわからなかった。ただその唇は、「どうして」と言いかけたまま固まったような半開きだった。
ジュールはふたたび口を開いた。身を裂かれるような痛みに耐えながら。
「きみはもう、償いのために踊ろうとしなくていい」
果たして、彼女にその意味が通じるだろうか。そんな懸念はまったく必要がなかった。みるみるうちに、彼女の睫毛の先に涙の粒がふくれていった。一瞬のうちに決壊して、そのまま床にこぼれ落ちる。わななく唇が、訴えるように動いた。
「だって、私のせいなのに……あなたが舞台に立てないのは、私のせいなのに……」
「きみのせいじゃない。そもそも、償わなきゃいけないのは俺の方なんだ。今朝言ったとおりで」
「やめて」強い拒絶の声が放たれる。「そんなの、いいの。だって、私はあなたを愛している。出会ったときからずっと……」
「だめだ」ジュールは握り返そうとする彼女の手をやんわりと振りほどいた。「俺はなかったことにしてはいけないし、きみもなかったことにしてはいけない。巻き込まれたのも、裏切られたのも、そもそもはきみなんだ。俺がきみを利用した。それがすべての発端だったんだ」
「でも、オペラ座の契約書にサインしたとき私はもう大人だった……」
「だからこそだ。だからこそ、俺たちは認めなきゃいけない。出会ったときのカルロッタ・グリジが、まだ子どもに過ぎなかったことを」自分の声が、棘のように喉を刺す。その痛みに顔をゆがめながら、ジュールはなおも言葉を続けた。「マリーがゆくゆく16歳の娘になったとき、もし彼女を罠にかけようとする者が現れたら、俺たちは大人としてそれを止めなければいけない。同じことを、自分たちに対してもちゃんとしなければだめなんだ。そうじゃないと、俺たちは、」言葉がよじれて、宙に浮く。「ごめん、俺は、これ以外の方法を思いつけない。たとえ間違いだったとしても……」
ジュールの腕をつかむように握ろうとしていた彼女の手が、止まった。
ふたたび、グリジの顔がキンポウゲの花々に覆われて見えなくなった。ジュールもまた目を逸らした。パンドラの箱を開けてしまったのは自分だ。昨晩から今の今まで、ずっと頭の中で想定問答を繰り広げていた。だから、もういちど顔を上げた彼女からこの問いが返ってくることもわかっていた。
「だったら、別の方法を選べばいいじゃない」説得の言葉を探して闇をさまよっていた彼女の瞳が、にわかに天啓を得たかのように明るくなった。「ねえ、私、あなたを赦すから。だから、あなたは私を赦して。結婚式を挙げるとき、神様の前で、ふたりで誓いましょう。それでいいじゃない」
その揺りかえしの波は、想像していた以上に大きかった。このまま、彼女のセリフに押し切られてしまいたい。そんな温かな欲望がジュールの全身を攫いかけた。愛をすべての免罪符にして、祭壇の前で永遠の忠誠を誓えばいいじゃないか。
その最後の誘惑に耐えながら、ジュールはまた口を開いた。
「それはできない」
「なぜ?」
「……俺の夢は、もうオペラ座で踊ることじゃなくなったんだ」
もしも、グリジの大きな瞳に疑いの色が浮かんだら。「嘘はやめて」と強く言われたら。それに逆らえる自信はなかった。己の本心が果たして放った言葉そのままであるのかどうかは、ジュール自身にも未だわからなかった。だが、その一言を告げたあとの彼女の表情は、巨大な竜巻が過ぎ去った後の大地のように静まり返っていた。一バレエダンサーとして、一同僚として、同じ道を歩む仲間の将来を慮る顔つきで、彼女はジュールを見返していた。
──終わった。
ジュールは小さな嘆息を漏らした。これで、終わった。そう確信できるほどに、彼女のまなざしは怜悧だった。ちゃんと、終われる。夜明けの刻は無事に過ぎた。
「……別の劇場で踊りたいの?」
「さしあたりロンドンに行きたいかな。でも、ゆくゆくはロシアでも踊りたい。最近じゃ、実力のあるダンサーや振付家が次々とロシアに渡っている。オペラ座ではできない仕事をやれる余地があるかもしれない」言いながら、微笑をつくった。「マリーは連れて行きたいけど、きみも手放す気はないだろう。それは、よく話し合って決めよう」
行かないで。私も一緒に連れて行って。言おうとしたセリフがどちらも役に立たないことを、グリジはすでに悟っているようだった。たとえパートナーが誰であろうとも、彼女はもう間もなく、パリ・オペラ座の新たな女王として君臨するべき人なのだ。今日の舞台は、いうなれば彼女の戴冠式だ。
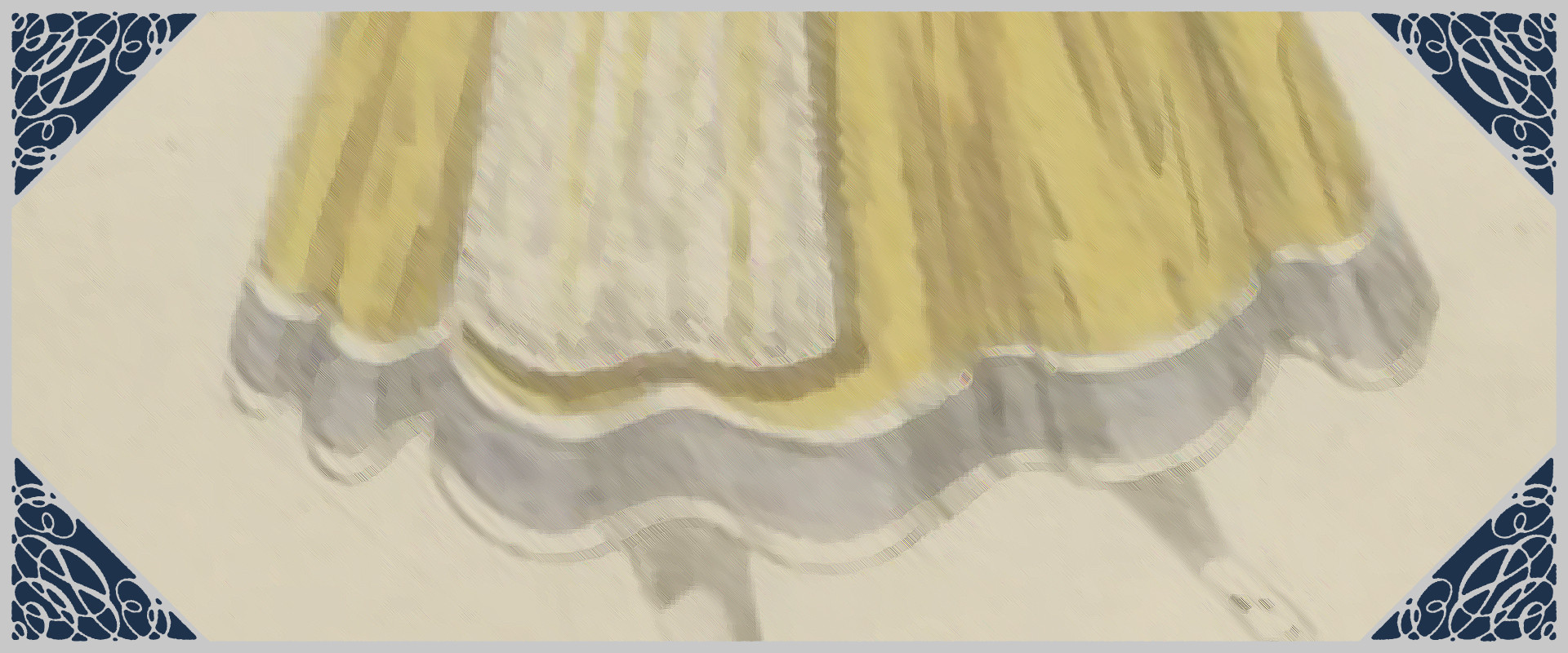
いつの間にか、舞台とフォワイエ・ド・ラ・ダンスをつなぐ渡り廊下の中途にリュシアンが立っていた。おそらく今宵のパートナーを迎えにやって来たのだろう。だが、フォワイエに漂う尋常でない空気を察したのか、ひどく不安げな表情で、グリジとジュールを見つめている。
促すように、ジュールはグリジの背をそっと押した。その肩甲骨には、まだ羽根は生えていない。彼女が村娘から精霊へと変貌を遂げる第2幕は、きっと第1幕以上に観客たちの度肝を抜くだろう。リュシアンに向かって小さくお辞儀をしたあと、彼女は渡り廊下の方へ歩みだした。誇らしげに鳴る爪先の音とともに、そのしなやかな両脚が舞台へ向かうのを、ジュールはフォワイエからひとり見つめていた。
──終わった。
もういちど心の内でつぶやきかけた矢先、グリジは振り返った。鋭くきらめく瞳がまたたいて、唇がこう動いた。
「あなたは、いまのままでは、オペラ座から永久に逃れられない」
それは実際に起きた出来事なのか、それとも自分が見たまぼろしか。ジュールが口を開くより前に、グリジの決然としたまなざしは、もう第1幕の舞台袖へと向かっていた。
「さかしまのジゼル」第3部:完
Back Number
<第1回> イントロダクション──1873年
<第2回> 第1部 I みにくいバレエダンサー──1833年
<第3回> 第1部 II 遠き日の武勇伝
<第4回> 第1部 III リヨンの家出少年
<第5回> 第1部 IV オペラ座の女王
<第6回> 第1部 V 俺はライバルになれない
<第7回> 第2部 I 転落と流浪──1835年
<第8回> 第2部 II 救いのミューズ
<第9回> 第2部 III 新しい契約
<第10回> 第2部 IV “踊るグリジ”
<第11回> 第2部 V 男のシルフィード
<第12回> 第2部 VI 交渉決裂
<第13回> 第2部 VII さかしまのラ・シルフィード
<第14回> 第2部 VIII 最高のプレゼント
<第15回> 第3部 I 仕組まれた契約──1840年
<第16回> 第3部 II 夢見る詩人
<第17回> 第3部 III 狂乱の振り写し
<第18回> 第3部 IV ジゼル、または群舞たち
<第19回> 第3部 V オペラ座の新女王






