さかしまのジゼル <第1回>
イントロダクション──1873年
かげはら史帆
踊り子たちの白銀のチュールを、湾曲した大きな影がさえぎった。
目のかすみか──と思ったのは一瞬だった。右手を庇にして、大広間の中央を足早に過ぎていった影の正体を確認すると、私は再び木炭をたずさえた。公衆の面前でパステルを使う度胸は、まだない。エドガー・ドガの変化は、当面、世間に知られるわけにはいかない。
踊り子の爪先のデッサンで埋めつくされた紙を換えていると、広間の奥で軽やかにリズムを刻んでいたヴィオラの音が途切れた。三脚の画架の向こうで、先ほどの影の主と、ドレスの袖口を絵具で汚した女が、身振り手振りを交えて話し込んでいる。花の髪飾りを直す若いバレリーナたちの間を縫いながら、私は慌てて駆け寄った。
「これは失敬。私の連れが邪魔をいたしまして」彼女の腕を引きながら、詫びを入れる。「彼女はアメリカ人で、バレエを知らないのです」
「いえ、いえ、お気になさらず」
鷹揚にステッキを振る影の主に一礼すると、不服そうな彼女をうながし、画材を散らかした柱の下に戻る。ヴィオラの伴奏はすぐに再開され、固いトウが床に触れる音がフォワイエじゅうに響いた。『コッペリア』のワルツにあわせて、11、2人ほどの踊り子たちが左右に揺れながらステップを踏む。本日のクラス・レッスンはそろそろ佳境だ。
「あの方はジュール・ペロー大先生だぞ。このパリ・オペラ座の有名な指導者だ」
「すみません。けど……」
彼女の過ちも無理はなかった。「視界をさえぎる“男”はすべて追い払ってくれ」──劇場の楽屋口に入る前、彼女にそう頼んだのは他ならぬ私だ。小さくため息をもらす。
「それに、彼は“男”じゃない。“爺さん”だ」
彼女──メアリー・カサットは、私の隣の高椅子に腰掛けながら、憮然とした顔でこう返した。
「爺さんだって、男でしょうよ」
「われわれのような画家にとってはそうだ」先の丸くなった木炭をナイフで削りながら、とっておきの皮肉を彼女の耳にささやいた。「しかし一般的には、婆さんは女じゃない」
カサットと一緒に、床の上に膝をついてスケッチや画材を片していると、木炭の描線の上にうっすらと影が差した。パステルのケースを後ろ手に隠しながら、顔を上げる。踊り子たちは目ざとく、噂話が大好きだ。多くの若い娘がそうであるように。
しかし部屋にはすでに彼女たちの姿はなく、ジュール・ペローだけが、スケッチの束の前で紳士的な微笑みを浮かべていた。「フォワイエ・ド・ラ・ダンス」と呼ばれるこの舞台裏の大広間が、これほど静かなのは珍しい。開演時間が近づくと、ここはパトロンとバレリーナの──つまり“男”と“女”の逢い引きの場所になる。
「これはお見事。あなたの観察力はすばらしい」
ペローは、アラベスクをする若いバレリーナのデッサンにステッキを向けた。
「どの娘を描いたのかすぐわかりますよ。彼女は入団したばかりで、まだ技術が追いついていない。体重がトウに乗り切れていないし、膝も少し曲がっている。けれど、肩から腕のラインはたおやか。1秒でも長く立とうと、必死でこらえているのも微笑ましい。美点と欠点、すべてをありのままに描いておいでだ」
ほっとした。「踊り子」をモチーフにした画は数年前から制作していたが、このパリ・オペラ座の舞台裏や楽屋に出入りしてデッサンを許されるようになったのはつい最近だ。自分の描写は未熟と思っていたが、彼のお墨付きとなれば心強い。意見をもっと聞きたい。そんな欲望に動かされて、今日のスケッチを床に広げた。
「人物はモデルありきですが、構図はまったくのフィクションです。デッサンを配置して、レッスンの風景を創り出すのです」説明しながら、紙の上の踊り子たちを重ねていく。「さまざまな踊り子がいる。ポーズを取りながら伴奏に耳を澄ませる娘。待ち時間に飽きてトウで床を叩いて遊ぶ娘。こらえきれずに背中を掻きむしる娘。そして中央には」つい先ほどスケッチした1枚を置く。「あなたを」
床の上で眠るように傾いていたステッキの先が、ぴくりと動いた。スケッチの上に落ちた影が、心なしか濃さを増した気がした。また、目のかすみか──小さなおびえとともに顔を上げたが、その勘は外れた。
「私は、美術に関しては素人ですが──」
彼の顔からは、すでに先ほどまでの微笑が失せていた。しばらくの沈黙のあと、ためらいがちに唇を開く。「この画に、私は邪魔なのでは。せっかくの愛らしいバレリーナたちが台無しです」
私は笑った。「何をおっしゃいますか。あなたが居てくださってこその作品ですよ」
しかしペロー爺はひるまない。「ご再考を。私は、美術のモデルにはふさわしくありません」
口調は穏やかだが、譲る気配はなかった。いささか焦りながら、私は彼のデッサンを1列に並べた。ステッキをたずさえてバレリーナたちを指導するペロー。座って両の手をゆるやかに組んだペロー。離れた位置からコール・ド・バレエの列の乱れを確認するペロー。しかし、見せれば見せるほど彼の顔は青ざめていく。カサットがとがめるようなまなざしを送っているのに気がついて、私は手を止めた。気味が悪いと思われても当然だ。これでは、諜報員かのぞき魔ではないか。
「ペロー先生。私はあなたに関心があるわけではないのです。ただ、」手を構図の中心部にかざす。「ここにあなたがほしい。あなたの、その、この場にそぐわない、異形と申しましょうか、老いた、存在が」
脂汗が出る。完全に悪手だ。ペロー爺は無言のまま、視線を足元のステッキに落としていた。私の要領を得ない言葉を持て余しているのか。いや──違う。彼の瞳のなかに何かが蠢いている。老人が過去の記憶をさかのぼるとき特有の仄暗い渦。おそらくは、平穏な思い出ばかりではない。岩肌に阻まれながら急流を駆け上がり、しぶきを吸い上げながら滝をのぼり、下流から上流に、そして清水のにじむ山上の土にまで還っていく人生の回想録。
どれほどの時間が経っただろうか。カサットが助け舟を出そうと唇を開きかけたそのとき、彼もまた言葉を放った。
「……ご説明が必要ですかな?」

オペラ座のあるル・ペルティエ通りから、パリの街を真北に向かって10分ほど。モンマルトルの丘陵の一角に現れた瀟洒な白亜の建物を前に、カサットが「オウ・マイ・ゴット」と小さくつぶやいた。
スクワール・ドルレアン──1830年頃から建造され、かつてはショパンやデュマが住んだといわれる、中庭を四角く囲んだイギリス式の集合住宅は、いまでも芸術家の溜まり場として知られている。「初めてか」と聞くと、カサットは噴水のしぶきの残る青々とした芝生を踏みながらこう答えた。「ええ。中に入るのは」
ステッキをたずさえたペローの歩みに従いながら、私とカサットは中庭に通じるアーチ型の通路を抜けて、すぐ左手にある棟に入り、人ひとり通れるほどの狭い階段を上がった。初夏の真っ昼間だというのに妙にひんやりしている。おまけに、人の気配がまるでない。
中二階の扉の内に導かれて、同時に息を呑んだ。小さな舞踏室くらいの大きさのワンルームの左右に、パサージュの店舗さながらショーウィンドウが並び、石膏やブロンズの彫刻作品がぎっしりと飾られている。名前も知らぬ海の生き物。蛇。虎。ギリシアの神々。ブルジョワの紳士淑女の胸像。
見覚えのある作品もいくつかあった。細い髪を長く垂らしてピアノに愛を注ぐフランツ・リスト。理知的な額をつややかに光らせたヴィクトル・ユゴー。洋梨さながらの下ぶくれの頬をしたルイ・フィリップ王──。
「ジャン=ピエール・ダンタンの作品ですね」
「おお、ご存知でしたか」
ペロー爺は穏やかにそう言ったが、私は小さな胸さわぎをおぼえた。ダンタンの名前はむろん知っている。今世紀の前半に一世を風靡した多作な彫刻家だ。だが、すでに故人のはずである。スクワール・ドルレアンにアトリエがまだ残されているという話は聞いたことがない。となると、ここはいったい何だ。作者と同じく、これらの像のモデルの多くもまた故人だろう。もうこの世にいない人びとの顔が、左右から迫りくる。顔、顔、顔。人、人、人。まるでペローのステッキに導かれて、死霊のうろつく墓場に誘い込まれてしまったかのようだ。
彼の足がふっと止まった。
目の高さほどの棚に置かれた、薄茶色に彩色された石膏像の前でじっと佇んでいる。その視線の先を追って、私もまた硬直した。
それは異様な胸像だった。
頭蓋が、左右からぐしゃりと押しつぶしたようにひしゃげている。頬骨が鶏肉の関節のように皮から浮き上がり、そのおかげで、顔の下半分がひどく痩せこけて見える。眼はぎょろりと大きく、半開きになった口は苦悶のうめき声をあげているかのようだ。ゆがんだ頭の上にちょこんと乗った髪束が、間抜けさをかもしだしている。
ただ、顎から下だけはこの上なく美しかった。わずかに傾いだ首の線が、優美なラインを描き、肩までなめらかに落ちている。鍛え抜かれ、削ぎ落とされた肉体の美。そう、まるでパリ・オペラ座の一級舞踊手のような──
「これは、誰です?」
そう尋ねたが、もちろん答えはわかっていた。パーツのひとつひとつが、目の前の老人に重なってゆく。湾曲した額も。出っ張った頬骨も。大きすぎる双眸も。いまは赤のネッカチーフに包まれて見えないが、たぶん、首の美しさも。
ただ加齢によって現れたいくらかの肉づきが、目尻や頬に垂れた皮膚が、地割れのように走る皺が、後頭にみっしりと生えた白髪が、それらをすべて覆い隠しつつあった。老いは万事を曖昧にする。死んで、土に葬られて、骨になれば、みんな似たりよったりであるように。
いまはもう多くの人が気づかないだろう──彼の容貌が「みにくい」ことに。
老人は、私を見つめ、背後のカサットを見つめ、それからひとこと言った。
「かつて“男”だった私です」

「調査してまいりましたよ」
威勢のいい声とともに、枕の横に包みがふたつ投げ出された。ひとつは赤茶けた古雑誌の束。ひとつはまだ温かい特大のバゲットだ。ベッドから身を起こし、朝ぼらけの白光のなかで目をこすると、メアリー・カサットの妙に誇らしげな顔があった。
「セーヌ河岸の新しい古書店で見つけてきたんです。ほら、見て。ジュール・ペローの名前がいっぱい」
古書店さえリニューアルされるのが昨今のパリだ。エトワール凱旋門に通じる新しい街路が続々と開通し、ブローニュの森は整備され、曲がりくねった小路や鼠だらけの貧民街は惜しげもなく破壊される。老朽化したル・ペルティエ通りのオペラ座も、数年のうちに取り壊されるという話だった。この私のアトリエ兼自宅も、いつ、そのような大工事の餌食になるかはわからない。
「調べてくれと言った覚えはないが」下着ひとつで寝ていたことに気がついて、足元に丸まっていたブランケットを引き寄せる。「きみ、私のネタを盗らないでくれよ?」
「ご心配なく。私は“男性を中心にした”画を描くつもりはございません」
「ふん」
言葉の含みは差し置いても、たしかに彼女が手掛けるのは女性や子どもばかりだ。それもひどく痩せぎすだったり、肥っていたり、ぞんざいに髪をとかしていたり、美女や聖女とはほど遠い女たちをカンバスいっぱいに描く。
「ペローお爺さまをモデルにする許可を得たいのでしょう? それならば、まずは彼の心を理解しなくては。その協力をして差し上げようと思ったまでです」
目の前の男が素っ裸も同然だというのに、平然とベッドの脇に腰を下ろして、新聞の包みを解き始めた。
「心を理解する──苦手だ。第一、私のポリシーじゃない」
「仕方ないでしょう。すべての人があなたのようではありませんから」
そういうカサットも根は私と同類だ。彼女がペンシルヴェニア出身の良家の子女らしく、私と昼食を共にするのさえためらい、いつも女友達や姉と連れ立っていたのは最初の頃だけだった。いまとなっては、アトリエはおろか寝室にもずかずか入ってきて、おとなしくしていると思いきや、画架に頭を乗せて平然と昼寝している。私より10歳下だから、もうすぐ30歳になるはずなのに、男の影も結婚の気配もまるでない。
世間から見ればおかしな女だが、私も同じ程度にはおかしな男だ。オペラ座でバレリーナを観ても、娼館で女たちの裸体を見ても、それを紙の上に写し取ることにしか興味が向かない。だから、こぼれる乳房や太腿にごくりと生唾を呑む男弟子とも、娼婦たちに露骨に軽蔑のまなざしを送る潔癖な女弟子とも、私は一緒にいられない。
私がズボンを履いている間にも、カサットはベッドの上でバゲットと雑誌のページを交互につまみながらしゃべり続けた。
「ねえ、カルロッタ・グリジってご存じです?」
「まさか知らないのか。ジゼルの……」
「“ジゼル”って?」
ルーブル美術館で模写するのもいいが、オペラ座にも通ったらどうだ。そう言いかけて、やめる。そういえば私自身も『ジゼル』の上演を久しく観ていない。あれほどの人気演目だったのに。
「バレエ作品の名前だ。グリジが初演で主役のジゼル役を踊った」
「ペローお爺さま、若かりし頃にそのグリジと恋仲だったそうですよ。ふたりの間には女の子がひとり」
「子ができたのに、結婚しなかったということか……」
薄幸の天才バレリーナと振付師。いかにも往年のオペラ座にぴったりのラブ・ロマンスではないか。いまやタバコの煙とトウシューズの傷で薄汚れたオペラ座が、まだ豪奢な輝きをまとっていた時代。別離の痛みさえも、『ジゼル』のラストシーンのように美しく。鬱蒼とした森の奥深く、乳白色の霧たちこめるなか、グリジの墓の前で泣きむせぶ醜男の姿が頭に浮かんだ。
だが、カサットはあっさりとその想像を打ち消した。
「グリジはご存命。引退はしたけれど、たいそうお元気なお婆さまだとか」
「ふん」
とくに失望はない。もとよりロマンスに関心はない。私が求めているのは、ジュール・ペローという“影”だけだ。花弁のようにそよめく白銀のチュールは美しいが、それだけでは絵画にはならない。
光を描くには、光をさえぎる存在が必要なのだ。
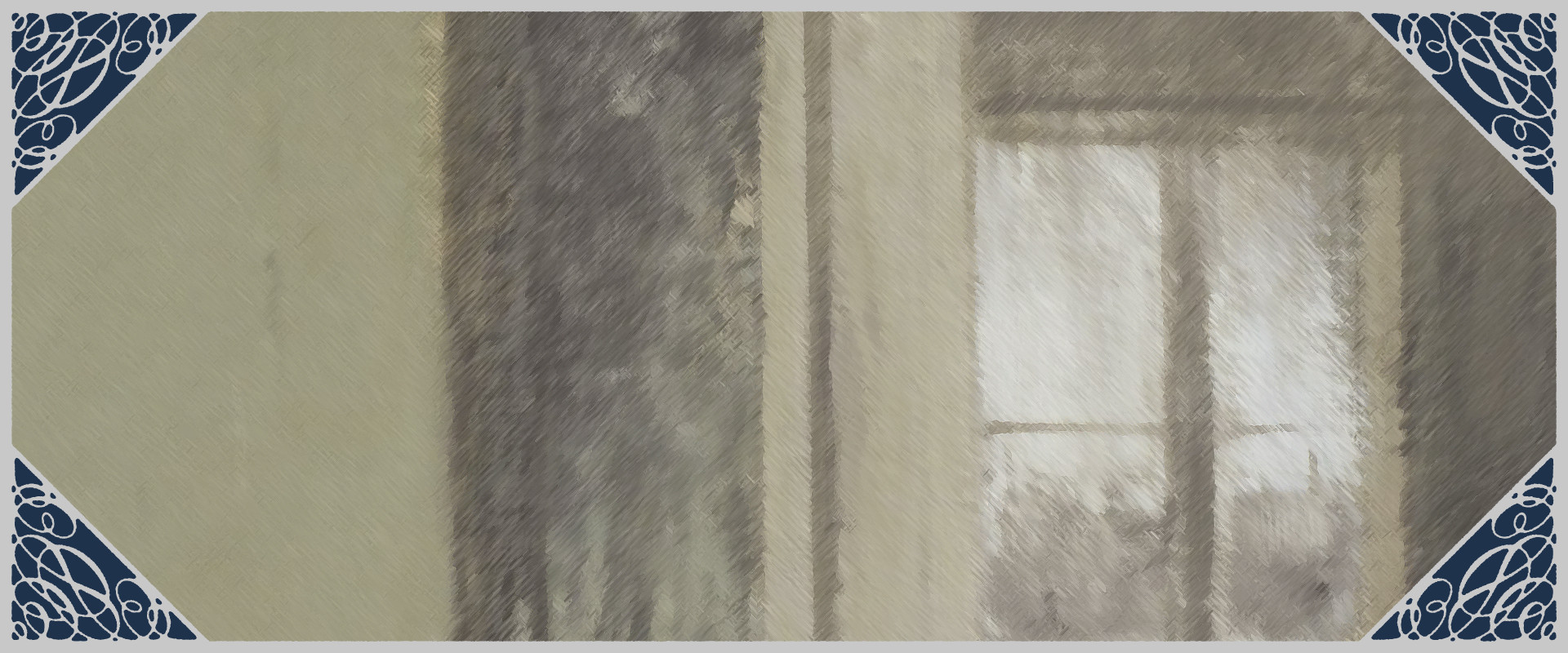
陽が高くなり、アトリエに初夏の強い光が差し込んだ。
カサットは椅子から立ち上がると、窓のカーテンをぴったりと閉めた。部屋がすっかり薄闇に包まれたのを確認してから、彼女は明るい声音でこう言った。「図書館にも、ペローの情報があるかも。行ってきますね」
いったいいつ、カサットは私の目の病に感づいたのだろう。決定的にしまったと思ったのは、ある春の日の真っ昼間、こんな風にカーテンを閉め切って、薄暗がりのアトリエでカンバスの上に白のパステルを夢中で塗り込んでいるのを見られたときだった。ドアの前に無言で佇むカサットに気づいたときには手遅れだった。ドアから微かにこぼれる光が、バッスル・ドレスの後腰の輪郭を点々と浮かび上がらせている。しばし言葉を失っていると、暗がりのなかに、小さな白い歯があらわれた。「ムッシュー・ドガは、お日さまが嫌いですからね」ごく平静なアルトの声。「深夜の森で、百合の花と幽霊の白の違いを見分けるのがお好き」
察しのいい女は損をするぞ。そう皮肉っても、いささかも動じる様子がない。「私だっていつ、外が苦手になるかわかりませんからね」
太陽まぶしい初夏の野原にスケッチに出かけていいんだぞ。ほかの“印象派”の画家どもと一緒に。美術アカデミーから嫌われ、仲間たちともはぐれるのは私ひとりで充分だ。そう言ってやりたかったが、彼女の意志を止める理由はなかった。あのふたりは恋人同士だ──そんな世間の噂はどうでもいい。私たちは恋人どころか、師弟ですらない。ただカンバスに向かう日々を送るなかで、互いの作品に共鳴し、仕事を助け合う間柄になっていただけだ。
物体や人物それ自体に、意味はない。
駆ける馬も、踊る娘も、脱ぐ娘も、傾いたチェロケースも、ビジネスマンの紳士も、老教師も、みな同じだ。私が描きたいのは彼らの半生なぞではない。もし私の画を見て余計な想像をふくらませる輩がいたら、その者はすでに私の作品ではなく別の何かを見てしまっている。
かといって私には、それをとがめるすべはない。
もしこの画がぶじ完成し、ぶじ話題になって、ぶじ売れて、ぶじ100年も200年も生き残ったとしても。この画を展示室の一角で見た未来の輩が、ここに描かれたひとりの老人の人生を夢想し、予想だにしない物語を紡ぎあげたとしても。それはそれで致し方ない。
人は作品を見たいようにしか見ない。私が、彼を見たいようにしか見ないのと同じように。
ジュール・ペローの後頭部を覆う髪に、白をまぶした絵筆を乗せようとした矢先。
何者かの悲嘆にくれた叫び声が聞こえた気がして、私は一瞬だけ手を止めた。
<本作は歴史上の人物、出来事、芸術作品などから着想を得たフィクションです>
『さかしまのジゼル』主要参考文献
*下記のほか、本作の執筆に際しましては、音楽史・バレエ史研究の永井玉藻さん(researchmap/Twitter)にご助言をいただいております。(作者)
・Levinson, André, Marie Taglioni, Hampshire 2014(originally published in 1930)
・Lifer, Serge, Carlotta Grisi, translated from the French, with an Introduction, by Doris Langley Moore, London, 1947(originally published in 1941)
・Guest, Ivor, Jules Perrot Master of the Romantic Ballet, London 1984
・Guest, Ivor, The Romantic Ballet in Paris, Princeton, 2008
・Smith, Marien, Ballet and Opera in the Age of Giselle, Princeton, 2000
・ポール・ヴァレリー『ドガ ダンス デッサン』塚本昌則訳、新潮社、2021年(原著:1936年)
・アイヴァ・ゲスト『パリ・オペラ座バレエ』鈴木晶訳、平凡社、2014年(原著:2006年)
・シリル・ボーモント『ジゼルという名のバレエ』佐藤和哉訳、新書館、1992年(原著:1944年)
・アンリ・ロワレット『ドガ 踊り子の画家』千足伸行監修、遠藤ゆかり訳、創元社、2012年(原著:1988年)
・上田泰史『パリのサロンと音楽家たち 19世紀の社交界への誘い』カワイ出版、2018年
・鹿島茂『失われたパリの復元 バルザックの時代のパリを歩く』新潮社、2017年
・鹿島茂『19世紀パリ時間旅行 失われた街を求めて』練馬区立美術館監修、青幻社、2017年
・家庭画報特別編集『魅惑のドガ エトワール物語』守山実花監修、2010年
・澤田肇/佐藤朋之ほか共編『《悪魔のロベール》とパリ・オペラ座』上智大学出版、2019年
・鈴木晶『バレエ誕生』新書館、2002年
・鈴木晶『オペラ座の迷宮 パリ・オペラ座バレエの350年』新書館、2013年
・富永明子編著『トウシューズのすべて』誠文堂新光社、2021年
・永井玉藻「19世紀後半のパリ・オペラ座におけるバレエ伴奏者――フランス国立文書館及びオペラ座図書館の資料に見る実態――」『音楽学』63巻2号、p.94-109、2018年
・永井玉藻「ミシェル・サン=レオン著『ダンスの練習帳』ー19世紀前半のクラス・レッスン用音楽に見られる特徴」『武蔵野音楽大学 研究紀要』50巻、p.25 -41、2019年
・芳賀直子『バレエ・ヒストリー バレエ誕生からバレエ・リュスまで』世界文化社、2014年
・平林正司『十九世紀 フランス・バレエの台本 パリ・オペラ座』慶應義塾大学出版会、2000年
・町田市立国際版画美術館編『「ラ・カリカチュール 王に挑んだ新聞展』図録』2003年
・横浜美術館編『「ドガ展』公式図録』横浜美術館/読売新聞東京本社/NHK/NHKプロモーション、2010年
・横浜美術館、京都国立近代美術館編『「メアリー・カサット展』公式図録』NHK/NHKプロモーション、2016年
・永井玉藻「【マニアックすぎる】パリ・オペラ座ヒストリー」バレエチャンネル、2021-2022年 https://balletchannel.jp/author/tamamo-nagai
・Gallica https://gallica.bnf.fr
・Museums of the City of Paris https://www.parismuseescollections.paris.fr/
・Musée d’Orsay https://www.musee-orsay.fr/fr








