さかしまのジゼル <第10回>
第2部 IV “踊るグリジ”
かげはら史帆
泣くだろうな──。
そう思ったら、やっぱり泣いていた。
小さな頭に不釣り合いなほど大きな濃黄色のリボンが、力なく耳の下まで垂れ下がっている。幼い顔立ちをさらに幼く見せる朱色の頬紅は、涙でどれほど濡れても流れ落ちず、ひとつしゃくりあげるごとに色を増しててらてらと光っていた。
首から上は子どもじみているのに、胸元が大きく開いたサテン生地の上着も、釣鐘型の重たい白のスカートも、年増の農婦のように野暮ったい。ナポリの伝統的な民族服をベースにしているが、一流のパリの文化人の目には、さぞ田舎じみた衣装に見えるだろう。グリジも審査員たちの冷めた視線に感づいたのか、せっかく得意なタランテラを踊っているのに、ソロの中盤からは完全に身体を固くしていた。ジュールの指導のもと、この半年あまりで徹底して鍛え直したシャープな足さばきも、粋なリズムの取り方も、曲が終わる頃にはすっかり吹っ飛んでしまった。
「今後のご活躍も楽しみにしておりますよ」
去り際にひとこと声をかけてくれたのは、新総裁に就任したばかりのアンリ・デュポンシェルだけだった。ほかの審査員たちは、バーの下に並んだ椅子から一斉に立ち上がり、物ひとつ言わずフォワイエ・ド・ラ・ダンスを出てゆく。1836年8月のパリ・オペラ座の臨時オーディションは不発で終了、というわけだ。
オペラ座を辞めてから2年足らずだというのに、ジュールが知っている顔は審査員席にほとんどなかった。フィリッポ・タリオーニが娘のマリーと一緒に辞めたのは知っていたが、いまやあの“社長”のルイ・ヴェロンさえもいないと知ったときには驚いた。当局からの助成金がこれまでの3分の2に減らされてしまい、ブルジョワ紳士から巻き上げる金で補填するにも限度があると見切りをつけて、あっさりと総裁の座から降りたという。しばらく悠々自適の休暇を送ったあと、満を持して政界入りを狙うのではと噂されていた。
逃げ切り勝ち、というのはいかにも彼らしかった。
元同僚のジョゼフ・マズリエが、審査員の列のいちばん後ろから、何か言いたげにジュールに目線を投げていた。あの列に加わったということは、指導者なり振付家なりの地位に就いたのだろう。そういえば、永遠の美青年のように思われた端麗な面差しにも、ほんの少し、年齢を思わせる肉の厚みが加わった気がする。
ということは、彼のギャラもそれなりに上がったにちがいない。
待遇に文句を言わず、上の連中がいなくなって席が空くのをおとなしく待っているのが正解だったのだろうか。実際、遠目でジュールを眺めるジョゼフの表情は、同情と心配に満ち満ちていた。──ジュール。きみはいったいどうしたんだ? オペラ座を辞めたかと思ったら、今度はそんな子どもみたいな女の子を連れ回して。
──ジョゼフ。きみはいいよな。そうやって綺麗な顔を曇らせていれば済むんだから。
ジョゼフの視線から逃れるように背中を向けて、ジュールは、グリジの肩に片腕を回して抱き寄せた。
「泣いてはだめだ。失敗も経験なんだから」
赤子にそうするように背や肩をさすってやると、ますます泣きじゃくった。
「でも、ロンドンの公演はちゃんとうまくいったのに……」
金色の後れ毛が落ちる小さな耳に、ジュールは低く優しい声でこうささやいた。
「これでわかっただろう。オペラ座の壁の高さが」

ロンドンのキングス劇場は、ナポリから再び戻ってきたジュールを手放しで出迎えてくれた。一緒に連れてきた「新しいパートナー」が、オペラ歌手の名門であるグリジ家の血縁だと知ると、なおのこと喜んだ。
「すぐに出演計画を立てます。宣伝文句は“踊るグリジ”にしましょう」
待遇は桁違いだった。ギャラに加えて、リージェント・ストリートの一等地に新築の小洒落た住まいと上等なワインまで用意してくれる歓待ぶりだ。ジュールは、前回の滞在中に知り合ったロンドンの文化人たちを次々と家に呼び込んで、グリジを紹介した。慣れない英語をたどたどしく使って、顔を真っ赤にしている少女を前に、皆はどっと笑った。
「お嬢さん、怖気づかないで。きみはもう芸術家の仲間入りをしているんだから」
ロンドンの人びとの性質は知っていた。自国の出身者には過剰に手厳しいが、大陸からやってくるアーティストは皆すばらしいと思いこんでいるふしがある。醜男のジュールが『ラ・シルフィード』の青年ジェームズを演じても拍手喝采だったのだから、良く言えば寛大、悪く言えばディテールなぞおよそ気にかけない。
グリジは日々の稽古のおかげでひよこが若鳥になるほどの成長を遂げていたが、まだパ・ド・ドゥやソロを張れるほどではなかった。でも、ロンドンの舞台であればどうにかなるだろうと踏んだ。観客はまだ、1年前のタリオーニとジュールの『ラ・シルフィード』を記憶していて、あの感激をもういちど味わいたいと夢見ている。
ジュールの勘はあたった。女性ダンサーがジュールに手を引かれて舞台に現れただけで、すわタリオーニの再来か、と観客は一斉に湧いた。しかも、はっとするほどの美少女だ。青白い霊気で劇場の温度を下げていくタリオーニの研ぎ澄まされた踊りとはまるで異なる、粗削りながらもはじけるような踊りを、汗をかきかき一生懸命に披露する。ただ元気なばかりではなくて、ピケ・ターンでふっと振り返った瞬間には、いまにもそよ風に巻かれて消えてしまいそうな儚げなほほえみを見せる。なんともアンバランスで、不思議な娘だ。つまづいてもよろけても、応援したくなる。オーケストラが最後の音を鳴らし終えるより前に、劇場は平土間から桟敷まで拍手と笑顔で満たされた。
グリジは半ば呆然と、その轟音のような喝采を全身に浴びて立ち尽くしていた。髪から汗がひとしずく流れ落ち、真珠のイヤリングにシャンデリアの光が映って星のようにまたたいている。よろよろと足を一歩前に踏み出して、お辞儀をする。拍手が湧く。もう一歩踏み出して、お辞儀をする。また拍手が湧く。いまにも倒れそうな有様だったので、ジュールは颯爽と舞台に出ていってその手を取った。またまた拍手が湧く。グリジは酔っ払ったかのようにとろんとした目つきで、ジュールの肩に熱くなった額を乗せた。
喝采はアヘンのようなものだ。
これを浴びれば、もう、彼女はこの爪先の固いサンダルを脱ぐおそれはないだろう。そう確信した。確信したからこそ、ジュールは舞台袖に入るや否や彼女の耳にささやいた。
「さあ、アンコールだ」
「もう踊れないよ……」
ぐったりとした身体をジュールの腕にもたせかける。
「踊らなくていい。歌うんだ」
たちまち正気を取り戻したように、グリジは目をまんまるにした。「え?」
「歌うんだ」
息が苦しそうだ。舞台袖で、背中のコルセットの紐だけ少しゆるめてやって、ふたたび舞台に送り出した。
グリジがいまでもときおり、ドニゼッティの『ランメルモールのルチア』のアリアを口ずさんでいるのは知っていた。昨年、サン・カルロ劇場で初演されて大ヒットしたオペラの1曲だ。ヒロインのルチアが、恋人との密会のときを待ちながら、これから来るかもしれない不運を予感しながら歌う。すでに指揮者とオーケストラには曲目を伝えてあった。短い前奏のあと、グリジは大きく息を吸い込んだ。最初は自分の喉の調子をはかるように控えめに、けれど、だんだんと、桟敷席にまで届くほどのはっきりした声で。
「ブラヴォー、グリジ!」「カルロッタ!」
最高の余興に、観客は沸きに沸いた。花束にとどまらず、金貨や宝石までもが舞台上に投げ込まれる。グリジ家出身のアーティストにふさわしい、ちょっとした余芸のご披露、というわけだ。
このお遊びめいたファン・サービスを見せてこその“踊るグリジ”の誕生だ。もう、カルロッタ・グリジは2度と“本業”の歌手として歌うことはない。彼女はスターへの階段をこれから上がろうとするバレリーナなのだから。
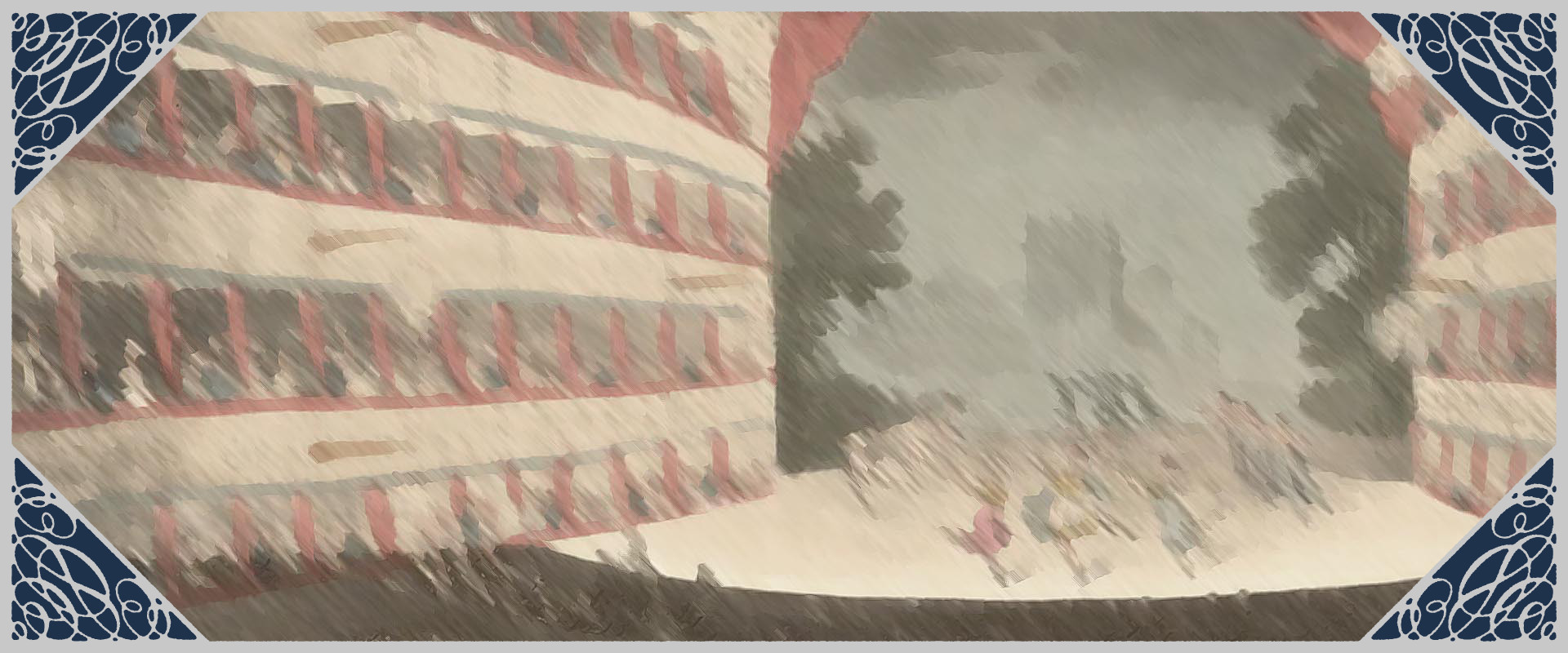
自分がこの一晩で得たものと失ったものに、だんだんと思い至ったのかもしれない。黒塗りの上等な四頭馬車で家に帰り着いてから、湯浴みをして、寝間着に着替えて、寝室のベッドの端に腰を下ろすまでずっと、グリジはぐすぐすと鼻をすすっていた。急激に変わっていく人生。もう戻れない過去。かすかな哀れみをおぼえながらも、ジュールは彼女の隣に腰を下ろして、肩にショールをかけてやった。
今宵はここでもうひとつ、彼女の退路を絶たなければならない。
「新聞記者から質問を受けている。きみの名を、マドモアゼル・グリジではなく、マダム・ペローと書いてもいいかと」
長い沈黙があった。目線を下に落としているので表情はうかがえない。だが、ショールがほんのわずか震えている。
「それはちゃんと訊かないと……ママに」
「そうか」
つとめて穏やかに、相槌を打った。打ちながら、肩から落ちたショールをもういちど巻き直してやった。シルフィードをつかまえるためにヴェールを掛けるジェームズのように。
「でも俺は、きみのママともう約束したつもりだけどな」
するとふいに、グリジはジュールの腕にひしとしがみついた。細い首を白鳥のように伸ばして、キスをする。最初はジュールの出っ張った頬に、次は驚きのあまり半開きになった唇に。自分の身体を懸命にジュールの腕に押しつけて、あげく、ベッドの上に膝立ちになって押し倒そうとさえしてくる。ことばで応えるのを避けるように。
彼女がこんな風になるのは初めてではない。けれど、今夜ばかりは想定外だ。宙に浮いてしまったプロポーズの行方に惑いながら、ジュールはグリジの身体を押しとどめるように抱きしめた。
──ということは、いままでのあれは、ママに命じられてやっていたわけではないのか……。
彼女と最初に関係を持ったのは、ナポリを離れる数日前だった。
部屋に押しかけられた上に、狭いシングルベッドのど真ん中に座って帰りたくないと駄々をこねられたときは、ジュールのほうが困惑した。そしてはたと気がついた。少年期から青年期をバレエの世界にどっぷり浸かって過ごすなかで、自分はいつの間にか、異性への欲望を封印するすべを身につけていたのだ、と。パ・ド・ドゥで相手の腰に腕を回したとき、差し出した手が胸のふくらみに触れてしまったとき、舞台袖で半裸になって早着替えする姿を目撃したとき、そうした日常茶飯事ともいえる小さな危機が積み重なって腹の底で暴発しそうになったときは、男子用の楽屋に駆け込んで、ひとり背を丸めながら必死で言い聞かせた。あの人は同僚だ。あの人は職業ダンサーだ。あの人は下手したら俺より稼いでいる。そうしていると、どういうわけか、荒波が凪に戻るように衝動がおさまっていくのだった。
あのひそかに耐えてきた時間、やり過ごしてきた時間のすべてが、何もかも無駄になりそうで怖かった。それに、ベッドの上から強引に腕を引っ張ったのは彼女の方なのに、いざドレスの背中のボタンに手をかけると、それだけでもう静かに泣きはじめている。吐きそうだった。こんな状況に無邪気に興奮する男がいることが想像できたからだ。フォワイエ・ド・ラ・ダンスのブルジョワ紳士たちの群れ。彼らがためらいもなく踊り子たちに向けるぬらぬらした目つき。いま、自分の前には薄いシュミーズ・ドレスをはだけた少女がベッドに横たわっているのに、その一幅の絵画のように美しい裸像ではなく、我こそ先にとカンバスのなかに侵入する醜男たちの毛むくじゃらな腕や、噛み煙草を奥歯でくちゃくちゃと鳴らす品のない口元だけが蠢いている。
もうやめてしまおうか、とも思った。自分が愚かだった。こんな風に若い女の子をだしに使おうとするなんて。引き返すならいまのうちだ。それでも、「おやすみ」と言って何事もなかったように身を離そうとすると、なぜか彼女は必死でしがみついてくるのだった。やっぱり泣きじゃくったまま。

ロンドンやパリのメディアは、結局、勝手に「マダム・ペロー」の名を新聞や雑誌に書いてしまった。
「一応、訂正を申し入れておくよ」そう言うと、グリジは「ただの間違いなら、それでいいと思う」と、案外、平静な顔をしていた。
その一件をのぞけば、すべてはジュールの計算通りに進んだ。グリジが、ロンドンのキングス劇場の公演で大成功をおさめるのも。一転して、オペラ座のオーディションで大失敗するのも。あえて趣味の悪い衣装を選んで審査員の心象を下げたのも、実は作戦のひとつだった。いちど心を折られなければ、本気になることはできないだろう。
パリ・オペラ座こそが唯一無二の芸術の殿堂。ほかのパリの劇場も、それ以外の都市の劇場もすべて二流以下。だからこそ、オペラ座を目指すことこそがバレエ人生最大の意義であり、ジュール・ペローの助力なしにそれは成し得ない──。
徹底してそう教え込むことこそが、ジュールがグリジに行った最大の「指導」だった。
「仕方がない。まだ、きみにはオペラ座に入れるだけの実力がないんだ」
フォークを皿の上に置いて、しゅんとしているグリジの姿に、ジュールは少年時代の自分を重ねた。「きみは、イケメンとはいいかねる。背も低いし、脚も短い」──師のヴェストリス先生にそんな宣告を受けたときの自分を。
けれどグリジの置かれた状況は、あのときの自分に比べたら雲泥の差だ。この子に足りないのは、実力を蓄えるための時間だけだ。容姿は申し分ないくらい美しく、才能があって、ひとまずは家族にも応援されていて……。
そして、最強のアドバンテージを持っている。“女”だ。
「加えて言うと、俺たちには、作品が足りない」
「作品?」
「そうだ。かのマリー・タリオーニはどうして成功したと思う?」
突然の質問に、グリジは大きな瞳をぐるぐると高い天井に巡らせた。ジュールも一緒になって頭上に目を遣る。壁に油やヤニの染みひとつなく、据えつけのランプの隅々まで曇りひとつなく磨き上げられているのに驚いた。長らく行きつけだったカルチェ・ラタンの安食堂とは大違いだ。
自分ひとりでさえ足を踏み入れたことがなかったイタリアン大通りの高級レストランに、いまや、17歳になったばかりの少女を連れて堂々と入店している。「これも、一流のアーティストになるための人生経験だ」と肩をそびやかしながら。門前でおじけづいて、タリオーニと一緒に隣のカフェのアイスクリームを食べたのはたったの3年前なのに。
なんだか、ひどく離れた場所に来てしまった気がする。
「踊りが上手だから」
「それだけじゃない」
「綺麗だから。爪先立ちができるから……?」
「ぜんぶ一理あるけど、それだけじゃない。いい作品を作ってもらったからだ」給仕がメイン料理の皿を持ってくる。「それが『ラ・シルフィード』というヒット作だ。シルフィードという当たり役を得たからこそ、彼女は誰もが憧れるスターになれた」
わかったようなわからないような曖昧な顔つきで、グリジは神妙に仔牛肉のソテーをつつきだしていた。ジュールはもういちど天井を仰いだ。伝えるのは難しい。懸命にことばをひねり出す。
「きみだって、俺と出会ったときに、タリオーニの真似っ子みたいな稽古着を着ていただろう。つまり、それが彼女の影響力だ」
グリジのフォークがふたたび止まった。彼女の表情に、淡い光が宿ったように見えた。はじめて地球が回る仕組みを見つけ出した学者のように。肉汁が皿にぽたぽた落ちるのにも構わずに、少女は、華奢な腕を長いこと宙に浮かせていた。
「わかった」声が小さくこぼれ出る。「少し……わかったと思う」
ジュールは壁にぶらさがったマホガニー製の時計に目を遣った。そろそろオペラ座の終演の時間だ。今宵の客がなだれこむ前に、ここを立ち去るべきだろう。
「馬車に乗って、次の街へ行こう。俺たちは作品に出会うための旅に出るんだ」
※主要参考文献は<第1回>のページ下部に記載
Back Number
<第1回> イントロダクション──1873年
<第2回> 第1部 I みにくいバレエダンサー──1833年
<第3回> 第1部 II 遠き日の武勇伝
<第4回> 第1部 III リヨンの家出少年
<第5回> 第1部 IV オペラ座の女王
<第6回> 第1部 V 俺はライバルになれない
<第7回> 第2部 I 転落と流浪──1835年
<第8回> 第2部 II 救いのミューズ
<第9回> 第2部 III 新しい契約








