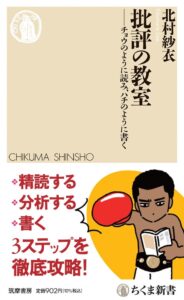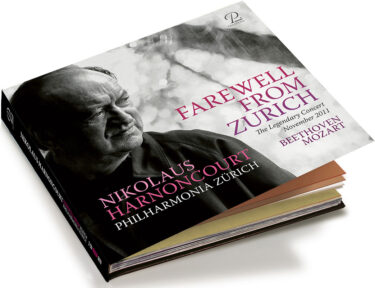<Review>
「ただの聴衆」よ、ペンを執れ――
音楽ファンとして読む『批評の教室 ─チョウのように読み、ハチのように書く』
『批評の教室 ─チョウのように読み、ハチのように書く』
北村紗衣 著
筑摩書房 2021年
text by かげはら史帆
私たちは喝采を言語化する革命的な力を手に入れた、が
たとえば、あるコンサートに行く。終演後の帰り道でSNSを開いて、自分なりの意見をひととおり書く。けれど投稿ボタンを押す前につい考えてしまう。関係者がエゴサーチしてこの投稿を見つけるかな。フォロワーのあの人とあの人はたしかこのアーティストのファンだったな。タイムラインを見ると、みんな今日の公演を褒めまくっている。出演者のキラキラした笑顔のオフショットと、たくさんの「いいね」。ああ、こんな投稿をしたらこのムードに水を差してしまうかな。やっぱりやめちゃおうかな。
──こんな経験は、多くの音楽ファンにとって珍しくないだろう。
聴衆が、拍手やブラボーだけで演奏や作品に対する評価を表現する時代は終わった。ウェブの発達によって、私たちは喝采を言語化して発信できる革命的な力を手に入れた。それは、演奏家や作曲家やスタッフの側にとっても喜ばしい変化であるはずだ。たとえ客席にプロの批評家や記者を呼んでこられなかったとしても、一般のお客さんから、今宵の自分たちのパフォーマンスに関する分析や解釈を聞けるかもしれないのだから。
それにもかかわらず、革命後の世界はいまもって窮屈だ。ひとを病や死に追いやるような悪質なヘイトスピーチが飛び交う一方、コンテンツに対して何か少しでもネガティブな、大胆な、風変わりな言葉を口にすると、アンチやクレーマーとしてファンダムの敵とみなされかねないのが現代のSNSだ。正直に意見を言えないもどかしさを感じながらも、自分自身、好きな作品に対する批判や気に入らない解釈を目にすると、過剰に傷ついたり苛立つ瞬間があるのは否めない。
なぜこんなにも私たちは過敏なのか? それは私たちが何かを評したり、評を通してコミュニケーションする訓練を受けないままこのSNS社会に放り出されてしまったからだろう。作品や演奏について何かを口にしたいという欲望があるのに同調圧力に屈してしまうとすれば、その環境は決して健全とはいえない。
逆にいえば「批評」として適切な手法を守ってさえいれば、私たちはもっと多くを語り、発信してもいいはずなのだ。2021年9月刊行の話題書『批評の教室 ─チョウのように読み、ハチのように書く』(北村紗衣、筑摩書房)が力強く背中を押してくれるように。
「ただの聴衆」から飛躍するための知恵と勇気をくれる本
『批評の教室──チョウのように読み、ハチのように書く』は、シェイクスピア研究者であり批評家である北村紗衣氏による「批評方法の入門書」であり、実際に批評を行うための手ほどきの本である。
登場する例は小説や映画が多いが、使われているテクニックの多くはさまざまなジャンルの批評に応用できる。新演出のオペラやバレエであれば特にうってつけだが、音楽作品一般を扱う際にもある程度は有効だろう。
本文は、「精読する」「分析する」「書く」「コミュニティをつくる」の4章で構成されている。第2章「分析する」においては、「タイムラインを起こす」「人物相関図やネットワーク図を起こす」、第3章「書く」においては「切り口をひとつにする」「自分を縛るタイトルを付ける」などのノウハウが具体的に紹介されている。第4章は、著者と教え子の飯島弘規氏が互いの評の面白い点や改善点を率直に指摘しあい、批評の精度を高めていく。
すぐにでも使えそうな実践的なヒントが詰まった本書だが、批評する際の「心構え」にも多くのページが割かれている。これは、SNS時代ならではの批評の困難を著者が強く意識しているからだろう。「SNSやブログの登場により、作品に批判的なことを言うと作者やファンから攻撃される危険性が増えている」(p.178)──そんな現実に触れつつも、著者は批評を行う際には関係者やファンへの忖度は不要と言い切る。「ここは現実を直視し、みんなから好かれる「良い人」になることは無理だということを認識しましょう」(p.179)
こんな言葉も登場する。「ただの人間の感動には誰も興味はない」(p.165)「大事なのは、「感動した」とか「面白かった」みたいな意味のない言葉をできるだけ減らして、対象とする作品がどういうもので、そういう見所があるのかを明確に伝えることです」(p.165-166)──音楽ファンにとってはドキリとするくだりだ。言ってみればこれまでの聴衆とは、客席に座る「ただの人間」であり、「ただの喝采」を送る人びとだった。しかし真剣に批評行為を始めた瞬間、聴衆はそうした受け身で心地よい匿名の座席を喪失する。「感動した」「面白かった」という言葉にとどめておけば、コンサートの関係者は喜んでシェアやリツイートをするかもしれないが、それらは拍手以上の意味をもたないのだ。
聴衆から芸術家へ、喝采から批評へ
自分は専門的な知識や分析力がないから「感動した」「面白かった」以上のことが言えない、と悩む音楽ファンもいるだろう。けれど、ちょっとした引っかかりさえあればそれを切り口に批評は始められる、と教えてくれるのもまた本書だ(これは私見であるが、楽曲分析ができなくても、プログラミングの特徴や、類似した編成や内容のコンサートとの比較、といったところは比較的言及しやすいだろう)。また、自分自身の鑑賞のクセや無意識のバイアスを見直すヒントを与えてくれるのも本書の面白さである。「身も蓋もない話になりますが、批評をする時は自分の性的な嗜好や趣味をきちんと理解しましょう」(p.44)という警告には、舞台上のアーティストの見目麗しさに心を奪われ、ちっとも演奏に集中できなかった恥ずかしい思い出が胸をよぎる。
著者は、イギリスの劇作家であり批評家オスカー・ワイルドの言を引き、批評というもの自体が芸術であるという考えを示している。「あなたが書こうとしているのは、クリエイティヴな能力が最大限に活用されるひとつの芸術作品です」(p.134)──聴衆から芸術家へ。受け手からコミュニケーションの主体へ。批評とは、そうした役割転換の試みでもあるのだ。
あらゆる芸術表現の中でも、音楽はとりわけ神聖視されがちなジャンルだ。音楽は言語よりも上位であり、言葉を操る批評家は音楽家の天敵である、と信じる人はいまもって多い。しかし、あなたが鑑賞しているのが芸術ならば、それに対するあなたのリアクションもまた芸術になりうるのだ。喝采では表現しきれない微妙な引っかかりを覚えたならば、「ただの聴衆」ではいられない衝動に駆られたならば、その理由を自分なりに分析し、言葉で適切に表現し、それを誰かに伝えたい。そう願う方に手にとってほしい1冊だ。