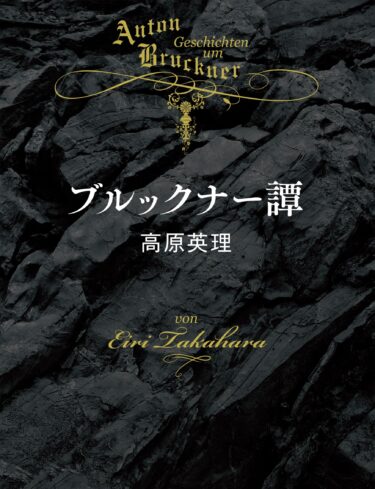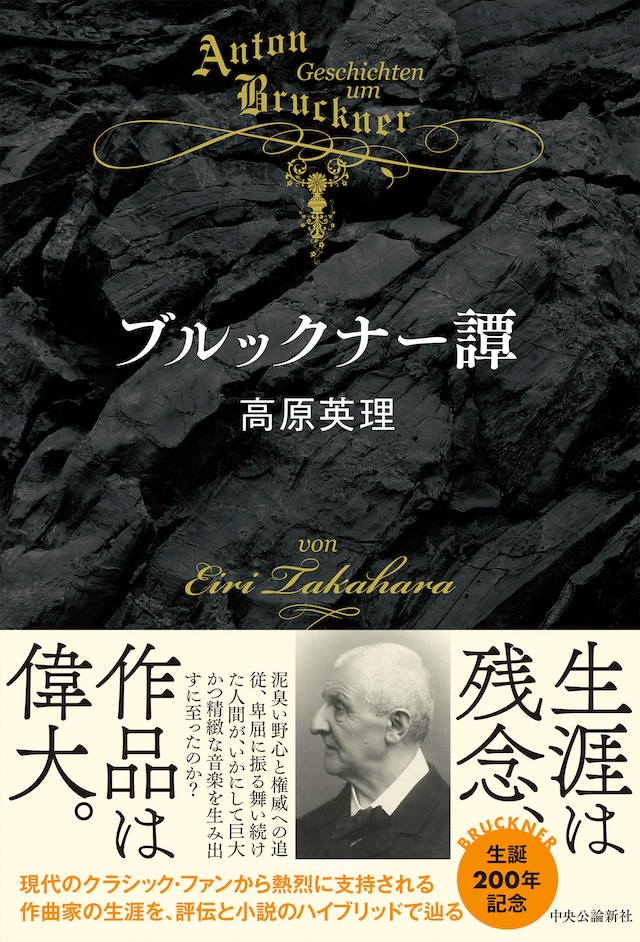<Review>
文学はブルックナーを救済するか
──高原英理『ブルックナー譚』評
text by かげはら史帆
『ブルックナー譚』
高原英理 著
中央公論新社 2024年
ブルックナーは「残念」なんかじゃない?
アントン・ブルックナーは、クラシック音楽界においてしばしば物議を醸す作曲家だ。──古今東西のクラシック音楽のなかでも最重量級といえる長大な交響曲群。改訂版や原典版をめぐる複雑きわまりない論争。女性の聴衆が圧倒的に少なく、コンサート会場で男子トイレだけに長蛇の列ができるという珍現象。巨匠の死体に執着したり、老いてなお10代の少女に次々と求婚したりという人生のエピソード。だが、これらを面白おかしく話のネタにすれば作曲家を愚弄していると批判され、触れずにいればそれはそれで盲目的な信者と揶揄される。それが、ブルックナーという作曲家を取り巻く今日の状況である。

本書『ブルックナー譚』の帯のキャッチコピー「生涯は残念、作品は偉大。」もまた、SNS上のクラシック・ファンを少なからずざわつかせた。生誕200年の記念年にもかかわらず、ブルックナーがまた例のごとく「残念」だの「キモオタ」だの「弱者男性」だのという下衆なミームの餌食となってしまうのだろうか。ブルックナーを愛聴する人びとがそんな不安を抱いたのも無理はないだろう。しかしこうした批判に対して、作者の高原英理氏は次のように反論している。
普通、作曲家の伝記は偉大さを伝えることが主なので「生涯は残念」などと書かない
だから一般音楽書に慣れた人の中には違和感を持つ人があるかも
しかし本書の視線は文学のそれだ
小説家はこういう所に注目する
https://twitter.com/ellitic/status/1769942713464766573
さて、この物議に自ら加わった方々、あるいは「うわ、またブルックナー界隈が揉めてる」と遠巻きに見ていた方々は、ブルックナーの交響曲に劣らぬボリュームのこの大著を実際に手に取っただろうか。もしもまだであれば、ぜひ書店で本書の重みを体感してほしい。 実際に本に触れてみたほうが、上の高原氏の言葉の意図をよりストレートに理解できるはずだからである。
“評伝と小説のハイブリッド”がもたらす意味
本書『ブルックナー譚』は、ブルックナーの評伝とブルックナーを主人公にした小説を交互に挟んだ作品である。第一章「出生から教師時代まで」から第五章「晩年」まで、ほぼ時系列で進行するが、評伝の間に全二十場の短い小説が挿入されている。
評伝セクションは、ブルックナーの生涯や作品の成立プロセスを平易な文体で詳説している。本評の筆者はブルックナーの専門家ではないため、使用されている資料が必要十分かどうかを論じることはできないが、少なくとも日本国内でこれまで刊行されたブルックナーの研究書を総括した内容であることは間違いないだろう。(なお高原氏は「序」にて「そもそも私は一小説家でしかなく、音楽の専門家でもなく、ドイツ語が読めるわけでもない。」(P8)と誠実に述べているが、氏が史料や文献の取り扱いに長けた論客であることは、ゴシック文化論として名高い著作『ゴシックハート』(立東舎/ちくま文庫)からも明らかである。)
一方の小説セクションは、ブルックナーの人生のエピソードを空想のセリフや心理描写でふくらませた創作であり、高原氏の小説家ならではのイマジネーションが発揮されている。たとえば第二章、ブルックナーが音楽理論家のゼーモン・ゼヒターに師事するくだり。評伝セクションにおいて「師ゼヒターは「まずは理論、その上で自由な創作」を旨としており、ブルックナーには一切自己流の音楽展開を許さず、修業中の作曲を禁じた。」(P84)と解説されている厳しい師弟関係は、続く小説中においては、より人間的で情愛に満ちた関係として描かれている。
「わたしも君に魔法を伝えることができて嬉しいよ。だがね、世に通じる魔法となるとどうか。わたしたちはともに、時代を間違えてきたのかもしれないね」
そう言い、いや、われらに似合う時代なぞあるのか、とも思いながら、ゼヒターは、左手の窓の向こう、夕映えにシルエットとなった教会の尖塔の先の方を見やった。
テーブルを隔てて向かいあうブルックナーもまた、師の視線の先を追い、しばらく無言の時間が続いた。」(P96)
評伝と小説が交互に現れることによって、読者は本書の主人公を、年譜の上で1年ずつきっちり老いていく遠い過去の人ではなく、テーブルを隔てたすぐそこで窓の向こうを眺めている生身の一人間として捉えることができる。その姿はあくまでも小説家・高原英理のマジックが生み出した幻像であり、アントン・ブルックナーの実像ではない。だが語弊を恐れずに言えば、わたしたちが日ごろ受容しているブルックナーの音楽もまた、指揮者や演奏家のマジックを介した幻像ではなかろうか。それに準じれば、本書の小説セクションは評伝に付随するオマケではなく、むしろ本書の核であり本質であるといっても過言ではない。
文学だから受け止めうるブルックナーの「わからなさ」
こうした幻像の一部として、アントン・ブルックナーの「残念」な一面が現れる。その残念さは、主として彼の他者や事物に対する「とらわれ」という形で顕在化する。年少の少女へのとらわれ、死体へのとらわれ、権力者へのとらわれ、ホモソーシャルへのとらわれ、数字をかぞえることへのとらわれ──そして、長大で荘厳な音楽へのとらわれ。小説セクションにおいて、高原氏はこうしたブルックナーの異様なとらわれの数々に迫り、残酷なほどあらわにそれを描き出す。しかし恐ろしいことに、主人公であるブルックナー自身は、そのとらわれの理由や由縁にまるで気づかない。つまりブルックナーは、己のはちきれんばかりの欲望にもがき苦しみながらも、その正体が何なのかまるでわからないし、わかったところでどうにもできないのである。
「十一、十二、と数えて次の石が見いだせず、ふと数かぞえが途絶えると、しかし、一気に揺り戻しが来た。
そんなことは望まない。自分はただ消えてゆくつもりはない。己の中には是非人々に聴かせたい響きがあること、そしてその素晴らしい響きを創り出した者として十分の尊敬を得ること、どこへ行ってもあの偉大な音楽家だと頭を下げられること、その威光のもとに、容姿の優れた若い娘を妻とし、充実の中でさらなる天界の音楽を組み上げてゆくこと、それらを決して手放さない手放せない希望が期待が執着が、燃えあがるように身中に湧いて、ブルックナーはひととき、息をもつくことができなかった。
身は顫える。視界は揺らぐ。おーあ、おーふあ、と言葉にならない呻きが洩れる。」(P154-155)
夢はある。それは人生の谷底にあってなお燃えあがっている。素晴らしい音楽を書きたいという「偉大」な夢も、権力を手に入れて美少女を娶りたいという「残念」な夢も、ブルックナーの混沌とした脳内においては同等の欲望である。だがどうして自分がそんな夢を持つのか、それにとらわれるのか、彼にはついぞわからない。この「わからなさ」は、もしくは「わからなさ」の肯定は、小説だからこそ、あるいは文学だからこそ成し得るものではないだろうか。わたしたちは音楽や音楽家に対して──少なくともブルックナーのような音楽や音楽家に対して──どうしても「わかろうとする」意識をはたからせてしまう。だからこそブルックナーをめぐる論争は永遠に終わらず、彼がわかりえなかったものをわかろうとする努力は今日まで絶えない。だが高原氏は、小説家にしか持ち得ない両腕で、ブルックナーのわからなさを全力で受け止める。高原氏は「序」においてブルックナーの心性を「どこまでも完全には手にしえないものへの強烈なとらわれ」(P5)と表現している。そのとらわれはどこまでいっても決して解消されないし、彼が谷底から救済されることは決してない。ただ文学は、谷底に落ちてあえぎ苦しむひとりの音楽家に視線を向け、その「残念」さと「偉大」さを等価な愛情でくるむことが可能なのだ。
「どこまでも完全には手にしえないもの」を夢見て
さて、ブルックナーの音楽を語る上で外せないのは本人の改訂を含むいくつもの「版」の存在であるが、面白いことに本書『ブルックナー譚』も、実はとある小説の「改訂版」なのである。
本書の小説セクションの一部は、高原氏の2016年の小説『不機嫌な姫とブルックナー団』(講談社/講談社文庫)にその原型が登場している。この小説は、「ブルックナー団」と自称するブルックナーオタクの男性たちと、図書館の非正規職員として働くブルックナー好きの女性・代々木ゆたきによる──2024年風にいうと「推し活」の物語である。ブルオタ男子のひとりである武田一真(通称タケ)は、作中で『ブルックナー伝(未完)』を書いてゆたきに読ませるが、『ブルックナー譚』の第八場、九場ほかいくつかの小説セクションは、タケが執筆したテキストを改稿したものである。

つまり本書『ブルックナー譚』は、タケ作の『ブルックナー伝(未完)』の「高原版」であるといえる。高原は自身をタケと同じ「単なるブルックナー・ファン、「ブルックナー団」の一人でしかない者」(P8)と述べているが、さらに突き詰めて考えれば、ブルックナー自身もまたブルックナー団の一人でしかないのではなかろうか。なぜならアントン・ブルックナーという壮大なる未完のプロジェクトを始めたのは他ならぬブルックナー自身であり、彼の「どこまでも完全には手にしえないものへの強烈なとらわれ」こそが、ブルックナーという作曲家を生誕200年の記念年まで生き残らせ、ひとりの小説家に『ブルックナー譚』を書かせたからである。