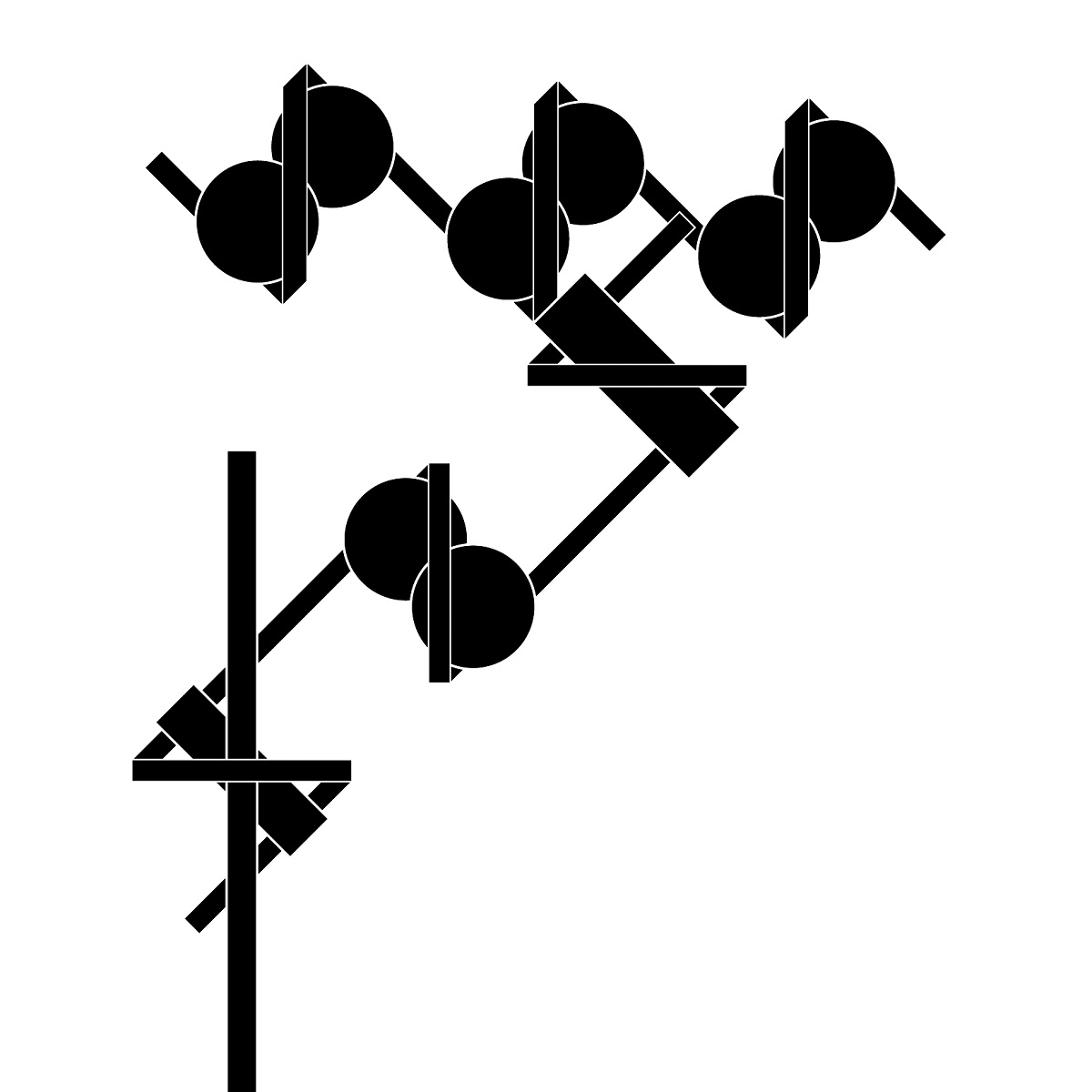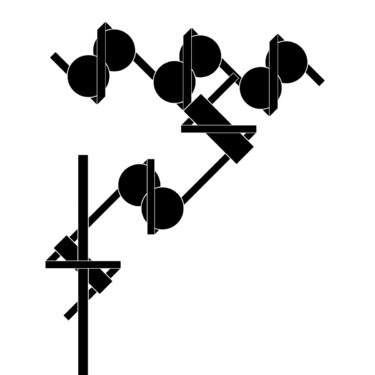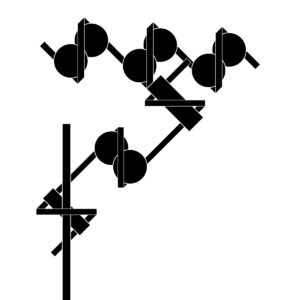<Cross Review>
坂東祐大:ドレミのうた / Do Re Mi
1. Voice Lesson
2. Introduction for Morse Code
3. Morse Code
4. Do-Re-Mi Study i
5. Introduction for Hanon Exercises
6. Hanon Exercises
7. Do-Re-Mi Study ii
8. Invention
9. Do-Re-Mi Study iii
10. Introduction for Fake Solmization
11. Fake Solmization
12. Arpeggio涂櫻(ヴォイス)、工藤和真(ヴォイス)、Sugar me(ヴォイス、ギター)
Ensemble FOVE〔多久潤一朗(フルート、アルトフルート)、中川ヒデ鷹(バスーン)、上野耕平(サクソフォン)、大家一将(パーカッション)、町田匡(ヴァイオリン)〕
望月実加子(小鼓)ほか録音:2020年7月 Endhits studio
Yuta Bandoh Studio/ナクソス・ジャパン株式会社
音楽という慣習がうちにふくむ脆弱さ
松村正人
あるひとがサギをさしてカラスだといい、それを聞いた相手がカラスを知らないならカラスは白い。おそらくここにはことばと意味の指示対象の齟齬があるが、それをシニフィエとかシニフィアンとかいってみてもつまらない。それよりもデリダ的な音声中心主義を高々と掲げるのに音声の受像機である耳にバグがあるというべきか、感受と運動をそれぞれ担う器官のあいだにズレがあるというべきか、それはさておき、坂東祐大の《ドレミのうた》にはボタンをかけちがったシャツを後ろ前に着こんだままフォークダンスをおどるような端然としたいびつさがみなぎっている。
「ドレミ」というだけであって構想は簡素である。簡素なぶん根源的ともいえる。12パートからなる全体は副題ごとに細分化できる。それにより、「ドレミの勉強」と題した主題の幕間に、ハノンやソルミゼーションといった規律訓練型の記号を誇張する対になった2曲が嵌入する構造ができあがる。10分に満たない全12パートを経過するなかで私たちはドレミにまつわる伝統をひととおり浚っていることに気づくのだけど、結果みいだすのは音楽という慣習がうちにふくむ脆弱さである。先にあげたソルミゼーションは口三味線みたいなものだが、口にする音名とじっさいの音高がちがえば、とても奇妙な気分になる。むろん絶対音感もない多くの聴き手にとってドの位置は不動ではない。だからといって音の高さを勝手に決められないのは慣習と体系にかかわるからであって、坂東祐大は《ドレミのうた》でそれらが析出する制度なるものを巧妙に欺いてみせる。
それをさしてサギだといっても、坂東祐大の仕事を知っているひとなら膝を打つだろうしご存じなければ耳を傾け翻弄されるほかない、といいたくなるほど、《ドレミのうた》には音にまつわる多角的な考察が哲学的な含意ばかりか多大なユーモアとともに提示してある。その志向性は本作で終始年端のいかない子どもの声と訓練を受けた声楽の発声を対置するように、パラドキシカルな力線をもち、クラシックというもっとも形式的な形式への自己言及もたぶんにふくむ。そのうえポピュラー音楽、というよりポップアートな側面もチラみさせるのだからたまらない。来たるべき大作の先ぶれだろう――か。
身体化した「ドレミ」への挑発
imdkm
ミュージカル『ザ・サウンド・オブ・ミュージック』に登場する「ドレミのうた(Do-Re-Mi)」。日本でもペギー葉山の訳詞で知られる。「ドはドーナツのド」というあれだ。主人公・マリアは、家庭教師先であるトラップ家の7人きょうだい相手にこの歌で音楽の“いろは”を教える。この歌をみんなで歌ううち、「ドレミ」は身体化されてゆく。ほがらかで楽しげではあるけれど、7人にそれぞれ階名を割り当てて「演奏」するかのようなくだりはちょっとグロテスクだ(映画でいうと、馬車の上で頭をムチで指しながら歌わせるところ)。まるで身体が規律訓練を経て「ドレミ」化されてしまうような。
対して坂東祐大による《ドレミのうた》は、身体化した「ドレミ」=「ドレミ」化した身体にチャレンジし、「ドレミ」をめぐる規範もろとも相対化しようとする。たとえば身体化された「ドレミ」を挑発するようにずらされたソルミゼーションと、それを乗り越えるいびつな技巧。あるいは「ドレミ」化される以前の「どれみ」がトレースされ、ハーモナイズされ、意味づけされていく児戯じみた楽しみ。先の「ドレミのうた」が音楽の世界へのいざないなら、坂東のそれは、その世界のあり方を問う軽やかな探究だ。
とはいえ、そうした探究から逸脱するポイントにもっとも惹かれるのも事実。たとえば「Fake Solmization」で、“偽のソルミゼーション”が次第にひとつの音塊へ溶けてゆくさま。ほぼカットアップとリヴァーブというシンプルな道具立てで編まれるこの音響は、「ドレミ」というモチーフを図から地においやるくらい存在感がある。と同時に、「ドレミ」と同じくらい現代の音楽(とりわけポップミュージック)において重要な、テクノロジーという言語の存在を前景化させてもいる。そのあたりはCorneliusやASA-CHANG&巡礼といった、ポップと音響(そしてことば)のスリリングな邂逅を彷彿とさせる。本作が持つ批評性の核心は、このポイントにあるように思う。
現代音楽の本来的なあり方そのもの
原典子
小学校1年生になったばかりの私の娘は、毎日宿題でひらがなの練習をしている。点線で四等分された大きなマス目に「ふ」「ふ」「ふ」と何度も書いているのを眺めていると、私の頭のなかで「ふ」という文字が4つのパーツに分割され、ゲシュタルト崩壊を起こす。そして、ふと思う。「ふ」という形を指して、なぜ「ふ」と読むのだろう?
気鋭の作曲家、坂東祐大が自身のレーベル「Yuta Bandoh Studio」からのリリース第1弾として発表したこの《ドレミのうた》も、同種の疑問を投げかけてくる作品である。「ド」という高さの音を指して、なぜ「ド」と読むのだろう? もし「ド」の高さの音が「ド」でなかったら……?
12のパーツからなり、トータル9分弱の《ドレミのうた》には、実際の音の高さと、歌われている音名が異なるフレーズがたびたび登場する。たとえばピアノのレッスン教本『ハノン』の「ドミファソラソファミ~」からはじまるおなじみのスケールが、滅茶苦茶な音名で歌われる。あるいは「ドレミ」と歌われているのに、その音は実際のドレミではない。こうした乖離は、楽器を弾く人やソルフェージュを叩き込まれた人にとっては頭を混乱させる代物に違いない。絶対音感のある人には耐えられない苦痛かもしれない。
けれど、「ドレミ」をインストールされていない幼児にとってはどうだろう? 小1の娘に聴かせたところ、なんの抵抗もなく滅茶苦茶な音名を一緒に口ずさみながら踊っていた。まだ音名と音の高さが一致していない彼女にとって、「ドレミ」はドレミではないのだ(ちなみにフランク・ザッパが大好きな夫もなんの違和感もおぼえなかったようだ)。だが、学校の授業で五線譜を習い、ドレミで歌うことを覚えるのはもうすぐ。やがて違和感を抱くようになるのだろう。
ドレミとは? 音楽教育とは? 西洋音楽とは? この作品がしれっと投げかけてくる問いは大きい。伝統に疑問を突きつけ、新たな道を模索する現代音楽の本来的なあり方そのものだとも言える。しかしアカデミックなフィールドに身を置きながら、宇多田ヒカルや米津玄師とのコラボ、ドラマ『大豆田とわ子と三人の元夫』の音楽などを通して、現代音楽をポップにアップデートしてきた坂東の手にかかれば、この通り。違和感や眩暈を通り越して快感すら覚える痛快なアート作品へと見事に昇華されてしまうのである。
音痴の子どもはいないんだ!
小室敬幸
こういった作品をレビューするとなれば、階名(国によっては音名)の起源とされるグイド・ダレッツォ(991/2年頃~1033年以降)に遡りたくなるところなのだが、それは他のどなたかが語ってくださることを期待しよう。
本作を聴いて、最初に頭に浮かんだのが高校時代のある授業だった。私は音楽大学の付属高校に通っていたのだが、1年生の時にコールユーブンゲン(≒声楽のバイエル)を歌うという、ソルフェージュ(≒音感を身につけるための授業)の一端を担う授業を受けていた。
担当の先生はクラシックのピアニストなのだが、スタジオミュージシャンとしても活躍していた方で、移調も即興も自由自在、歌えば純正律で完璧にハモることも出来るという(ちなみにエリートコースではない叩き上げタイプの)方だった。そんな先生がある日の授業で力説していたのだ――「音痴の子どもはいないんだ!」と。
子どもの歌が調子っぱずれな時、それは全く音程がとれていないのではなく、ピアノ譜の調(キー)に合わせられないだけなんだと、そう先生は言うのだ。子どもの歌おうとしているキーに合わせることが出来れば、それまで音程が怪しかった部分もある程度直ってゆくという。つまりは「その歌が音痴かどうかは、適切なハーモニーを付けてからじゃないと判断できない」ということになる。
実際、本作において冒頭の「Voice Lesson」で提起された問題が、「Do-Re-Mi Study」(=作曲の練習・試論としてのStudy)のi・ii・iiiでは主にハーモニー(そして時にリズム)によって、問題ではないことを示されていく過程は、前述した考え方そのものだ。
もうひとつ、本作を語る上で重要となる視点がある。(従来の価値観では)音痴とされる子どもの歌に、伴奏を付けるだけでは、スティーヴ・ライヒのスピーチメロディ技法や、エルメート・パスコアールの「Feira De Asakusa(Asakusa Market)」(浅草のバナナの叩き売りに伴奏を付けた音楽)などのようなものと本質的には変わらなくなってしまう。ところが坂東は、子どもの歌(=訓練される前の自然な歌)だけでなく、人工的に鍛えられたイタリアのベルカント的なオペラの発声をぶつけるのだ。
それによって本作は、あり方としても価値観の上でも対極に位置するふたつの声が共存できる世界を模索するStudyとなっているわけだ。実に現代的な価値観をもった作品であることが、この観点だけでもご理解いただけるはずだ。(坂東にとっては師匠・野田暉行の師匠にあたる)作曲家の矢代秋雄はかつて、美術の世界には子どもの作品ならではの魅力が存在するが、音楽にはそれがない。ただ未熟なだけになってしまう……といった旨の発言を残しているが、本作はそれに反論する狼煙となるかもしれない。
例えば、大友良英やいとうせいこうとのコラボレーションなどでも知られる「音遊びの会」(どんな団体かは是非ググってみてください!)の音を素材にして、坂東が作品作りをしたらどうなるだろう?……という勝手な期待が、本作を繰り返して聴くたびに膨らんだ。