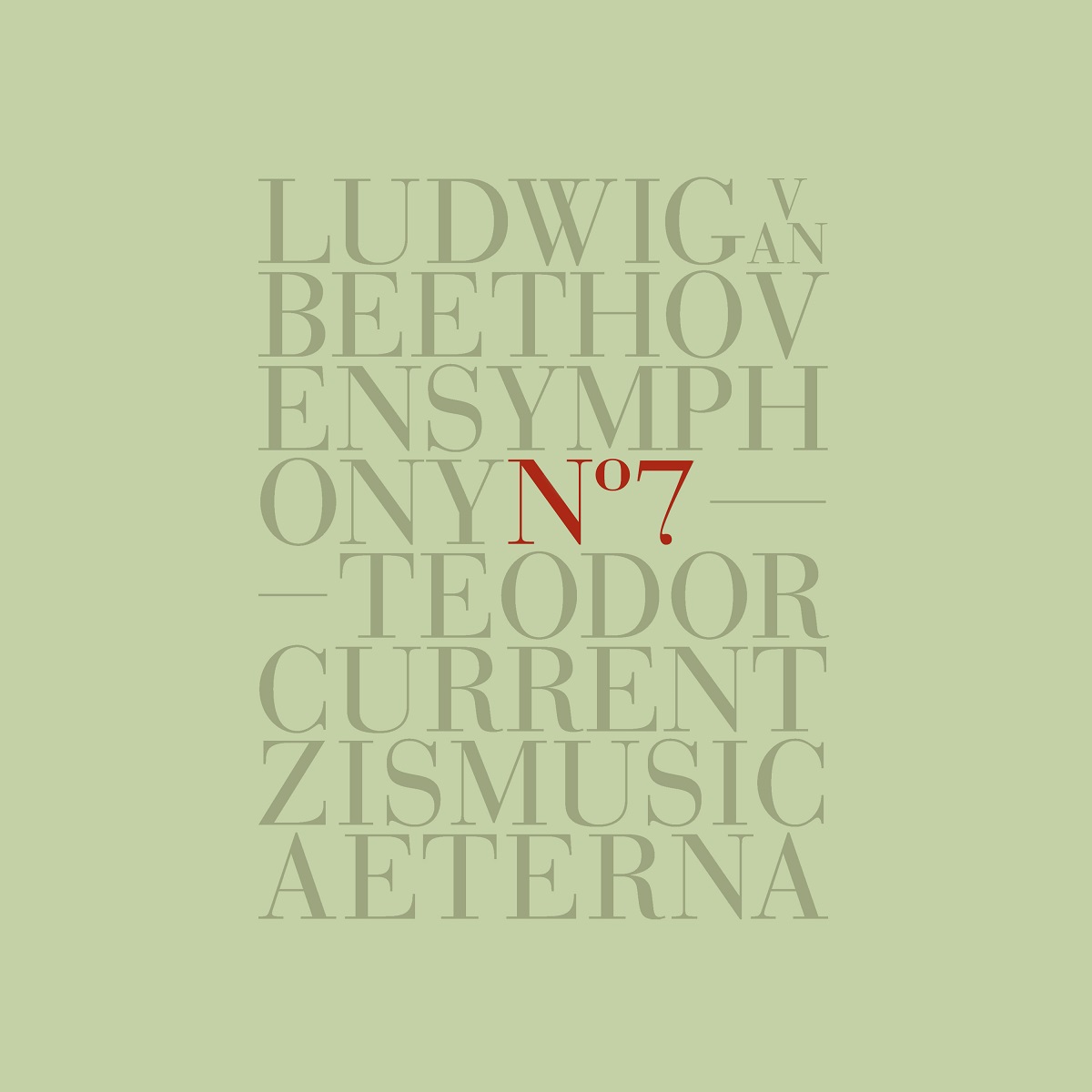<Cross Review>
テオドール・クルレンツィス指揮ムジカエテルナ
ベートーヴェン:交響曲第7番
ベートーヴェン:交響曲第7番 イ長調 作品92
テオドール・クルレンツィス指揮 ムジカエテルナ
録音:2018年7月31日~8月8日 コンツェルトハウス、ウィーン
ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル
既成イメージを粉砕する「生と死のドラマ」
岡田暁生
世が世ならクルレンツィスは、ハードロックのカリスマ・アーティストか、ラディカルな新興宗教の伝道師になっていても不思議ではない人である。彼の音楽の最大の特徴は、既存のものへの激烈なプロテストであり、生ぬるさに安住する人々を震え上がらせる容赦なさであり、その音楽を耳にした人を一瞬で金縛りにするフォースだ。わずか数年でクルレンツィスとその手兵ムジカエテルナ――彼は「私の兵士たち」と呼んでいるそうである――は、世界の音楽マーケットを征服したといって過言ではない。マーケット的なものへのむき出しの敵意にもかかわらず。いや、それ故にこそというべきか。シベリアで結成され、のちにウラル山脈西麓のペルミという都市を本拠地とするようになった彼らは、新自由主義的なクラシック音楽産業によって演出された、おしゃれなゴージャス・サウンドが売りの「スター」たちの殲滅を目指しているようにすらみえる。「生と死のドラマ」という音楽の根源を取り戻すことこそ、彼らの使命なのだ。
ベートーヴェンの交響曲第7番には、すでにあまたの名演が残されている。フルトヴェングラー、トスカニーニ、クライバー等々。だがクルレンツィスは「この曲のあそこはだいたいこんなかんじで、ここはこうして」といった既成イメージを粉砕する。第1楽章や第3楽章、そして何より第4楽章では、まるで獲物の血を口から滴らせる野獣のように金管が咆哮する。他方で第2楽章の葬送行進曲は、野戦病院における死にゆく人々のうめき声のように聴こえる。「名作」扱いされている作品において、ふつうはここまで生々しい表現はしない。それほどのリアルさだ。それからもう一つ。もちろんこれはスタジオ録音なわけだが、このサウンドは「スマホやCDプレーヤーで音楽なんて聴くな!」と言わんばかりの迫力である。ヴァーチャルに逃避せずリアル空間で地面の震動を共有せよ――こういうメッセージとして私はこの録音を聴いた。
パズルを組み立てていくような面白さ
坂入健司郎
はじめてディスク・レビューを書くにあたり、私の立場を明らかにしたい。私は普段、指揮者として活動している。よって、音楽評論家でもないし、まして自分以外の演奏を批判することなどもってのほか。しかし、演奏する立場で書かれたこのレビューが、演奏の好悪などよりもっと大切な演奏側のアプローチを紐解くきっかけや、紹介する録音を手に取って聴いてみようというきっかけになれば、という願いが強く、今回執筆に携わることになった。
さて、本題。今回はクルレンツィスのベートーヴェンの話。指揮者のクルレンツィスは、思いがけず官能的な『モーツァルト:フィガロの結婚』や、聴き手をロック・コンサートでも味わえないような興奮のるつぼに誘う『ラモー:輝きの音』など、録音がリリースされるたびに大きな話題を生んでいるギリシャ生まれの鬼才指揮者。最近はスイスの会社とコラボレーションして香水も販売していて、比類なき極上の香りらしいのだが、いかんせん高価(390€、約50,000円!)なのでなかなか手が出ない。いつか入手して、通りがかる人々をドキドキさせたいものだ。
クルレンツィスは本CDのブックレットにて、ベートーヴェンの交響曲第7番について「かつて書かれた交響曲の中で最も完璧な形式をそなえている」と語り、その構造的な完成度を、自らの故郷・アテネの古典建築と比較して讃えている。なるほど、スコア(指揮者が読む譜面。全てのパートの楽譜が書き記されている)という「設計図」をくまなく眺め尽くした指揮者の思うがままにオーケストラの音が積み上げられていることがわかる。
たとえば低音のナチュラルホルンやコントラバスが打楽器のような音色でリズムを打ち鳴らしたり、普段聴こえないパートをデフォルメして彫刻のような装飾を施したり、細部までパズルを組み立てていくような面白さが楽しめるだろう。指揮者にとって、こうした作業はひとつの「エクスタシー」になりうるかもしれないが……一方で素晴らしい器楽奏者たちが集まったオーケストラが生み出す「音の渦」のような音楽の流れや自発性を丁寧に取り除き、(ギリシャ建築にたとえるならば)オーケストラのパーツは「大理石や石灰石のひとつ」でしかないのも事実。果たしてみなさんはどう捉えるだろう? 現代の「指揮界のカリスマ」だからこそ作り上げられた、指揮者の頭の中を覗くような興味深いアルバム。間違いなく、今回もクラシック音楽界に一石を投じる音盤になったと言えるだろう。
グロテスクな極限までのピアニシモ
八木宏之
今日、ベートーヴェンの交響曲演奏のキーワードとして重要なのは「古楽」と「室内楽的アンサンブル」であろう。アーノンクールやブリュッヘン、ガーディナーといった古楽演奏の先駆者たちが積み上げて来た時代考証に基づくベートーヴェン演奏の新しい様式は、21世紀において主流派となった。また、そうした古楽の影響をモダン・オーケストラのベートーヴェン演奏に落とし込んで行ったアバド、ラトル、ハーディングらの演奏は実に室内楽的で、奏者たちの自発的なアンサンブルに音楽の核が置かれる。古楽的でもなく、室内楽的でもないベートーヴェンの交響曲演奏は今日では珍しくなっている。
ではクルレンツィスとムジカエテルナによるベートーヴェンの交響曲第7番はどうか。これが全く古楽的でもなく、室内楽的でもないのである。何より第2楽章がすごい。冒頭、管楽器による悲痛な響きで幕をあけると、それに続く弦楽器の歩みは聴こえるか聴こえないかの本当に極限までのピアニシモだ。このピアニシモこそ、クルレンツィスの音楽だと私は思っている。かつて聴いたヴェルディの《レクイエム》でも、クルレンツィスはこの信じがたいほどの弱音を巧みに用いていた。クルレンツィスのピアニシモは美しいというよりもむしろグロテスクであり、音楽的というよりむしろ音響的な緊張が聴くものを貫く。
徹底した人工美と指揮者によって完全に掌握された音楽は、セルやカラヤンのそれと似ているようで少し違うものだ。ほんの一瞬でも「ゆらぎ」というものをクルレンツィスは許さない。彼はオーケストラを冷徹なまでにコントロールしているし、その支配はベートーヴェンのスコアにすら及んでいる。他の3つの楽章では音楽の持つエネルギーに任せて突き進むことは決してなく、オーケストラが過度な興奮と熱狂に陥らぬように手綱を引き締め、驚くほどに禁欲的な「舞踏の聖化」を聴かせている。これほどまでに指揮者の意思というものがスコアとオーケストラに貫徹されたベートーヴェンの交響曲第7番の演奏を私は他に知らない。