今こそ「春」を聴く意味
N響4月公演に寄せて
text by 小宮正安
春がはじける!
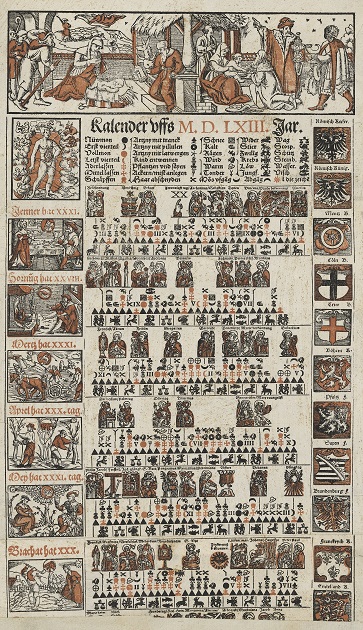
一年の始まりに春を置く……。これはなにも、日本をはじめとする東アジアの地域に限った話ではない。この先ようやく日が長くなり、春への芽吹きが少しずつ始まろうかという時期に新年を設定したヨーロッパもしかり。
そもそもヨーロッパの文化とは切っても切り離せないキリスト教で、聖書には「どの季節の出来事」とも記されていないクリスマスが、ほぼ新年と重なるのも偶然ではない。つまり、キリスト教の教会の戦略としてはこういうこと。世の中に希望の光をもたらす救世主誕生の出来事をリアルに体感してもらうにあたっては、ここから春への道のりが始まるという季節の移わり目こそがベストだった。
そうでなくても、ヨーロッパの冬はうんざりするほど長く厳しい。とりわけアルプス山脈の北側の地域は、下手をすると9月頃には早い秋が訪れ、やがて分厚い雲が一日中空を覆うようになり、ついにはちらほら雪が降り出す。じつをいえばクリスマスや新年が来る頃でも、状況はさほど変わらない。だがそれゆえにこそ、いつまでも続く冬の最中にこの先への希望を少しでも持てるよう、春の予兆に対しては誰しもが敏感になる。
ようやくこの地に本格的な春が訪れるのは、早くて3月、遅くて4月。この日ばかりは浮かれ騒いで、嘘をついても構わない。「エイプリル・フール」という奇習が存在する理由もよく分かる。それはまさしく、春がはじけるという感じそのものなのだ。英語で春のことを“spring (ばねのようにはじける)”と名付けたのも、うなずける話!
切実な憧れ

とはいっても、その昔はヨーロッパやアジアを問わず、今の私たちが「春が来て嬉しい」と単純に喜ぶのとは事情が異なっていた。現在のように自然科学が発達していなかった時代にあって、春の到来は、神に象徴される超人的な存在に司られていると考えられていたから。いい換えれば、自然の圧倒的な力を前に人間があまりにも無力だった、ということになる。
人生を四季に例える考え方が出てきたのも、そうした背景があったため。といっても、ある意味「人生の冬」とされる「老齢」に達すること自体、天の恵みとしかいいようがなかった。幼児死亡率がきわめて高く、平均寿命も現在に比べればはるかに低かった時代の話である。
そんなことを考えると、当時としても若死にとされたモーツァルトが、早すぎる最晩年を迎えた1791年に書いた作品も(この年には歌劇《魔笛》も作られている)、その愛らしい響きとは裏腹に意味深長に思えてくる。なにしろ、タイトルからして《春への憧れ》《もうすぐ春が》。しかも、まさしく人生の春を迎えたばかりの子どもが歌うことが想定されている。そうなのだ。モーツァルトが生きたのは18世紀後半であって、そろそろ近代科学が幕を開けようかという時期である。それでもまだ、世界や宇宙そのものが神の支配の下にあるという考え自体が根強かった。
人間の知恵や力では、正直なところ明日をどうにもできないという現実。あるいは自我の目覚めを覚えつつも、それをどのように発揮してよいか分からず、苦悩の末にみずからの人生の春を摘み取ってしまう若者。モーツァルトと同時代を生きたゲーテが、小説『若きウェルテルの悩み』に描いた青春群像も、この過渡期の産物である。なお、のちにこれをフランス人が翻案した歌劇がマスネの《ウェルテル》だ。
市民の心の拠り所
事態が大きく変化を遂げたのは、19世紀に入ってからのこと。自然科学の発達に伴って、人間にとってそれまで制御不可能だった自然や健康といった分野に、神に代表される超人的存在が影響を及ぼしているわけではない、ということが判明してゆく。さらにいえば、神そのものが疑われてゆく……。
というわけで19世紀のヨーロッパでは、人間が神に代わって世界の中心になり、すべてを支配できる、という考え方が急速に広まった。またこれは、神の権威を盾に社会に君臨してきた教会や貴族といった特権階級のもと、人間扱いさえされてこなかった市民階級がのし上がるにあたって、不可欠な考え方だった。
ただし一方で新興階級である市民は、立身出世の日々を送る中、ときに人一倍戦い、ときに人一倍傷つかなければならなかった。そんな心の傷を癒すにあたって、彼らはなにに目を向けたのか? 普通であれば、それは宗教になるのだろう。だが神の存在が疑問視され、しかも教会自体が長年にわたって特権階級として君臨してきたことを顧みるに、その選択肢はありえまい。そこで市民が着目したのが芸術。芸術もまた19世紀に入ると、特権階級の威光を飾り立てる役割から自立を遂げ、人々に「感動」を与える存在となりつつあった。
とりわけ音楽は、その抽象性ゆえ聴き手の心を多種多様に揺さぶるものとして、台頭を遂げつつあった市民階級にしてみれば、既存の宗教に代わる崇拝の対象となってゆく。いや、ときに音楽はそれ自体で、人々を夢や希望へと駆り立てることとなった。20世紀に入る頃のフィンランド独立運動の中で書かれ、暗から明に至るその内容で聴き手を感動で揺さぶるシベリウスの交響曲第2番などは、その典型である。
自然への新たな眼差し

人間が自然を支配したはずの19世紀にあって、当の自然に回顧的な眼差しが向けられている。
シューマンの交響曲第1番、その名も《春》も象徴的な作品だ。もちろんそこには、待ちに待った春への喜びが満載である。だがそれにもまして、今や市民階級にとって魂の拠り所となった音楽の新たなあり方が示されている。なにしろこの交響曲を書くにあたって、シューマンがインスピレーションを受けたアドルフ・ベトガーの詩からして、新時代の宗教とも呼べるものだろう。その内容たるや、「変えよ、変えよ君の行く道を/谷には春が生まれ咲く!」というものなのだから。
そうなのだ、市民たちが社会の頂を目指して昇ってゆく時代にあって、あえて谷間に目を向けよという内容。しかもその谷間を目指す音楽が、溌剌たる希望に満ちている。19世紀は、人間が神に代わって世界の頂点に立ち、すべてを統御できることが当然のように思われるようになった時代だ。しかもそのただ中で、こうした考えから一歩距離を置く新たな生き方へと、音楽が目を向けさせる。
そう考えると、わが世の春を満喫していたはずの19世紀ヨーロッパにあって、あえて寂莫とした情緒の中に、「春」(《2つの悲しい旋律》より)を書いたグリークも同様だろう。この作品は「過ぎた春」という通称でも知られるが、そのドキリとするような題名には、繁栄に浮かれ騒ぐ社会を前に、それが盛りを過ぎたことを密かに悟り、人生の冬へと向かう音楽家の姿が垣間見えるようだ。しかもこの曲の英訳の定番(意訳だが)は“Last Spring”。「この前の春」という意味なのだが、ばねのようにはじけるはずの生命力は、夢魔戻りのごとく立ち現れるだけだ……。
新型コロナウイルスによる感染症が猛威を振るう今日、人間は自然をコントロールするのではなく、自然と共生してゆくしかない、という意識があらためて芽生えつつある。そうした中で私たちは今あらためて、人間の技の極致ともいえる手段でありながら、そこに人知の及ばぬ世界のあることをも指し示し続けた音楽に耳を傾ける。しかもそれらのテーマは「春」。既存の価値観から、新たな価値観への転換が模索される現在にあって、それはきわめてリアルなものであるにちがいない。
NHK交響楽団 4月公演
■2021年4月10日(土)18:00/11日(日)14:00
サントリーホール
三ツ橋敬子[指揮]
森谷真理[ソプラノ]
福井敬[テノール]モーツァルト:歌劇《魔笛》より
モーツァルト:歌劇《コシ・ファン・トゥッテ》より
モーツァルト:歌劇《イドメネオ》より
ヴェルディ:歌劇《シチリア島の夕べの祈り》より
マスネ:歌劇《ウェルテル》より
マスネ:歌劇《タイス》より
プッチーニ:歌劇《蝶々夫人》より■2021年4月16日(金)18:00/17日(土)14:00
東京芸術劇場 コンサートホール
鈴木雅明[指揮]
吉井瑞穂[オーボエ]ハイドン:交響曲第95番 ハ短調 Hob.I-95
モーツァルト:オーボエ協奏曲 ハ長調 K.314
シューマン:交響曲第1番 変ロ長調 作品38《春》■2021年4月21日(水)18:00/22日(木)18:00
サントリーホール
大植英次[指揮]
阪田知樹[ピアノ]グリーグ:《2つの悲しい旋律》作品34より「胸の痛手」「春」
ショスタコーヴィチ:ピアノ協奏曲第1番 ハ短調 作品35
シベリウス:交響曲第2番 ニ長調 作品43【NHK交響楽団公式サイト】https://www.nhkso.or.jp








