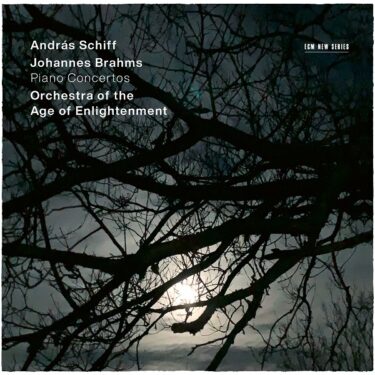<Cross Review>
アンドラーシュ・シフ
ブラームス:ピアノ協奏曲第1番、第2番
ブラームス:ピアノ協奏曲第1番 ニ短調 作品15
ブラームス:ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調 作品83アンドラーシュ・シフ(ピアノ・指揮)
エイジ・オブ・インライトゥメント管弦楽団録音:2019年12月19-21日 アビー・ロード・スタジオ、ロンドン
ECM Records/ユニバーサル ミュージック合同会社
知・情・意のバランスとシフの語り口
坂入健司郎
先日、演奏を終えたあと舞台上からお客様へメッセージを届ける機会があった。舞台上で話すとなれば、明瞭に、ゆっくりと、誰もが聴き取れる声量で話してみようと努力したし、私自身は会心の出来だと思い込んでいたのだけれど、いざ、その日の実況録音を聴いてみれば…想像以上に早口になってしまっていたことに驚き、大いに恥じ、反省した。
——ベルリンにあるフィルハーモニーホールで、はじめてアンドラーシュ・シフのピアノ・リサイタルを聴いた時、まず最初に舞台上での「喋り」が恐ろしく安定していることに感心した。遅い?とも思われるほどに確実な速度で、細やかな発音をホールの隅から隅まで届ける。全く扇情的にならず、確実に喋るので、言葉に慣れていない人でもじゅうぶんに意味がわかる。そのあとのピアノ演奏も含めて彼が音楽において最も大切にしている部分を垣間見た気がしたことを鮮明に思い出した。
今日は、アンドラーシュ・シフがエイジ・オブ・インライトゥメント管弦楽団と共に録音したブラームスのピアノ協奏曲全集の話。
この演奏は、最近では「HIP」という言葉で括られる“演奏における時代考証がなされた“演奏で、オーケストラの使用楽器には、初演された当時の楽器等も使用したスマートなアプローチであり、テンポもスピーディな設定だが、シフの独奏は決して気が急いたような部分は皆無で、丁寧に破綻なく音楽を運ぶ。エイジ・オブ・インライトゥメント管弦楽団の演奏はアーティキュレーション(音と音のつながり、分かれ目の表情)に呼吸感がみなぎっており、実に無理なくブラームスを奏でる。これまでのブラームスのピアノ協奏曲が持つ重厚長大なイメージを良い意味で払拭してくれる素晴らしい演奏だ。
ブラームスの作品には歌ってほしい、ロマンティックであって欲しい、というリスナーも悲しむなかれ。たっぷりヴィブラートをかけて、グリッサンドをしながら歌うようなパッセージも用意してあります。とにかく淡々と知・情・意のバランスをとるアンドラーシュ・シフの妙技を堪能するのみ。そして、いつか彼の語り付きの演奏会にも足を運んでみてください。
「陰影」と水彩画のような淡い色彩の変化
本田裕暉
ブラームスのピアノ協奏曲は、第1番が1859年、第2番が1881年初演と、創作時期に隔たりはあるものの、いずれもシンフォニックな性格を帯びた作品である。そして、もちろんその特徴によるところも大きいのだろうが、普段聴かれるこれら2曲の演奏は「ピアノ入りの交響曲」を地で行くような、重厚で壮大なものが多いように思われる。
だが、この度登場したアンドラーシュ・シフの録音は、そうした重々しいブラームス像とは明らかに一線を画するものだ。今回の演奏のコンセプトはブックレットに記されたシフ自身の言葉に端的に示されている。曰く、「ヨハネス・ブラームスの音楽は、重たくも、鈍くも、分厚くも、騒々しくもない。そのまったく反対――清明で、繊細で、特徴的で、ダイナミクスの陰影に満ちている」(大橋栗生訳)。
「まったく反対」と言い切ってしまってよいのか、という点はさておくとして、確かに本盤で聴くことのできるブラームスは、シフが自由自在に奏でる1859年製ブリュートナー(第1番と同年生まれの楽器!)と英国の古楽器オーケストラであるエイジ・オブ・インライトゥメント管弦楽団とがまるで室内楽を愉しむかのように親密に語らう美しい対話となっており、数多ある従来の録音とは一味も二味も違った魅力に満ちている。
シフのソロは、もちろん熱情が迸るような箇所もあるものの、全体としては節度を保った説得力溢れる歌い口。恣意的なヴィルトゥオジティの誇示とは明確に距離を置きながら、タッチを繊細に使い分けて響きの質感を自在にコントロールすることで、それぞれ50分弱の演奏時間を要するふたつの大曲をひとときたりとも飽きさせることなく聴かせる。他方、オーケストラも随所で見通しのよい清新な演奏を繰り広げており、通常のモダン楽器による録音では響きが飽和してしまうような強奏部であっても立体感を喪わず、しっかりとした「陰影」を感じさせてくれる。そして、例えば第1番冒頭楽章、ガット弦を張った弦楽器がしなやかに第2主題を奏でる部分などで聞こえてくる、ピアノとオーケストラがごく自然なバランスで融けあった響き、あるいは両曲の終楽章に代表される、管弦楽・独奏間での滑らかな主役の交替なども古楽器の使用がじつによく効いている部分だ。さながら水彩画のような、淡い色彩の変化も堪能できる演奏であり、ECMレーベルならではの美しい――ときには少しばかり美しすぎる?――音づくりも、こうした質感の移ろいを心地よく味わわせてくれる。
確かに、本盤以前にも古楽器によるブラームスのピアノ協奏曲の録音はあった。ハーディ・リットナーが1854年製エラールを弾いた2011年の録音(MDG90416996)がそれである。しかし、リットナーが録音したのは第1番のみであり、その意味で、今回のシフ盤の登場はブラームス作品録音史における大きな一歩と言うことができよう。今後これら両作品の録音について語る際には、本盤を避けて通ることはできないはずだ。ブラームスの名曲に新たな光を当てる、まさに蒙を啓いてくれる録音の登場に心より感謝したい。
必然としての弾き振りと時代楽器
八木宏之
ブラームスは青年期と晩年に1曲ずつピアノ協奏曲を作曲したが、両曲とも「ピアノ付き交響曲」と言える壮大な作品であり、ピアノとオーケストラのどちらにも重厚な響きが連なっている。ピアニストはただでさえ難しいソロ・パートをオーケストラに埋もれずに弾かねばならず、その難易度の高さは古今東西のピアノ協奏曲のなかでも屈指のものであろう。さらにオーケストラとの「競奏曲」になってしまっては台無しで、絶えずオーケストラと一体になって、交響的な世界を創りあげることを求められる。そうした負担ゆえに、これまでブラームスのピアノ協奏曲を弾き振り(ソロ・パートを弾きながら同時にオーケストラの指揮も務めること)するピアニストはほとんどいなかった。
アンドラーシュ・シフはこのアルバムでそんな離れ業をやってのけただけでなく、オーケストラとピアノが細やかな対話を繰り広げる、実に室内楽的な協奏を実現した。筆者は2017年にパリで、シフが第2番を弾き振りする公演を聴いたのだが(オーケストラはヨーロッパ室内管弦楽団)、その時はこの作品を弾き振りするというチャレンジの範疇を脱しない演奏に、「指揮者を置けば良いのに」と感じたのを思い出す。しかし今回の録音ではそうしたかつての印象は吹っ飛んで、室内楽的であるために弾き振りを選択した、その必然性を強く感じさせる演奏の説得力に唸らされた。
シフの演奏は作品によっては冷たさを感じることもあるのだが、このブラームスのピアノ協奏曲では過度なロマンチズムは避けながらも暖かみがある演奏を聴かせてくれる。とりわけ第2番は、ブラームス晩年の精神世界に寄り添った、澄み渡る青空の下で黄金色の枯葉が敷き詰められた道を歩むかのような演奏で、この作品の録音史に残る名演であろう。第1番も若々しいというよりは青春時代を回想するかのようなメランコリーがあって魅力的だ。シフの演奏でこれほどまでに惹き込まれたのは、ベートーヴェンの最後の3曲のピアノ・ソナタ以来である。
エイジ・オブ・インライトゥメント管弦楽団の演奏は、ただ単に時代考証に基づいた演奏であるにとどまらず、人生の晩秋に差し掛かったブラームスが聴きたかったのはこんな響きであったのだと思わせてくれる。時代楽器による演奏も弾き振りも、それ自体が目的ではなく、シフが思い描くブラームスにとって必要な選択であったのだろう。前世紀から魅力的な名盤が数多あるブラームスのピアノ協奏曲で、2021年にまだなお新たな名盤が登場したことは何より嬉しく、クラシック音楽の奥深さを感じずにはいられない。